Twin's Story 1 "Chocolate Time"
1-4 禁断の時
明くる8月3日木曜日。
「あんたたち、ケンカでもしてんの?」
夕食時、母親が切り出した。
「え?」マユミが手を止めた。「な、なんで?」
「今朝から会話がほとんどないじゃない」
「そうだっけ?」
「あのね、兄妹ってのは一生で一番長くつき合う人間なんだからね。いがみ合ったりしたらきついわよ」
「べ、別にケンカなんかしてないよ。なあ、マユ」
「う、うん。そうだよ」
「ならいいけど……」

しばらくの沈黙の後、ケンジがマユミに目を向けた。「そうそう、また学校でチョコもらったから、後で食べに来ないか? マユ」
「ほんとに? いくいく」
「誰からもらったっての?」母親が怪訝な顔で訊ねた。
「だから友だちだよ」
「あんたにチョコくれる友だちがいんの。誕生日でもないのに?」
「いいじゃないか、母さん。あんまりしつこくすると嫌がられるぞ」父親がビールのグラスをテーブルに戻して言った。
「ごちそうさま」マユミが食器を持って立ち上がった。
「俺も」ケンジも後に続いた。
二人がダイニングを出て行った後、母親がため息をついた。「何だかうわべだけ仲良くしてるような気がするんだけど、あの二人」
父親が言った。「気にしすぎだ」
先に二階に上がったケンジは、ドアの前で後から上ってきたマユミに声を掛けた。
「マ、マユ、チョコ、一緒に食おうぜ」まるで好きな子に告白できずにいる少年のようにおどおどしながらケンジは赤くなって言った。
「う、うん」
「あ、あの、お詫びと言うか、何と言うか……」
「あ、あたし気にしてないよ、ケン兄」マユミはぎこちなく笑った。「今日はケン兄の好きなコーヒー淹れてくるから待ってて」
「そ、そうか。ありがとう。マユ」
「ケン兄の好きな『ヒロコーヒー』のスペシャルブレンド、今日買ってきたんだ」数日前と同じようにマユミはケンジの部屋の同じ場所にぺたんと座って、デキャンタから二つのカップにコーヒーを注いだ。
「ほ、ほんとか? お、俺のために?」
「うん。いつもチョコごちそうになってるからね」
「すまないな。でもマユ、おまえコーヒー苦手じゃなかった?」
「いいの。たっぷりミルク入れて、砂糖も入れて飲むから」
「ご、ごめんな、無理させちゃって」
ケンジはずっとおどおどしていた。
「このチョコ、」マユミがアソートの箱を手に取った。「この前のと同じだね」
「そ、そうだっけ?」
「友だちからもらったって嘘でしょ。ケン兄」
ケンジは肩をびくつかせた。
「自分で買ったんでしょ?」
ケンジは小さな声で言った。「う、うん。お、おまえ、好きなんだろ? メリーのチョコ……」
マユミは微笑んだ。「ケン兄優しいね」
「だ、だって、お、俺、昨夜おまえにひどい事しちゃったし、その……、こ、こんな事でお詫びになんかならないけど……」
「だから気にしてないって」
「でも、ついこないだ、おまえの悩み相談した時、俺は乱暴しない、って言ったばかりだし……」ケンジはひどく申し訳なさそうに言ってうつむいた。
マユミは顔を赤くして言った。「き、昨日のケン兄のキス、あたし乱暴だって思ってないから」
「ごめん、マユ、本当にごめん。軽蔑しただろ……」ケンジは床に手をついた。「最低だよな、俺……」
マユミはふっと表情を和らげた。
「ほんとに気にしないで、ケン兄」そしてケンジの手を取り、顔を上げさせた。「ケン兄はやっぱり紳士だよ。間違いない」
「え?」
「ちゃんと自分のやった事に向き合ってるし、やっちまった後できちんと謝る、って。そう言ったのケン兄じゃん」
「そ、そうだけどさ……」
ケンジは頭を掻いた。
二人の会話が途切れた。
しばらくしてマユミが小さな声でぽつりと言った。「あ、あたし、ケン兄がお兄ちゃんでなかったら、コクってたかも」
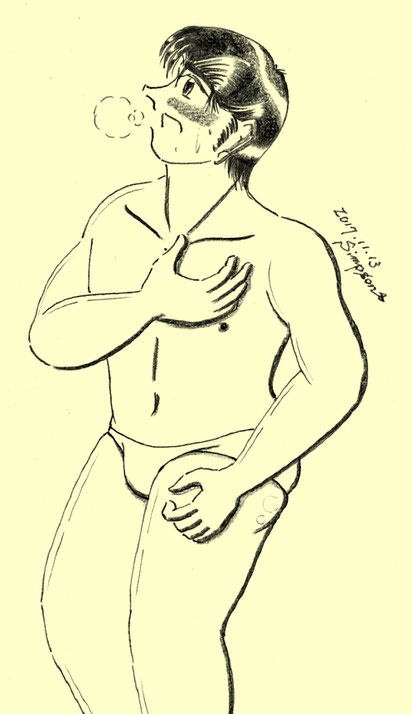
「えっ?!」ケンジは赤面した。
マユミの身体がまた疼き出した。耳が熱を持ち、鼓動が喉の辺りで聞こえた。彼女は焦ったように自分のコーヒーを飲み干すと、立ち上がった。
「じゃ、あたし勉強があるから。ごちそうさま。残ったチョコ、ケン兄が食べて」
返事も聞かずマユミはカップの載ったトレイを抱えて部屋を出て行った。
マユミへの想いは、治まるどころか前日よりももっと強烈なものになっていた。ケンジはベッドに横になってからも身体の火照りが冷めず、なかなか寝付かれなかった。彼はベッドから降りて暗い部屋に立ち、全裸になった。すでにペニスは天を指して脈動を始めていた。
ベッドに隠していたマユミの白い小さなショーツを取り出すと、それを身につけた。胸が締め付けられるように痛んだ。呼吸も荒くなってきた。「マユ、おまえを……抱きたい」小さなマユミのショーツの中ではち切れんばかりに怒張した彼の分身はその先端から透明な液を漏らし始め、穿いていた妹の下着にシミを作った。
マユミは昨夜と同じようにケンジの黒いTシャツを素肌に身につけ、ベッドに横になった。それだけで彼女の身体はどんどん熱くなっていった。ショーツを脱ぎ去り、躊躇う事なく彼女は指を自分の秘部に宛がった。そして敏感な部分をくまなく刺激した。「ああ、ケン兄、あなたに抱かれたい……」
マユミは行為の後、しばらくじっとして息を整えた。暗い部屋の中、放心したようにベッドの上に横たわっていた。
ふと彼女は壁越しに聞こえる隣の部屋の物音に耳を澄ませた。数日前と同じようにベッドの軋む音とケンジの息を殺した声が聞こえた。
かすかに聞こえる兄の声、「マユ、マユ、ああ……」という喘ぎ声……。
それを聞いたマユミは、ショーツを穿き直すと決心したように部屋を出た。
コンコン。ケンジの部屋のドアがノックされた。もう少しでマユミを想いながら登り詰めるところだったケンジは、ベッドの上で凍り付いた。
「ケン兄、起きてる?」マユミの声だった。
ケンジは慌ててハーフパンツとシャツを身につけ、部屋の灯りをつけてドアを開けた。
「ど、どうしたんだ? マユ」
「怖い夢をみちゃって……」切なそうなマユミのその声に、ケンジの胸はまた締め付けられるように疼いた。
「入りなよ」
「ごめんね。起こしちゃった?」
「平気だ」
「ね、ねえ、ケン兄、」
「何だ?」
「今夜は一緒に寝てくれる?」
「えっ?!」
「一人じゃ心細くて……」
ごくりと唾を飲み込み、ケンジは少し震える声で言った。「わ、わかった。お、俺のベッド使いなよ」
「うん。ありがと」
マユミはあっさりとケンジのベッドに腰掛けた。
「で、どんな怖い夢をみたんだ?」
「ケン兄が遠くに行っちゃう夢」
「俺が?」
「そう。もうあたし、辛くて、寂しくて、悲しくて……」
「俺はどこにも行かないよ。お、おまえを一人になんかしたりしないよ」
ケンジのぎこちない、しかしひどく優しいその声を聞いたマユミの眼から涙がぽろりと落ちた。
「さあ、もう寝なよ。俺は床でいいから」
「ケン兄も一緒に来て」
「えっ?!」
「一緒に寝てよ。昔みたいに」
二人は小学校を卒業するまで一つのベッドで寝ていた。マユミは寂しがり屋で、いつもケンジの手を握って眠りについていた。当時ケンジはそんな妹が鬱陶しくて、早く一人でベッドを占領したいとずっと思っていた。

ケンジは恐る恐るマユミの隣に横になった。しかし妹に背を向けていた。「ごめん、マユ、狭いだろ」
「この方がいい。だってケン兄といると安心できるもん」そう言ってマユミはケットの半分をケンジの身体に掛けた。
「じゃ、じゃあ、灯り消すから」
「うん」
ケンジは枕元の灯りを消した。
部屋は完全には暗くならなかった。ベランダの窓から、家の近くに立っている街灯の白い灯りが、部屋全体をぼんやりとモノトーンに染めていた。
しばらく沈黙が流れた。ケンジは自分の熱い呼吸音をマユミに聞かれるのが気まずくて必死で息を殺していた。しかし背中に寄り添ったマユミの身体の温もりと柔らかさと甘い匂いがケンジの身体をどんどん熱くしていく。身体の中心にある分身も熱く硬く大きくなって脈動を始めている。もはやケンジはこのまま眠りにつく事が叶わない程爆発寸前に高まっていた。
「ケン兄、」
マユミが囁くような声で言った。
「…………」ケンジは荒くなっている呼吸をこれ以上抑えるのは不可能だと諦めかけていた。
マユミは背後からケンジのシャツをめくり上げた。そして汗ばんだ素肌に直に触れたまま腕を前に回し、彼の胸を優しくさすった。
ケンジはびっくりして声を上げた。「マ、マユ!」
「ケン兄、あたし……」
マユミは手をケンジのハーフパンツの中に忍ばせた。そして彼が身につけたままの小さなショーツの上から、ペニスに軽く触れた。
「あ!」ケンジはビクンと身体を硬直させた。
「ケン兄……お願いが……あるの」
「マ、マユ……」
「あたしを……抱いて」
「マ、マユっ!」ケンジは我慢できず二人の身体に掛かっていたケットをはぎ取った。そして身体を起こすとマユミに乱暴に覆い被さり、その口を自分の唇で塞いだ。またカチリと歯がぶつかる音がした。
「ん、んんっ!」マユミは一瞬苦しそうに呻いたが、すぐにケンジの濃厚なキスを受け入れ、同じようにその唇を味わい始めた。
ケンジは、キスを続けながら、着衣越しにブラを着けていないマユミの豊かで柔らかい乳房をさすった。「んん……」マユミはまた小さく呻いた。
口を離したケンジは、マユミが身に着けていたシャツをめくりあげ、露わになった乳房を夢中で吸った。
「ああ……、ケン兄!」
ケンジははっとしてマユミから身を離した。
「ご、ごめん、マユ、お、俺、乱暴だよな?」
「平気だよ。大丈夫」マユミはそう言って上気した顔をほころばせた。「きて、ケン兄」
マユミはゆっくりとシャツを脱いだ。露わになったバストが、薄暗い中でも白く浮き上がって見えた。
「マユ……。優しく、するから」ケンジは我慢できない様子で着ていたシャツとハーフパンツを脱ぎ捨て、マユミの身体を抱きしめた。そして彼女の耳元で申し訳なさそうに囁いた。
「マユ、ごめん、実は俺……」
「どうしたの?」
「おまえの下着、盗んだ」
「やっぱり、これあたしのショーツだったんだ。でも何だか嬉しい。気にしないで、ケン兄」マユミはそう言いながらケンジの穿いていた自分のショーツにそっと手を触れさせた。
マユミは躊躇いがちに言った。「あたしの中にきて、ケン兄。お願い」すでにマユミの秘部はしっとりと潤っていた。
ケンジが大きくごくりと唾を飲み込む音が聞こえた。
「……い、いいのか? マユ、お、俺で、いいのか?」
「あなたに抱いて欲しいの。きて、お願い」
自分でショーツを脱ぎ去り、マユミのそれもはぎ取って全裸にしたケンジは、焦ったようにマユミに体重を掛けて覆い被さった。マユミは少し恥じらいながら両脚を少しずつ広げていった。
「マ、マユ……」
マユミは両手で顔を覆っていた。「ケン兄……」
ケンジは身体を起こした。
「マユ、さ、触っても……いいか?」
「……うん。でもそっとね、そっとだよ」マユミはくぐもった声で応えた。

ケンジは、息を止めて、人差し指の先で、初めて見る女性のその部分に触れてみた。いつしか暗い部屋の中でも目が慣れてきて、うっすらと生えそろったマユミの秘毛や、汗ばんだ太股がケンジの目にくっきりと映り込んだ。
彼は、マユミのその大切な場所の合わさった襞を少し開いて、ほんの少し指先をその中に差し入れてみた。
「あっ! ケ、ケン兄」
ケンジはびっくりして手を引っ込めた。「ご、ごめん、い、痛かったか?」
「ううん。違うの、大丈夫、ケン兄続けて……」
ケンジは再び指を、そのぬるぬるした感触の柔らかい粘膜に触れさせて、ゆっくりと上下に動かした。
「マ、マユ……すごいよ……柔らかくて、温かくて……。トロトロしてる……」
「……恥ずかしい……」マユミは顔を覆ったまま小さな声で囁くように言った。
いつしかケンジのペニスははち切れんばかりに大きく、硬くなって、びくびくと脈動を始めていた。先端からも透明な液が漏れている。
マユミは決心したように言った。「ケン兄、あたしの中に、入ってきてもいいよ」
「い、いいのか? マユ、本当に、いいのか?」
マユミは黙って大きく頷いた。
ケンジは最高に怒張した自分の分身を彼女の秘部に宛がった。
「いくよ、マユ」
「きて、きて……」
ケンジのペニスの先端は十分に潤っていた。手で握ったままケンジはそれをマユミの中に挿入し始めた。しかし、そこはひどく狭くて、簡単には先に進んでいかなかった。
「あ、あああ……ケン兄」
「マ、マユ、痛かったら、いつでも言いなよ」
「だ、大丈夫。痛くない。大丈夫」はあはあと荒い呼吸を繰り返しながらマユミは固く目を閉じ絞り出すような声で言った。
ケンジのものは少しずつだが、マユの谷間を押し広げながら中に入っていった。同時にケンジの腰の辺りの疼きはどんどん強くなっていき、限界が目の前に迫ってきた。
ケンジの身体には、いつしか汗がびっしりとこびりついていた。
「マユ、マユっ!」
ケンジは腰をしきりに突き出し、マユミの中に入り込もうと必死になっていた。しかし、途中ひどく狭くなっている所に阻まれ、思うように先に進まないままだった。
「マユ、も、もう俺……」
ケンジは苦しそうに歯を食いしばっている。

マユミはとっさに両手でケンジの腰を捉え、その逞しい大臀筋を鷲づかみにした。
「えっ?! マユ?」
そして、腕に力を込めて、上になったケンジの腰を力任せに自分の秘部に押し付けた。
その途端、ケンジのペニスは、狭い所を無理矢理押し開いたかと思うと、一気にマユミの身体の奥深くまで到達した。
「いっ!」その瞬間、マユミは仰け反り大きくうめき声を上げた。「んんんっ!」
「うあっ!」ケンジも思わず叫んだ。
そしてついに、ケンジは臨界点を超えた。
「出、出るっ!」
どくん!
「んっ、んんっ!」
ケンジはびくびくと腰を大きく脈動させながら襲いかかってきた強烈な快感に身を任せていた。
びゅくびゅくびゅくっ! びゅるるるっ!
マユミは、今まで感じた事のない燃えるような激しい痛みを秘部に感じていた。眼からは涙がぽろぽろとこぼれていた。
脈動が収まって、ケンジはマユミを見下ろした。
涙を流しながら苦痛に顔を歪ませている妹を見た途端、ケンジは焦って腕を突っ張った。
「マ、マユっ!」
「ケン兄……」
「だ、大丈夫か? マユ」
「うん。大丈夫だよ」マユミは照れたように指で涙を拭って、力なく微笑んだ。
「痛かったんだな? 俺、おまえに痛い思いをさせちまったんだな?」ケンジはうろたえて、身体をマユミから離そうとした。するとマユミはとっさにケンジの背中に腕を回し、ぎゅっと抱きしめた。ケンジは肘を折り、マユミの身体にのしかかった。
「だめ! まだ離れないで!」
「マユ?!」
「離れないで、お願い。そのままあたしにくっついてて! ケン兄、好き、大好きだから!」
ケンジは少し胸を浮かせ、自分の体重がマユミに掛からないようにして、荒い呼吸を落ち着かせながらしばらくじっとしていた。
ゆっくりと顔を上げたケンジは、数回瞬きをして、切なそうな表情でマユミを見下ろした。「マユ……、俺も、おまえが……」そしてはにかんだように唇を噛んで、また彼女の柔らかい身体を抱きしめ、耳元でそっと囁いた。「大好きだ……好きで好きで堪らない。もう離したくない……」
「ケン兄……嬉しい……」マユミは幸せそうに長く熱いため息をついた。
「ケン兄の……おっきいんだね……」
マユミが小さな声で言った。
「痛かったんだろ? マユ……」ケンジはまた言った。
「少しだけね。でも平気だよ」
マユミはケンジの目を見つめて微笑んだ。
ケンジとマユミは繋がったまま、お互い顔を赤く上気させ抱き合っていた。
「男のコってさ、」
「うん」
「その……出しちゃった後って、無反応になる、って聞いたけど」
「一人でやる時はそうだな。無反応というより、めちゃめちゃ虚しくなる」
「なんで?」
「やっぱり、相手がいないからじゃないかな」
「今はどう?」
「なんか、今までにない幸福感がある」
「幸福感?」

「そうさ。好きな女の子と抱き合えてるんだ。幸せじゃないわけないだろ」
マユミは恥じらったように微笑んだ。
「出す時、どんな感じだった?」
「あんまり……よくわからなかった」
「気持ち良くなかった?」
「大好きなマユを抱いている、っていう事の方が気持ちいい気がする」
「出す瞬間って、すごい快感があるんじゃないの?」
「なんか……夢中で……」ケンジは恥ずかしげに言葉を濁した。
「ケン兄って、出してもちっちゃくならないの? まだ、あたしの中でびくびくしてるみたい……」
「そ、それは……」ケンジは顔を赤らめ、腰をもぞもぞさせた。
「もしかして、出してない……とか」
「い、いや、そうじゃない。ちゃんと、って言うか、さっきは確かに出した。いっぱい……出したけど……」
ケンジはますます顔を赤らめた。そして小さな声で続けた。「またイきそう……」
「ほんとに?」マユミはちょっと驚いて言った。「すごいね、ケン兄」
マユミがそう言った時、ケンジは腰を浮かせて大きくなったままのペニスをマユミの秘部から抜き去った。
「え? どうしたの? ケン兄」
「い、いや……」
「もう一度、あたしの中でイけばいいのに……」
ケンジはベッドの上に正座をして静かに言った。
「マユは初めてだったんだろ?」
「うん」マユミも身体を起こした。「あ、ケン兄、ティッシュちょうだい」
「え? あ、う、うん」ケンジは慌ててベッド脇のティッシュボックスを手にとってマユミに渡した。
マユミは数枚のティッシュを手に取り、ケンジに背を向けて少し焦ったように自分の秘部に当てた。
「ご、ごめん、マユ。お、俺の出したもの、漏れてるのか?」
マユミは恥ずかしげにケンジに振り返り、顔を赤らめた。
ケンジは枕元の電気スタンドのスイッチを押した。そして、何気なく自分のまだ衰えを見せないペニスを見た途端、息を呑んで、大声を出した。「マユっ!」
「な、なに? どうしたの?」マユミはびっくりして顔を上げた。
「こ、こんなに血が付いてる……」
マユミは落ち着いた声で言った。「当たり前じゃん。初めてだったんだもん」
「お、おまえめちゃめちゃ痛かったんじゃないのか?」
マユミは呆れたように言った。「もう、ケン兄、しつこ過ぎだよ。何度も訊かないで」
「だ、だって、おまえ……」ケンジは泣きそうな顔になっていた。
マユミはケンジに近づき、そっと腕をその逞しい胸に回してきゅっと抱いた。そして耳元で囁いた。「心配しないで、ケン兄。あたしは平気。大好きなケン兄があたしの中に入ってきた、って事だけでもすっごく幸せで気持ちいいんだから」
「マユ……」
「ねえ、ケン兄、もう一度イきたいんだったら、あたしの中に来て、出してもいいよ、もう一回」
「えっ?!」
「入れたいんでしょ? また」マユミは悪戯っぽく笑った。
ケンジはしばらく固まっていた。そして彼の中心にあるものは、大きく脈動していた。
マユミは再びベッドに横たわり、灯りを消した。
「いいよ、ケン兄」
ケンジは出し抜けにシーツの上に置いていたティッシュボックスから焦ったように数枚ティッシュを取り出すと、マユミに背を向けた。
「ケン兄?」

ケンジは右手をしきりに動かしていた。そして、すぐに「マユ、うっ!」と唸り声を上げて、背を丸め、身体を数回びくびくと脈動させた。
背後からその様子を見ていたマユミは、再び身体を起こした。
「ケン兄……どうしたの?」
振り向いて切なそうな目でマユミを見たケンジは、荒い息を整えながら、ゆっくりと妹の名を呼んだ。「マユ……」
「もしかして、一人で出しちゃったの?」
ケンジの手に握られていたティッシュの包みを見て、マユミは言った。「あたしとエッチするの……いやなの?」
ケンジはそれをゴミ箱に捨て、ゆっくりとマユミに向き直った。
「マユ、今夜は一回で十分さ」
「え?」
「いわば俺、おまえに傷を負わせちまった。ケガしたすぐ後に、その傷口を刺激する事なんかできないよ。大切な妹だからな」
「ケン兄……」マユミは涙ぐんで兄を見つめた。
「その代わり」
「うん」
「明日もおまえを抱きたい。抱いてもいいか?」
「……嬉しい、ケン兄、ケン兄……」
マユミはケンジにすがりついて、本格的に泣き始めた。
「マ、マユ」ケンジはおろおろしながら、それでもマユミの身体をぎゅっと抱きしめた。
ホーム|Chocolate Time シリーズ 本編第1期 本編第2期 外伝集|Chocolate Time シリーズ総合インフォメーション




































