Twin's Story 2 "Bitter Chocolate Time"
《4 改心》
腕の故障で競技に出ることができないケンジは、大会の間、プールサイドで仲間の泳ぎをずっと見ていた。左腕には大げさに包帯が巻かれ、首から吊られていた。それはケネスのアイデアだった。
すぐ近くにアヤカはいて、ストップウォッチと記録用紙を片手にまめに働いていた。
マユミは自分のチームのメンバーといっしょに行動しながら、時折ケンジやアヤカの動きに目をやった。
午前の競技が終わり、昼休みに入ったところで、ケネスの推測通り、アヤカが動き出した。
ケンジがプールの入り口から出て自分の学校の控え場所まで一人で移動していた時、背後からアヤカが彼を呼び止めた。
「海棠くん」
ケンジは何食わぬ顔で振り向いた。「なんだ、アヤカ」
「話があるんだ。付き合って」
ケンジはアヤカの背後にかなりの距離を置いてついてきていたケネスに目配せをした。ケネスは小さく頷いた。
アヤカはケンジを人気のない更衣室に連れ込んだ。
「なんだ? 話って」
「昨日は興奮した? 初めてだったんでしょ? ああいう体験」
「何の話だ?」
「自分に正直になれば? ケンジくん。また私にされたいんじゃない?」
「ごめんだね」
「私はまたしたいな」アヤカは不敵な笑みを浮かべた。「あなたには断る権利はないから」
「どうして?」
「あれ? いいのかな? 昨日の写真とかビデオとか、公開しちゃうよ」
ケネスの筋書き通りにコトが進んでいた。
「好きにしろよ。俺は別に構わない。お前の言いなりになんかならないし、お前を抱こうとも思わない。もう二度とね」
更衣室のドアの横に身を隠して、二人の様子を窺っていたケネスは小さくガッツポーズを決めた。「(思った通り、あいつはデータがなくなっていることに気づいてへんな)」
「へえ。そうなんだ」
「話ってそれだけか? 俺、昼飯食べなきゃいけないから」ケンジが出口に向かって足を踏み出そうとした時だった。
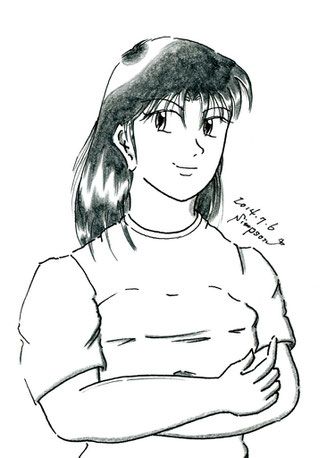
「そう言えば、昨日私とエッチしてる時、ケンジくん、『マユ』ってつぶやかなかった?」
ケンジの心臓が一瞬止まりそうになった。「え?」
「確かに言った。マユって妹のマユミのこと、だよね?」
「…………」
ケネスも凍り付き、青ざめた。
「エッチの時に名前を呼ぶなんて、普通じゃないよね。ケンジくん、妹のマユミとはどういう関係?」
「そ、それは……」
「まさか、」アヤカはケンジに近づき、下から見上げるようにしてケンジの顔をしげしげとのぞき込んだ。
ケンジはゆっくりと口を開いた。「これだけは隠しておきたかったんだけど、そこまで勘ぐられたんじゃ、話すしかないか」
ケネスは歯ぎしりをして拳を握りしめた。
「俺、たぶんシスコンなんだ」
「シスコン?」
「そう。妹のことが可愛くて、愛しくてたまらない」
「へえ、そうなんだ」アヤカは腕を組み、にやにやしながら聞き返した。「それで?」
「だから、あいつがケニーと幸せになって欲しいと思ってる」
「(へ?)」ケネスの頭上にクエスチョンマークが飛び出した。

「妹は俺の親友ケニーと付き合ってる。もちろんすでに深い仲だ。だからあいつを幸せにできるケニーが日本に定住することになって、俺は心から喜んでるんだ」
「でもどうしてエッチの時にマユミの名前をつぶやくわけ?」
「ケニーとあいつが愛し合っているところを、俺は見てしまったんだ。そのことが、その光景が頭から離れない。強烈に記憶に残ってる」
「ふうん」
「その時は俺も自然と身体が熱くなって、もう少しで漏らすところだった。でも相手がケニーでなければ飛びかかって引き離していただろう。その時のことを思い出したのさ」
「なんだ。あんまりおもしろくない」アヤカは期待外れの顔をしてため息をついた。
「もういいだろ」ケンジは頬を少し赤くして、再びその部屋を出て行こうとした。
「待って」アヤカが呼び止めた。ケンジはドアのところで立ち止まった。すぐそばの外の壁にケネスがアヤカからは見えないように張りついている。
「私、そのケニーともエッチしたんだ。知ってるよね」アヤカの声が低くなった。
ケンジは黙っていた。
「私、きっと病気なんだ」
「病気?」
「心の病気。誰にも相手にされない寂しさやむなしさが、悔しさや怒りになって攻撃をしたくなる」
「いや、お前何人ものオトコに言い寄られてるじゃないか」
「みんな私のカラダ目当てだってこと、わかるもん。そんなのいや」
「だからって、」
「そう、だからって、あなたやケニーを無理矢理捕まえてエッチしたって、心の病気が治るわけじゃない。それはわかってる」
「アヤカ……」
「海棠くん……」アヤカはひどく落ち込んだようにうつむいたまま言った。「私、どうしようもない女だよね」
「……」
「こんなことしてもあなたが私を好きになってくれるわけないのに……」
「…………」
「私、海棠くんが朝から腕に包帯しているのを見て、ああ、私のせいで怪我がひどくなったんだろうな、って思った。でも、だから何なの? って思ってた」アヤカは少し笑った。「悪魔みたいだね、私。でも、海棠くんが妹のマユミのことそれほどまでに想っているのに、ケニーと幸せになることを願って、マユミの本当の幸せを祈ってることを知ったら、自分のやったコトが急に恥ずかしくなってきちゃった……」
「アヤカ……」
「もう、何言ってるかわからないよね……」
「人の心は自分の思い通りにはならないよ。なかなか」
「信じてもらえないかもしれないけど、私、海棠くんのことが、ずっと純粋に好きだったんだよ。海棠くんに抱かれたら、どんなに幸せだろう、ってずっと思ってたんだよ」
アヤカは涙声になっていった。
「海棠くんのことを想いながら、一人で濡らして、一人で慰めてた。毎晩のように」アヤカは顔を上げた。「でも勘違いしないで、私、海棠君とのエッチだけを望んでたわけじゃないよ、貴男と二人きりで話したり、貴男と一緒に食事したり……。ちゃんと普通の恋愛感情もあったんだよ」
ケンジは黙っていた。
「でももう手遅れだよね。私、インランな女子高生に堕ちちゃってるよね」アヤカはまたうつむいた。「結局貴男は……私が何を言っても、何をしてもこっちを見てはくれなかった」
「残酷なこと言うようだけど、俺、お前を好きにはなれない」
「当然だよね」アヤカは涙を右手で乱暴に拭って言った。「あんなヒドイことしたんだもんね。当然だよ……」そしてケンジから目をそらし、小さな声で言った。「私のやったことは犯罪だよ……」
「悪いけど、お前の気持ちは受け止められない。でも、少なくとも憎んではいない」
「え?」アヤカは顔を上げ、目を大きく見開いた。
「他の女子に対する気持ちと、あんまり変わらない」
「海棠くん……」
「俺には、幸運なことに今、思い切り好きな人がいるんだ。だから他の女子を好きになれるわけがない。それだけだ」
「知ってる……」アヤカは独り言のように呟いた。「康男君たちから聞いた」
「そうか……」
「私、それを聞いちゃったから、あんなことしたのかも知れない……」
アヤカの目からぽろぽろと涙がこぼれ落ち、彼女の荒々しく大きな声がロッカールームに響いた。「海棠くんが他の女のモノだって、信じたくなかった!」
ケンジのバッグの中から短いチャイム音が鳴った。彼はバッグのチャックを開けて自分のケータイを取り出すと、ディスプレイを見た。ケネスからの空メールだった。ケンジは右手でキー操作してすぐにディスプレイを閉じた。
アヤカは右手で乱暴に涙を拭った。そして洟をすすって目を上げた。「海棠くんの好きな人から?」
「……うん」
「深い仲なの? もう」
ケンジは少し間を置いて言った。「いいや」
「その子も海棠くんのことが大好きなんでしょ?」
「この大会が終わったら、俺の方からちゃんとコクって確かめる」
「……真剣なんだね、海棠くん。きっとうまくいくよ」アヤカはうつむいた。
「そうだといいけどな」
アヤカは小さく震える声で言った。「昨日の私との出来事もその人に話す?」
ケンジはアヤカの目を見つめ返した。「俺は忘れたい。お前も覚えてて欲しくないだろ。仮に昨夜のことを彼女に話したとしても、お前がますます悪者になるだけだ。そんな意味のないこと、俺はしたくない」

アヤカはまた目を伏せた。「海棠くんの好きな人って……誰? 私の知ってる人?」
ケンジは少し躊躇した後、小さく言った。「ああ」
二人の間にしばらくの沈黙があった。
「……幸せだね、その人。こんなに優しい人に愛されて……」
「アヤカ……」
「それが誰かなんて、私訊かないよ。大丈夫。聞いてしまったら、また何しでかすかわかんないからね」アヤカは目に涙をためたまま、ぎこちない笑顔を作った。
「お互いに忘れてしまおう。アヤカ」
「私、あなたに抱いてもらって、幸せだった」アヤカの目から、また涙が頬を伝った。
「俺、抱いてないし」ケンジは少し赤くなった。
「ううん。私にとっては抱かれたのと同じ」
アヤカは本気で泣き出した。「本当は優しく抱いて欲しかったけど、ああでもしないと私とあなたは繋がれないって思った」しゃくり上げながらアヤカは続けた。「ごめんね、ごめんね、ごめんね……ケンジくん」
ケンジはアヤカに向き直ると、右手を肩にのせた。アヤカは涙目でじっとケンジを見つめた。二人はしばらく見つめ合っていた。ドアの陰からケネスがその様子を固唾を呑んで見守っている。
「アヤカのことをわかってくれるヤツがきっと現れるよ」ケンジは手を離した。
「ありがとう、海棠くん……」
◆

「っちゅうわけでな、あんまりおもろい展開やなかってんで」
「そうなんだー」
その晩、ケネスがケンジの部屋でマユミに昼間の様子を話して聞かせていた。
「マーユもその場にいたらそう思たと思うで」
ドアが開いて、ケンジが三つのコーヒーカップとデキャンタの載ったトレイを持って入ってきた。「誰のことだよ、『マーユ』って」
「マユミはんのことに決まってるやんか」
「そうか、お前もやっと打ち解けて俺たちと話してくれるようになったか」ケンジは嬉しそうに言った。
「その代わり、」ケネスはマユミに向き直った。「わいのことも『ケニー』って呼んでくれへん?」
「え? いいの?」
「もうええやろ。こうして図々しく部屋に何度もお邪魔してんのやから」
「わかった。そうする」マユミはにっこり笑った。そしてケンジの顔を見て言った。「ケン兄、今日はがんばってくれてありがとう」
ケンジはカーペットの上にトレイを置いた。
「腕、痛くない? ごめんね、あたしがコーヒー淹れてくればよかったね」
「大丈夫。もう痛みもほとんどないんだ。少しだけ違和感がある程度。マユもいつも通りに抱ける」
「ケン兄のエッチ」ケネスが言った。マユミがまた笑った。
「そやけどあの包帯もアヤカには効かなかったっちゅうのは、なかなか悔しい」
「いいアイデアだと思ったんだけどな」
「アヤカんちで撮ったボイスレコーダーのデータも用無しになってしもた」
「ボイスレコーダー? 何でそんなもの持ち歩いてんだよ、お前」
「語学の練習用やんか。日本語うまくなりたいよってにな」
「練習する必要あんのかよ」
「わい、日本語ようしゃべらへんねん。大阪弁やったら達者やねんけどな」
「あほか」
マユミが笑いながら訊いた「で、そのボイスレコーダーのデータって?」
「わいがアヤカに犯されてる時のアヤカの声が録音されてるんやで」
「犯されてる?」マユミは赤くなった。
「あれはエッチとは言われへん。わいはアヤカのおもちゃやった」
「おもちゃねえ……」ケンジがコーヒーをすすりながら言った。
「聞いてみるか? 二人とも。臨場感たっぷりやで」
「え、遠慮する」マユミが言った。「俺も」ケンジも即答した。
「そうか、そら残念や」
「何が残念なんだか……」
「このデータ、アヤカが知らばっくれた時の切り札やったんやけど……。おお、そうやった。忘れとった」ケネスはバッグからアソート・チョコレートの箱を取り出した。「親父の特製アソートや」
「ケニーのパパがショコラティエだったなんて、すごいよ」

「普通のチョコなんだろうな? これ」ケンジがいぶかしげに訊ねた。
「催眠剤入りや。マーユを眠らせて、ふっふっふ……」
「じゃあお前が先に食え。ほら、口開けろよ」ケンジはケネスに掴みかかった
ケネスは笑いながら抵抗した。「そうやってわいを眠らせて、どないする気ぃや? ケン兄のエッチ」
「あほっ! いいかげんにせえ!」
「ケン兄も大阪弁になってきてるよ」マユミがおかしそうに言った。
「ツッコミ、なかなかええタイミングやで、ケンジ」
「もういいよ。で、店はいつオープンなんだ? ケニー」
「四月に入ったらすぐや。三丁目のど真ん中やで」
「へえ! じゃあここから近いな」
「そやな。オープンの日、遊びに来たって。待っとるさかい」
「行く行く!」マユミが叫んだ。「楽しみだね、ケン兄」
「そうだな」
マユミがデキャンタからコーヒーをケネスのカップにつぎ足した。「おおきに」ケネスはそのカップを手にとって言った。「しかし、アヤカが泣き出して、ケンジがヤツの肩に手置いた時には、やばっ! て思ったで」
「どうして?」ケンジがチョコを口に運びながら聞いた。
「そのままキスでもすんのか、思たやんか」
「しなかったんだ」マユミが言った。
「しないよ」
「しなかったんやな、これが。ほんま、ケンジは紳士やと思うたわ。さすがやな」
「同情が人のためになったためしがあるか? 俺のためにもならないしな」
「そらそうやわな。へたするとアヤカの病気が再燃するかも知れへんからな」
「でもさ、」マユミだった。「ケン兄のついた苦し紛れの作り話が、結果的にアヤカを改心させたわけでしょ? それってすごくない?」
「そうなんや。しかしまたとんでもない作り話を考えついたもんや、て思わへん? わいとマーユが深い仲で、愛し合っているところを、見てしまってーの、その光景が頭から離れなくてーの、強烈に記憶に残ってーの。何やの、それ」ケネスはあきれ顔で言った。
「半分事実だろ」
「どこが事実やねん」
「俺とマユの夢の中でお前マユとエッチしたじゃないか」
「そのケニーは無理矢理やったんやろ?」
「でも、あの光景が頭から離れないのは事実だぜ」
「早よ忘れてーな」ケネスは頭を掻いた。
「そうそう、」ケンジがマユミに身体を向けた。「メールの着信履歴、消去しといて正解だった」
「え? 何かあったの?」
「今日の最後のミーティングの時にさ、拓志と康男のやつが、俺のケータイこっそり覗いてやがったんだ」
「なんであの二人がおまえのケータイ盗み見すんねん」
「俺の付き合ってる彼女が誰なのか知りたがってたらしくて」
「間一髪やったな」
ケンジはケネスを横目で見た。「ただ、おまえからの空メールを不審がってたけどな」
「空メール」マユミが訊いた。
「うん。アヤカと話してる時にさ、ケニーがタイミング良く送ってくれたんだ。それでうまく話の流れを作れた」
「何で不審がっとったんやろな」
コーヒーを飲み干して、トレイにカップを戻しながらケンジは言った。「『ケンジの恋人ってのはもしかしてケニーなのか?』って疑ってたよ」
「『そうだ』とか何とか言うとったら良かったのに」ケネスが口角を上げた。
ケンジは慌てて言った。「バカ言うな。そっちの方が大ニュースに発展しちまうだろ!」
「じゃあ、まだとりあえずばれてないんだね」マユミがにこにこしながら言った。
「ケンジ、実はばらしたいんとちゃうか? みんなに」
「何言ってる! そんなことして、もし俺たちの親の耳に入ったりしたらどうするんだ」
ケネスは後ろに手を突いて天井を見上げた。「両親にはもうばれてるんとちゃうかなあ……」
「な、何を根拠に」ケンジはうろたえた。
「ケンジすぐ顔や態度に出るやんか。家の中でもいちゃついとるんやろ? 食事の時とか」
「もうどきどきなんだよ」マユミが言った。「ご飯食べてる時に、ケン兄ったら椅子を近づけてきて、こっそりあたしの背中を撫でたりするんだよ」
「時間の問題やな」ケネスは笑った。
「さて、そろそろ寝るとするかな」ケンジは立ち上がった。
「そうやな。ほたらわいはここで一人で寝るよってに、ケンジとマーユは出てって」
「またそんな……」ケンジが呆れて言った。
「そのつもりやったんやろ?」
「ま、まあな」
ケンジとケネスは笑った。
マユミは恥じらったようにケンジの左腕に寄り添った。そして二人は立ち上がり、肩を寄せ合ってドアを出て行った。

ケネスは一人、ケンジの部屋に残った。彼は腰を伸ばして一度伸びをすると、部屋の灯りを消し、ケンジのベッドに横になった。
「(ああ、ケン兄、ケン兄……)」
「(マユ、マユっ!)」
すぐに二人の声とベッドの軋む音が隣から壁越しにかすかに漏れてきた。それを聴きながら、ケネスは大きなため息をついてぽつりと呟いた。「ああは言ったもんの、これではしばらく眠られへんな……」




































