Twin's Story 3 "Mint Chocolate Time"
《6 民宿》
その夜、三人は民宿の部屋で缶コーヒーを手にポテトチップスをつまんでいた。
「格安民宿とは言え、あの夕食、しょぼ過ぎやな」
「確かに。サラダのマカロニは半分干からびてたし、小魚の佃煮は歯が折れそうだったし」
「そんなもんだよ。あたしたち高校生の身分で贅沢言えないよ」マユミが笑って言った。
「そや、マーユ、チョコレート食べるか?」ケネスが言った。
きらん! マユミの目が輝いた。
「こいつがチョコレートがそこにあるって知ってて、食べないなんて言うわけないだろ」ケンジが笑った。
「持ってきてるの? ケニー」
「新発売、ミントチョコレートや」そう言いながらケネスはマユミに、青く爽やかなデザインのパッケージの箱を手渡した。
「開けていい?」
「どーぞ。ご遠慮なく」ケネスは笑った。
マユミはその箱を開けて、薄い円盤状のチョコレートをつまみ上げた。「かわいいね。試供品とちょっと違うみたい」
「おお、そやったな。二人には試供品食べさしたんやったな。でもな、あれからけっこう手え加えてな、味も香りもアップしてんねんで」
「そうなんだー」マユミはそのチョコレートをつまみ、目の前に持ってきてじっと観察した。「でも、なんで溶けてないの? 昼間とっても暑かったのに」
「見損なってもろては困ります、マユミはん。わいを誰やと思てるねん。名店『Simpson's Chocolate House』の店主の倅、ケネス・シンプソン坊ちゃんやで?」
「だから何なんだよ」
「クーラーバッグ持参やないか」ケネスはバッグから小ぶりの携帯用クーラーバッグを取り出して二人に見せびらかした。
「おお、さすがだな」
「準備万端だね、ケニー」
「デリケートな品質を守るためなら、手段を選ばん。それがチョコレート専門店のプライドっちゅうもんや」
「なるほど、恐れ入りました」ケンジは畳に手を突いてケネスに向かって土下座した。

「口に入れてみ、マーユ」
「うん」
ケネスに促されて、その艶やかなチョコレートを舌に乗せたマユミは、うっとりしたように言った。「ほんとだ、試供品とだいぶ違うね。これ、何だか海の風の香りがする。ケン兄も食べてみて」マユミはケンジに、チョコレートをつまんで渡した。
ケンジもマユミから受け取ったそのチョコレートを口に入れた。「そう言われれば……。ミントがよく効いてほんとに爽やかだな……ちょっと塩味もするような……」
「ピンポーン!」ケネスは人差し指を立てた。「正解や。カナダの岩塩使てるんやで。ますます海のイメージがするやろ?」
三人はしばらくその海の風を思わせる風味のチョコレートを味わった。
「素敵な一日だったね」
「そうだな」
マユミはおもむろに、着ていたTシャツを脱ぎ始めた。「何だか、身体が火照ってる」
「ちょ、ちょっと、マーユ、い、いきなり脱がんといて。わいもここにいること、忘れてへんか?」ケネスが赤くなって言った。
「言っただろ、ケニー。マユの大胆さには、俺も未だについていけないよ」ケンジが言った。
「じゃーん」Tシャツを脱ぎ去ったマユミが言った。「実は水着でーす」
「へ? 水着?」
「そ。三着持ってきてるんだ。昼間着られなかったから、今着てるの」
不自然に顔を赤くしながらケンジが言った。「さ、三着も買ったのか? マユ」
「うん。一つに絞れなくて……」
それは真っ白なビキニだった。彼女が昼間身に着けていたものより布の面積は小さく、生地も薄い感じだった。
「お陰で今月と来月のお小遣いがパー」マユミは困ったように笑って立ち上がり、二人のオトコの前でセクシーポーズをとってみせた。
「それで海に入ったら透けてしまいそうだな」ケンジが顔を真っ赤にしたままマユミの身体をじろじろ見ながら言った。
「だって、ケン兄のリクエストでしょ? 白い水着」
そう言いながらマユミは畳に座り直した。
「ほお、ケンジは清純派イメージの女のコに欲情すんねんな。明日、それ着て泳ぐんか? マーユ」
「だめだ!」すかさずケンジが叫んで、マユミの肩を抱いた。
「何や、ケンジ、そない強力に否定せんでも……」
「マユのカラダを他人に見せられるか」
ケネスは呆れた。「ほんま独占欲の強い兄貴やな、マーユ」
「そうなんだよー」マユミはケンジの顔をちらちら見ながら困った顔で笑った。
ケネスもケンジの顔を見た。「ケンジ、息、めっちゃ荒くなってるで……」
二階のその部屋には三つの布団が並べて敷かれていた。窓際にマユミ、その隣にケンジ。畳二枚分のスペースを空けて入り口の襖にへばりつくようにケネス用の布団が伸べられていた。
ケンジが自分の布団の上にあぐらをかき、手をメガホンにしてケネスに向かって大声を出した。「そんなに遠くに離れなくてもいいじゃないか、ケニー。電話で話さなきゃいけないぐらい遠いぞー」
「なに言うてんねん。おまえら今夜もいちゃつくにきまっとるやんか。わい、いたたまれなくなるのは火を見るより明らかや。ほんまやったら別の部屋に寝るべきところや」
「心配するな。おまえには迷惑かけないから」
「微妙な言い回しやな」
マユミは自分の布団の上で腹ばいになり、両手で顎を支えてにこにこ笑っていた。
夜も更けて、三人とも眠ったふりをしていた。特にケネスは、息を殺したまま、いつケンジとマユミの行為が始まるのかと、期待で胸をふくらませていた。
ごそごそとケンジが動き出す音がした。
ケンジはマユミの方に寝返りをうって、彼女の布団の上に覆い被さった。
「もう、ケン兄ったら」マユミは目を開けて小声でそう言った後、恥じらったように微笑んだ。「ケニーを起こしちゃうよ」
「大丈夫。大声を出さなければ平気だよ」

窓から射す月の光が、マユミの布団のところだけをスポットライトのように白く照らし出している。床に入ったときから黒い下着一枚だったケンジは、マユミの布団をはぎ取り、身体を重ねた。そしてそっとマユミにキスをした。
マユミはさっきの白いビキニの水着姿のままだった。
やがて二人とも月明かりの中で目が慣れてきた。二人はひそひそ声で話し続けた。
「マユ、きれいだ、いつ見ても、おまえの身体……」
ケンジは、例のグラビアモデルの写真を思い出していた。
「どうしたの? 顔が赤いよ。日焼け?」
「あ、あのさ、マユ、」
「なあに?」
「そのビキニ、少しだけ下げてみてくれないか?」
「え? どういうこと?」
「ま、まだ全部脱がなくてもいいからさ、ちょっとだけ」
「いいけど……。いっそ全部脱ごうか?」
「え? そ、それは……」ケンジはますます顔を赤くして言葉を濁した。
「変なケン兄……」そう言いながらマユミはブラを外し、ビキニもあっさりと脱ぎ去って全裸になった。
ぶっ! 上になったケンジが突然自分の鼻を押さえた。指の隙間から血が垂れ始め、仰向けになったマユミの腹にぼたぼたと落ちた。
「な、何っ? どうしたの? ケン兄!」マユミは驚いて頭をもたげた。
「は、鼻血が……」
「えー? 鼻血? なんで?」
「お、おまえの水着の日焼け跡が、あまりにも刺激的で……」枕元に置かれたティッシュを手にとって、ケンジはそれを丸めて鼻に詰めた後、マユミの身体に落ちた血を拭き取った。

マユミの肌は、水着のブラとビキニの所だけ、透き通るように白く残り、他の場所は褐色に色づいていた。
「セクシーすぎるっ!」ケンジは鼻にティッシュを詰めたままマユミの身体をぎゅっと抱きしめた。「水着の日焼け跡はオトコのロマンっ!」
「うふふ、ケン兄、嬉しい」マユミは続けた。「じゃあさ、今夜はあたしが上になるね、この日焼け跡がよく見えるように」
「え? い、いや、いいよ。おまえ仰向けになれよ」
「なんで?」
「背中が、痛くて……」
「背中が? ちょっと後ろ向いてみてよ」マユミが促した。
ケンジはマユミに背中を向けた。
「ほんとだー、赤くなってる」
「なんだかんだで背中だけいっぱい日焼けしたみたいだ」
マユミは再び布団に仰向けになった。マユミの裸体が月の光に包まれた。ケンジはそのマユミの肌が、さっき口の中で甘くとろけた、つややかなチョコレートの色と同じだと思った。そして水着の跡だけ、白く浮き上がって見えた。
「や、やばい、俺、こういうマユの身体、抱くのが夢だった……」
「早く来て」マユミが手を伸ばした。ケンジはゆっくりとマユミの身体に自分の身体を重ね合わせた。マユミはケンジの首に手を回した。「ケン兄……」
「マユ……」
ケンジの口がマユミの唇を覆った。「んっ……」そしてケンジの舌がその唇を割って中に入ってくると、マユミは思わずケンジの背中をぎゅっと抱きしめた。
「う、うぎゃっ!」ケンジが口を離して悲鳴を上げた。「い、い、痛い痛い痛いっ!」
「しーっ! 大声出すなって言ったの、ケン兄でしょ? ケニーに気づかれちゃうよ」
ケンジはとっさに自分の口を押さえた。そしてすぐにマユミに抗議した。「おまえ、今、わざとやっただろ?」
「誤解だよ。感じれば抱きしめたくなるの、当然じゃん」
「困ったなー」
「わかった。じゃああたし、何もしない。ただ寝てるだけ。それでいい?」
「いわゆるマグロってやつだな」
「何それ?」

「いいよ、知らなくても。あんまり品がいいとは言えない言葉だ」ケンジは笑った。「じゃあ、マユ、今夜は俺が一方的に奉仕するから、おまえ何もするなよ」
「わかった」
「ただ、感じるだけ」
「うん……」
ケンジはマユミの白い乳房にむしゃぶりつき、舌で乳首を転がし始めた。
うっすらと目を開けて、二人の様子を見ていたケネスは、すでにかなりの興奮状態だった。「(まったく、人の気もしらんと、あの二人……。)」
「ねえねえケン兄、」
「何だ?」
「またケン兄の、咥えたい」
「えー……」
「ねえ、お願い」
ケンジは躊躇いながら下着を脱ぎ去り全裸になった。
「あたし、こうしてるから、ケン兄のをあたしの口に入れてよ」
「え? う、上からか?」
「うん。だってケン兄、仰向けになれないんでしょ? 背中が痛くて」
「そ、そりゃそうだけど……」
「昼間みたいに、反対向きでお互いに口で……」
「わ、わかった」ケンジは身体を起こした。「で、でもっ! 俺、もうおまえの口には出さないからな」
「ふふ、ケン兄、そんなに抵抗があるの?」
「ある。って何度言ったらわかるんだよ」
「わかった。じゃあ直前でやめさせて」
ケンジは身体を反転させてマユミの秘部に舌を這わせ始めた。「あ、ああん……」マユミが喘ぎだした。ケンジの舌がマユミのクリトリスを捉えると、マユミは目の前のケンジのペニスを手で掴んで、自分の口に咥え込んだ。
「ううっ!」ケンジも呻いた。
しんとした部屋の中にぴちゃぴちゃという音が響く。ケネスは思わず下着越しに自分の股間に手を当てた。
しばらくその行為を続けていたケンジは、興奮の高まりに危機感を覚えて、マユミの口からペニスを引き抜いた。そしてマユミと同じ方向に身体を向け直すと、マユミの口の周りを丁寧に舐めた。
「マユ、ありがとう。気持ちよかった」
「あたしも、ケン兄」
息を大きく弾ませながらケンジが言った。「俺、入れたい、マユに。入れていい?」
「いいよ。来て、ケン兄」
ケンジはマユミの脚を抱え上げて大きく開かせた。そしてそっとペニスを彼女の谷間にあてがった。「いくよ、マユ」
「うん。来て」
ケンジはゆっくりとマユミに挿入させ始めた。「あ、あああ、ケン兄……」
「マ、マユ、大声出すなよ」
「うん、わかってる。ケン兄もね」
「(全部聞こえとるがなー。)」ケネスは辛そうに独り言を言った。そして布団の中で下着を下ろし、ペニスを掴んでさすり始めた。「(ん、んんっ……。)」
ケンジは腰を前後に動かし始めた。
安普請な民宿で、温度調節の利かない空調のせいで寒いぐらいに冷えた部屋の中で、ケンジとマユミは全身に汗を滲ませながら同じように揺れ動いていた。
ケネスはその月明かりに浮かび上がった二人の躍動する様子を、もうしっかりとまぶたを開き、その蒼い目でつぶさに見ながら高まる興奮に身を預け始めていた。
マユミが思わず腕を伸ばし、ケンジの背中を抱こうとした。ケンジはとっさに彼女のその腕をとり、布団に押さえつけた。そしてさらに激しく腰を動かした。
「あ、ああ、ケン兄、ケン兄、あたし、あたしっ!」
マユミの声が大きくなってきた。ケンジはマユミの腕を押しつけたまま、身体を倒して彼女の口を自分の口で塞いだ。
「んん、んんんっ!」
マユミは声を出すことができず、苦しそうに大きく呻いた。
「んん、んんっ!」ケンジもそのまま呻き始めた。そして腰の動きが最高潮になった次の瞬間、びくっ、びくっ! 重なった二人の身体が同時に数回跳ね上がった。
「んんーっ!」マユミもケンジもお互いの口を吸い合ったまま大きく呻いた。
「うう、くっ!」ケネスは布団の中で、ペニスを包み込んだティッシュの中に、激しく身体の中で熱く煮え立っていたマグマを何度も放出させた。「ぐっ、んっ、んんっ!」
ケンジの体内に溜まっていた熱いエキスも、何度もマユミの中に迸った。

いつしか汗だくになっていた二人の身体は、長い間びくびくと痙攣していた。やがてケンジがマユミから口を離すと、はあっ、と大きく二人とも息を吐き出した。そしてそのままはあはあと荒い呼吸を繰り返した。
「マ、マユ……」
「ケ、ケン兄……、とっても気持ちよかった……」
「俺もだ、マユ」
ケンジとマユミは繋がったままお互いの顔を見つめ合った。

「ケン兄のキス、ミントの香りがしたよ」
「俺も感じた。マユの息は夏の風と同じ香りがしたよ」
「ケニー、起こさなかったかな……」
ちらりとケネスの布団を見やったケンジは言った。「大丈夫みたいだ。気づいてなさそうだ」
「(いや、気づかんわけ、あれへんて。あないに激しく求め合っといて、何言うてんねんな。)」
「ケン兄、まだ背中、痛い?」
「え? 何でだ?」
「あたし、ケン兄を抱きしめたい。もう、欲求不満になりそうだよ」
ケンジは押さえつけていたマユミの腕を解放した。
「ねえ、抱きしめさせてよ、お願い」
「そっとな、そっとだぞ」ケンジはこわごわ言った。
「うん」マユミはそう言って上に重なったケンジの背中に腕を回した。そして最初は柔らかく彼の胴体に腕を巻き付け、少しずつ力を込めて愛しい兄の身体を抱いた。
「う……」
「痛い? ケン兄」
「だ、大丈夫。我慢できるよ」ケンジはそう言ってまたマユミにキスをした。
口を離したケンジの目を見つめて、マユミは言った。「ねえねえ、次はケン兄を抱きしめてイきたい、あたし」
「そうか? 続けてイける? マユ」
「うん。まだ身体が熱い。それにケン兄、また大きくなってきてるよ、あたしの中で」
「よし、じゃあいくよ、マユ」
「うん」
ケンジは再び腰を激しく動かし始めた。
「(勘弁してえな……)」ケネスは布団を頭からかぶったまま大きなため息をついた。
◆
明くる日もよく晴れていた。
「二人とも寝不足なんやろ?」貧相な卵焼きを口に運びながら、ケネスがおかしそうに訊いた。
「え?」マユミが恥ずかしげにケネスに顔を向けた。
「そういうおまえも目が赤いのはなんでだ?」ケンジがケネスを睨みつけて言った。
「え? おかしーな。昨夜は疲れて早うにぐっすり眠ったはずなんやけど……」
「嘘つけ」
「な、なんやねん」
「おまえの布団の下に丸められたティッシュが山ほど隠してあったのを俺は知っている」
「えー、ケニー、夜中に一人エッチしてたのー?」マユミが口を押さえて言った。
みそ汁の椀を心静かにちゃぶ台に置いて、正座をして居住まいを正したケネスは二人を交互に見ながらゆっくりと言った。「あのな、マーユ、同じ部屋で、恋人同士が、夜通し愛し合ってる状況で、心安らかに眠れると思うか?」
「えー、知ってたの?」
「ケンジ、おまえら、わいの知ってるだけで四回も繋がったやろ」
「え? 五回じゃなかったっけ?」マユミが言った。
「五回もイったんかいな! マーユ!」
「だって、ケン兄がやめてくれないんだもん……」
「俺のせいかよ!」ケンジが口からご飯つぶを飛ばしながら言った。
「まったく、人の気も知らんと……」ケネスは再びみそ汁の椀を手にとって、わかめくずと小さな麩の入ったみそ汁をすすった。
「ごめんね、ケニー。あなたを眠らせないつもりじゃなかったんだよ」
ケネスは一転爽やかな表情で言った。「ええねん。わいな、ケンジとマーユがああやって熱々の関係である証拠、見せられると、めっちゃ嬉しくなんねん。わいこそ、こそこそ二人のことのぞき見したりしてすんまへんでした」
「俺も悪かった。もっと気を遣うべきだった。すまん、ケニー」
「かめへんて。それにな、何もなしに一人エッチやるのに比べると、もうその興奮の度合いが全然違うねん。何しろ目の前で、惚れ惚れするぐらい美しい男女がセックスし合うんやから。AVやエッチ本なんかとは比べもんになれへん。最高のオカズやねんで」
「役に立てて嬉しい」マユミが言った。
「ううむ……これを役に立つというのかどうか……」ケンジは頭を抱えた。
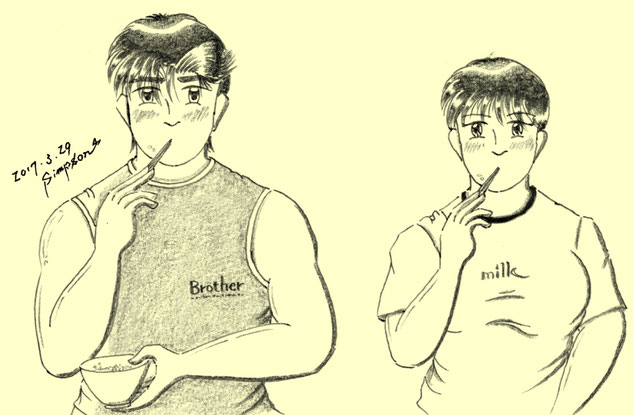
「そやけどケンジ、おまえら自分ちでもあんな風に激しく求め合うとるんやろ?」
「は、激しくってほどじゃ……」
「まあ、確かに愛し合っとる最中、本人たちにはわからんやろな。いや、十分激しかったで、昨夜も」
ケネスはにやりと笑った。マユミもケンジも同じように箸を咥えたまま動きを止めて顔を赤らめていた。
「そんな物音に両親は気づかへんのんか?」
「そう言えば、ママが言ってた」マユミが小さな声で言った。
ケンジは思わずマユミの顔を見た。「えっ? な、なんて」
「夜中に上からぎしぎし音がする、毎日のように、って」
ケネスが呆れたように言った。「マーユ、毎晩あないに激しく愛し合うとるんか? ケンジと」
「き、気づかれてるのかな」ケンジがおろおろしながら言った。
「ママはケン兄が一人エッチしてると思ってるみたい」
「そ、そうか……」
「いやいや、一人エッチにしては激し過ぎちゃうか……ベッドのぎしぎし度合い」
「と、とりあえず気づかれてはいないみたいだな……」
「ま、そない思うてもろとった方が幸せやな。二人にとって」
「良かった……」ケンジはほっとため息をついて、味噌汁を飲み干した。
「そやけど、なり振り構わん激しいエッチもほどほどにしとかんと、いつか部屋に踏み込まれて、ばれてまうで、おまえらの禁断の関係」ケネスは悪戯っぽく笑った。
「わ、わかってるよ」ケンジはうつむき気味で言った。
◆
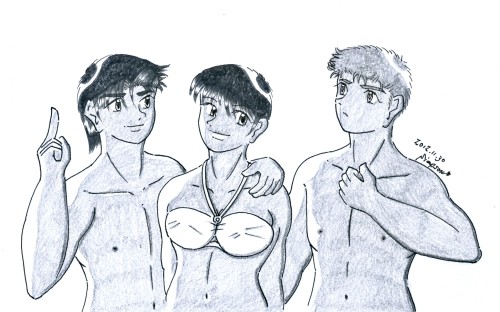
三人は砂浜に腰を下ろして、清々しい朝の海を眺めていた。
「気持ちいいねー」マユミが大きく伸びをした。
「そうだな、まだ朝のうちは人も少なくて、気分いいな」
「ケンジ、もう高校総体も終わって一息っちゅうとこやけど、卒業したらどないするつもりなんや?」
「俺か? 俺、水泳ばっかやってきたから、大学でも続けられればなって思ってる。インストラクターとか、指導者としての技術を身につけたい。ケニーは?」
「わいはショコラティエになることが運命づけられとる」
「店を継ぐんだー。偉いね、ケニー」マユミが言った。
「でも、それって、おまえ納得してるのか? 違う仕事に就きたいとか、思わないのか?」
「幸か不幸か、わいはずっと前からこの目標は変われへん。別に親父やおかんに気い遣っとるつもりはないねん。わいも純粋にチョコレート職人になりたい思とるから、その道を選ぶだけや」
「そうか……」
「マーユは?」
「あたしはね、経済とか流通とか経理とかの勉強がしたい。だから進学する。もう高校で簿記検定とか情報処理検定にも合格したんだ」
「二人ともちゃんと先のこと考えとるんやな」ケネスは空を仰いだ。
「さて、」ケンジが立ち上がった。「一泳ぎしたら、荷物まとめるか」
「そやな。昼前の電車に間に合うようにな」
「マユ、おいで」ケンジはマユミの手をとった。マユミも立ち上がった。
「ケン兄、もう背中痛くない?」
「うん。昨日よりずいぶん痛くなくなった」
「良かった」
「もう、ボート使わへんのか?」ケネスが悪戯っぽく笑って言った。
「気を遣わないでくれ、ケニー」
「確かに今からくたくたのへろへろになったら、帰るのん、大変やからな」
「そうだよ、またあんな思いをしてボート膨らませなきゃって思うと、気が遠くなる」
「いや、そういうことやのうて、おまえ、ボート膨らました後が大変やんか」
「なんで後が大変なんだよ」
「大変やんか。ボートに乗ったら、またおまえらあんなことやこんなことして激しく愛し合うに決まっとるやん。昨日も昨夜もそやったけど」
「大きなお世話だ」
「さすがにこれ以上愛し合ったらくたくたのへろへろやろ?」
「それについちゃ心配いらないよ」
ケンジはマユミの手をとって海に向かって走り出した。
「ほんま。タフっちゅうか、元気っちゅうか、絶倫っちゅうか……」ケネスは腰に手を当てて一つため息をついた。「わいも負けてられへんな。って、独り身でどないせえっちゅうねん」
ケネスは一人突っ込みをかまして、二人の後を追った。「待ってえな! わいもまぜたって!」
マユミが波打ち際で振り向き、飛び跳ねながらケネスに大きく手を振った。「早くー、ケニー」
2013,7,29初稿脱稿(2014,4,25改訂)
※本作品の著作権はS.Simpsonにあります。無断での転載、転用、複製を固く禁止します。
※Copyright © Secret Simpson 2012-2014 all rights reserved
《Mint Chocolate Time あとがき》
最後までお読みいただき感謝します。
アダルト小説で、甘い恋人同士のあんなことやこんなことを描くのに、水着姿になる夏という季節は、作者にとって絶対にはずせない時季です。ある意味、ケンジとマユミのアツアツぶりを存分に描きたくて、この話を書いた、と言っても過言ではありません。
男にとって、女の子の肌を目にするということは、相当な興奮を覚えるものですが、全裸より何かで隠されていた方が萌える、なんてことがあるのです。想像力というか、妄想力というか……。それに、深い関係の相手であれば、それを脱がせるという行為に興奮を覚えることも、もちろんありますよね。そうやって現れた素肌に、水着の跡がついていたりしたら、もう僕なんか一気にオオカミ化してしまいそうです。
それにしても、二人の親友ケネスにとっては、なかなかつらいバカンスになりました。眼前で繰り広げられる濃厚なラブシーン。もう生殺し状態ですね。そしてケネスは、一人でそれをおかずにしながら処理するわけで、不憫というか……。
彼のその悶々とした想いが報われる時が、先々きっとやって来ます。
Simpson





































