Twin's Story 6 "Macadamia Nuts Chocolate Time"
1.旅行前夜|2.出発|3.ハワイ|4.ワイキキビーチ|5.ミカの計画|6.競泳大会|7.二十年来|8.ミカの暴走|9.熱い夜|10.真実|11.新たな一日|12.四人の夜|13.旅行土産|14.バリアフリー|登場人物紹介

《2 出発》
あくる8月3日。
「20th. Anniversary! Great Summer Vacation for Mayumi & Kenji in HAWAII~! イエ~イ!!!」ケネスが叫んだ。
「ケニー、大声出すなっ! 他のお客さんに迷惑だろ? しかも滅多に使わない英語なんかで叫びやがって」
「ええやんか。めでたい日やねんから」
「なんでめでたいんだよ」
「今日はケンジとマーユの初体験記念日。しかも20周年っ!」
「こ、こらっ! ケニー、声が大きい。子供に聞かれたらどうするんだよ」
空港に向かう電車の中で大人4人と子供3人に分かれてボックス席に座っていた。子どもたち3人はトランプで盛り上がっていて、そんなケンジの心配は杞憂以外の何物でもなかった。
「ごめんなさいね、ミカ姉さん」マユミが言った。「切符の手配からホテルの予約まで何もかも任せちゃって……」
「いいんだよ。そもそもこの計画、あなたたちには秘密であたしとケネスで進めてきたんだから。旅費さえ割り勘なら何の問題もないよ」
「も、もちろんよ」
「でもさ、よくこんな高級ホテルの予約が取れたな、ケニー」ケンジがホテルのパンフレットを広げながら言った。
「コネや、コネ」
「コネ?」
「わいの親父がカナダで店やってた頃からのつき合いなんや、このホテル」
「へえ」
「カナダ人、けっこうハワイに行ってるんやで。わいもこのホテルには何回か泊まったこと、あんねで」
「そうだったの」マユミが言った。
◆
空港で昼食を済ませ、早めに出国審査を終わらせた7人は搭乗口前ロビーで語らっていた。子どもたち3人はウノで盛り上がっている。
「まだフライトには時間があるわね」ミカが言った。「ケネス、付き合って。これからの計画を話し合うよ」
「了解。ミカ姉」ケネスは敬礼をしてミカと一緒に席を立った。振り返りざまにミカが言った。「あなたたちもぶらついてきたら?」
「そうするよ。ちょっと歩こうか、マユ」
「うん」
健太郎が顔を上げてショッピングエリアに向かうケンジとマユミを見た。
「おい、マユ、」健太郎が肘で真雪を小突いた。
「何? ケン兄」真雪も顔を上げた。
「双子の兄妹ってさ、あんなにいつまでも仲がいいものなのかね?」
「いがみ合うよりいいんじゃない?」
「そうだけどさ、なんかケンジおじと母さんって、それ以上って感じ、しないか? 手までつないでるし……」
「双子だしね。そんなものなんじゃない?」
「俺たちあそこまでしないだろ?」
ケンジは不意に足を止めた。
「どうしたの? ケン兄」
「水着……」
「あ……」マユミも立ち止まった。
それは高三の夏、いっしょに出かけた海でマユミが着ていたビキニの水着によく似たものだった。
「このマネキン、お前に似てる」
「えー、やだー」
「あの水着、どうした?」
「まだとってあるよ。真雪にどう? って聞いたら、恥ずかしいからいやだ、って言われた」
「ふうん。やっぱりあの頃のお前って、意外に大胆だったのかな」
「自分じゃそんなこと思ってなかったけどね」
ケンジの脳裏にあの時のマユミの日焼け跡の白い肌と、その柔らかで熱い感触が甦り始めた。
「マユ……」ケンジはマユミの肩を抱き、頬に軽くキスをした。
「ケン兄……、人がいるよ」マユミが囁いた。
ケンジは無言でマユミの手を引いてそこを離れた。
◆
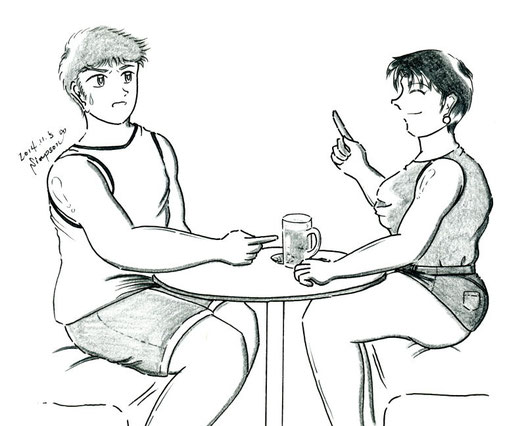
ミカとケネスはテーブルを挟んで向かい合っていた。ミカの前には生ビールのジョッキが置いてある。
「ミカ姉、今から7時間も飛行機に乗らなあかんねんで? その目の前のものは一体なんやねんな」
「あんたも飲む? ケネス」
「いや、遠慮しとくわ」
ミカはさっと手を上げて、遠くにいた店員に声を張り上げた。「生、もう一杯持って来て」
「ちょ、ちょっとミカ姉!」
すぐに同じ物が運ばれて来た。ミカは自分のジョッキを持ち上げた。「乾杯!」
ケネスもあわてて目の前に置かれたジョッキを持った。「か、乾杯」
「って、何に乾杯なんや?」
「我々の新たなシーンの始まりよ」
「新たなシーン?」
「そう」
「何やの、それ」
「あたし、向こうでやってみたいことがあるんだよね。記念に」ミカはケネスに身を乗り出した。
「記念にやってみたいこと?」ケネスはジョッキを口に運んだ。
「そう。夫婦交換」
ぶ~っ! ケネスはビールを噴き出した。そして慌てて口の周りとテーブルをおしぼりで拭き始めた。「な、なんやて?!」
「っつってもさ、もともとケンジとマユミは今日愛し合うわけだし、残ったあたしたちもせっかくだから愛し合ってみたらどうかと」
「ミっ、ミっ、ミカ姉、本気でそないなこと考えてんのんか?」
「うん。本気。声が大きいよ、ケネス」

ケネスは真っ赤になって言った。「そ、そんな相談するためにわいをここに連れ込んだんかいな」
「そうよ。で、どうなの?」
「わ、わ、わいは、その、ミカ姉が、そっ、そっ、その気なら、あの、あのあのあの……」
「それにさ、あたしとあんたが一度そういう関係になっとけば、ケンジたちもこれから気兼ねなく、あたしたちに気遣いなくいつでも会える、ってことでしょ? 一石二鳥じゃん。誰も傷つかないし、みんなで幸せになれる。どう?」
「ど、どう、って振られてもやな……」ケネスはもじもじして言葉を濁した。
「それに、もし、あたしとあんたのカラダの相性が良ければ、その後も時々ヤってもいいじゃない」
「あ、相性……、と、時々ヤっても……あ、あの、ミ、ミカ姉……」ケネスは口をぱくぱくしながらうろたえた。
ミカはテーブルをばん! と叩いて立ち上がった。「はっきりしないオトコねっ! あたしを抱きたいの? 抱きたくないのっ?!」
その声に遠くのテーブルにいたカップルと、水を運んでいた若い女性の店員が振り向いた。
「しーっ! ミ、ミカ姉、声が大きい、声がっ!」
◆
ケンジがマユミを連れてやって来たのは空港ターミナルの一画にあるリフレッシュ・ルームだった。
「『リフレッシュ・ルーム』?」
「マユ、お、俺……」
「やだー、ケン兄のエッチ」
リフレッシュ・ルームの中には、シャワー付きの仮眠室があった。
「予約してたんだ」
「うん」
「用意周到」
シャワーを済ませ、ケンジはバスタオルを身体に巻いたまま仮眠室に入った。そこには二つのシングルベッドが並んでいた。彼はそれを合わせて一つにした。
マユミはケンジの隣にやはりバスタオルをまとって座った。
「子どもたちは大丈夫かな……」
「一応電話しとこう」ケンジはスマートフォンを取り出し、パネルに触れ、健太郎に電話をかけた。
「何? ケンジおじ」すぐに健太郎が反応した。
「おお、健太郎、今何してる?」
「え? べつにぼーっとしてる。ウノにも飽きたから」
「そうか。あと一時間半ぐらいでそこに戻るから」
「一時間半? ずいぶん長くない?」
「ちょっと手がかかることがあってな。心配するな、そのうちケニーたちも戻ってくるだろう」
「わかった。じゃ」
健太郎は電話を切った。
「一時間半……。マユ、お前どう思う?」健太郎は真雪に問いかけた。
「どう思うって?」
「二人で何してるんだろう……」
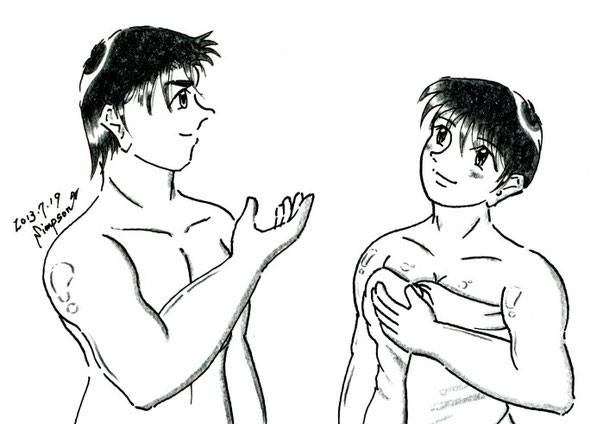
スマートフォンをバッグにしまったケンジは、マユミに向き直った。「例えば、」
「なに?」
「ケニーとミカがこの旅行中に一線を越えたとしたら、お前どうする?」
「え? そんなことあり得るかなー」
「俺、ちょっと望んでるんだ、そうなるの」
「……あたしも、ちょっとは……」
「ミカってさ、ああいう性格じゃん。もしケニーを誘惑するなら、きっといつもの軽いノリでいっちまいそうな気がするんだよな」
「ケン兄はいいの? ミカさんがそんな風に、」
「お前は? マユ。ケニーがミカと……」
「何だか都合のいい考え方かも知れないけど、そうなったらあたしたち、ちょっとほっとするよね」
「うん。ほっとする」
「問題は、その後、その関係を二人が引きずらないかってことだよね」
「いっそ、そのことを4人の公認事項にしてしまえばいいのかもしれないな」
「あたし、ケニーに言ってみる」
「え? 何て?」
「ミカ姉さんを抱きたくない? って」
「それは俺が言った方がよくないか?」
「えー、それって何だかフーゾクの客引きみたいだよ」
「ミカにも言ってみる」
「言ってみちゃう?」
「うん。でも俺の予想では、あいつすでにその気になっているような気がする」
「ほんとにー?」
「なんか、どきどきしてきたな」
「うん」
ケンジとマユミはお互いのバスタオルを取り去り、抱き合ってベッドに倒れ込んだ。
◆
「何? まだケンジたち戻ってけえへんの」
ケネスが免税店の中をのぞき込んでいる3人の子供たちに気付いて足を止めた。
「そうなんだよ。まったく、何やってんだか……」龍がため息をついた。
ミカがケネスの耳に口を寄せた。「ケネス、先超されてるぞ。こりゃあたしたちも機会を見つけて、」
「ミ、ミカ姉、酔った勢いでいらんこと子らの前で口走らんといてな」
「それにしてもすごいよね」真雪が言った。
「何が?」
「この店、世界中のいろんなものが置いてあるよ」
ジャカルタの木彫りの面、真っ赤なベネチアングラス、スコッチウィスキー、マダガスカルのラピスラズリのネックレス……。
「ロシアのマトリョーシカ人形まである」健太郎が言った。
「ほんとだ。わざわざロシアまで行かなくても、ここでアリバイが作れるな」ミカがその人形をのぞき込みながら言った。
「何のアリバイだよ」龍が母親のミカを見て言った。
「いろいろとな。必要になることもあるかもしれないよ。龍」
「意味わかんね」




































