Twin's Story 6 "Macadamia Nuts Chocolate Time"
1.旅行前夜|2.出発|3.ハワイ|4.ワイキキビーチ|5.ミカの計画|6.競泳大会|7.二十年来|8.ミカの暴走|9.熱い夜|10.真実|11.新たな一日|12.四人の夜|13.旅行土産|14.バリアフリー|登場人物紹介
《7 20年来》
小さな丸いテーブルを挟んでアヤカとケンジは向かい合った。
「思えば、あれからお前と一度も言葉を交わさなかったな」ケンジが少し申し訳なさそうに言った。
「無理もないわよ」アヤカが運ばれてきたアイスティにシロップを入れながら言った。
「別に避けてたわけじゃないんだけど、なんて言うか、こう話すきっかけがつかめなくてさ」
「あたしもあれきりマネージャーやめちゃったしね」
ケンジはコーヒーカップを手にした。

「今のだんなとはいつ知り合ったんだ?」
「彼は日系二世でね、私と同じ大学で当時一緒に学んでたんだよ」
「もともとサンフランシスコの人なのか?」
「そう。大学出て婚約して、店を持つことが決まってから結婚したんだ」
「そうか。よかったな。幸せそうだ」
「海棠君が言った言葉を私、まだ忘れてないよ」
「え?」ケンジはカップを口から離してアヤカを見た。
「『アヤカのことをわかってくれるヤツがきっと現れるよ。』って言ってくれたこと」
「もう、ずいぶん昔のことになってしまったな……」
「そうだね。今から20年も前……」アヤカは目を伏せた。
ケンジは小さなため息をついてコーヒーを口にした。
「でもね、」アヤカがいたずらっぽく微笑みながらケンジに身を乗り出した。「私のだんな、Mなんだよ」
「ええっ?!」ケンジはカップをテーブルに戻して、にわかに赤くなった。
「実は、縛られてされるの大好きなんだ」
「そ、そうなのか? っつうか、お前まだそんなことしてるのかよ」
「ケンジくんをあんな目に遭わせてから、私目覚めたかも」
「目覚めた、ってお前、あんなことしたの初めてだったのかよ」
「うん」アヤカはあっさりと言った。「ケンジくんが最初で最後の犠牲者」
「お、お前なあ!」
「本当に、あの時はごめんね。傷つけちゃって……」アヤカはしんみりとした口調で言った。
「あれから俺、黒いレザー張りのベンチ見ると、左腕が勝手に痛む。トラウマになってんだぞ!」
「えっ?! 本当に?」
「嘘だよ」
「驚かさないでよ。ああびっくりした」
「ごめん。ちょっとした仕返しだ」ケンジは笑ってコーヒーを一口飲んだ。
「良かった、あなたにまた会えて」
「俺もだ。いつかこうして笑って話せる日がくるのを、俺ずっと心の奥で待ってたような気がする」
「あたしも」飲み干したグラスをテーブルに戻してアヤカは言った。「これでずっと心の底に残っていたものが吸い出されてなくなった気がする」
やってきたショップのスタッフに代金をケンジが支払い、二人はテーブルを離れた。

「元気でな、アヤカ」ケンジがアヤカの左肩に手をそっと置いた。
「うん。あなたも、みんなと幸せに」アヤカの右手がケンジの左手を握った。
しばらく二人は見つめ合った。
「それじゃあ、飛行機の時間があるから」
「ああ」
ケンジはカフェの前に立ち、アヤカを見送った。サングラスをかけ直してアヤカはホテルの陰に消えた。
◆
「っちゅうわけでな、あんまりおもろい展開やなかってんで」
「そうなんだー」
ケネスがホテルの部屋に戻ってマユミたちにその時の様子を話して聞かせていた。
「マーユもミカ姉もその場にいたらそう思たと思うで」
ケネスはこっそりケンジとアヤカの様子を覗いていたのだった。
「昔、何かあったみたいね、二人の間に」ミカが言った。
「あったんやわ、これが。強烈な出来事が」ケネスは声を低くして言った。
「強烈な出来事?」
「そやねん。詳しくは『エピソード 2 Bitter Chocolate Time』読んでな」
ケネスがミカに当時のケンジとアヤカの間に起こった出来事を話し終わった時、ドアを開けてケンジが入ってきた。「ミカ、ビール買ってきたぞ」
「ありがと」ミカはケンジから缶ビールを受け取り、一本開けてケネスに、もう一つマユミに、自分の隣に座ったケンジにも渡して、手に残った缶のプルタブを起こした。
「何の話してるんだ?」ケンジが言った。
「さっきのアヤカさんとあなたの件」
「アヤカと?」
「聞いたよ、ケンジ」
「聞いたのか」
「確かに強烈な体験だったね」
「そりゃあもう! 俺の人生の中で一、二を争う強烈体験だった」
「あの時、ほんとにケン兄さ、」マユミが言った。「興奮したりしなかったの?」
「縛られてか?」
「うん」
「不思議としなかったんだよなー、これが」
「へえ」
「今、思い出すと、なかなか興奮するシチュエーションなんだけどな」ケンジが少し恥ずかしげに続けた。「あの時は、本当に気持ちが拒絶してた。でもさ、身体って刺激されると反応しちゃうじゃないか、オトコって」
「うんうん」ケネスが大きくうなづいた。
「だから余計にマユに対して申し訳なくて……」
「ケンジ、悔し泣きしてたんやで」
「大会の晩、ケン兄、痛む腕をかばいながらあたしを抱いてくれたよね。すっごく優しかった」
「だから、その時はもう痛くなかったってば」
「そんなに優しかったの?」ミカが訊いた。
「最初から最後まで。壊れ物を扱うようにあたしを抱いてくれたんだよ」
「へえ、今度あたしもそうやって抱いてくれる? ケンジ」
「お、俺はいつも優しいだろ」
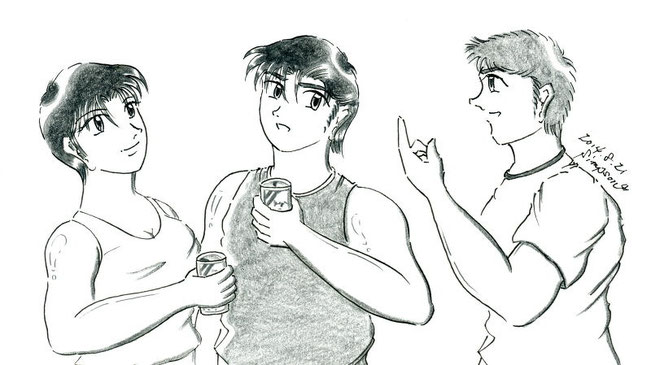
「そやけど、」ケネスが言った。「さっきケンジがアヤカの肩に手置いて、アヤカもケンジの手をとった時には、やばっ! て思ったで」
「どうして?」ケンジがビールの缶から口を放して聞いた。
「そのままキスでもすんのか、思たやんか」
「しなかったんだ」ミカが言った。
「しないよ」
「しなかったんやな、これが。ほんま、ケンジは紳士やと思うたわ。さすがやな」
その時、開けられたドアから、いきなり龍が飛び込んできた。健太郎と真雪も後ろからついて入ってきた。
「ノックぐらいしろ、ガキども」ミカが言った。
「ねえねえ、すごいよ、ほら、これ見てよ」
龍がケンジたちに数枚の写真を広げて見せた。それは、プールで泳いでいる6人の写真だった。プルの後水から頭を上げた瞬間の龍、すらりと前にまっすぐ腕を伸ばした真雪、飛び込む瞬間のケネス。
「ど、どうしたんだ、この写真」ミカがそれらを手にとって言った。
「僕たちの部屋に届けられたんだよ。これも一緒に」龍は封筒に入ったカードを出して見せた。短い英文が書かれていた。
「なになに……」ケネスがそれを見た。
「何だって? ケニー」
「嬉しいこっちゃな。ハワイであんな美しいスイマーの姿を見られてラッキーだった、てなことが書いてあるわ」
「中でもこの写真がすごいんだ」健太郎が最後の一枚を差し出した。それはケンジが大きくリカバリーしている正面からのアップ写真だった。
逞しくまるで鎧のような肩の三角筋、広げられたしなやかな腕、正面を見据えるゴーグル越しの眼、それは野性的でしかも均整のとれたケンジの身体の魅力だけでなく、内なる精神性をも見事に写し取った芸術的とも言える写真だった。
「ほー……」ミカがため息をついた。マユミも言葉を失ってその画を見つめた。
「ええ思い出ができたな、みんな」
「本当にな」ケンジが感慨深げに言った。
「他にもさ、お菓子やら手紙やら、花束やらがたっくさん届けられたんだよ。来てみてよ、部屋に」興奮したように龍が言った。





































