Chocolate Time 雨の物語集 ~雨に濡れる不器用な男たちのラブストーリー~
『ずぶ濡れのキス』 (1.音楽室での出来事|2.明かされる秘め事|3.目覚めの朝|4.ずぶ濡れのキス|5.門出)
《3.目覚めの朝》
明くる木曜日の朝。店の前の植え込みの雑草を抜いていたケネスは、どんよりと曇った空を見上げて呟いた。「降りそうやな……ん?」
ケネスは、通りの歩道を自転車を押しながらとぼとぼと歩く男子高校生に目をやった。
「将太!」ケネスはその少年に声を掛けた。将太は足を止め、ケネスの顔を見た。
「どないした、具合でも悪いんか? 学校の帰りの方向やないか」
「今日はサボり」
ケネスは将太に駆け寄り、その顔をじっと見つめた。将太の視線は定まらず、落ち着かないように揺れ動いた。
「寄っていけへんか? 将太」ケネスはにっこりと笑ってその男子高校生の手を取った。

「ごめん、ケニーおっちゃん」
「気にせんでもええ」ケネスは店内の喫茶スペースのテーブルに将太と向かい合って座った。
マユミが銀色のトレイに二つのカップを載せて運んできた。「はい。淹れたてでおいしいよ。飲んで、将ちゃん」
「すいません……」
将太はカップを手に取ったが、なかなかそれを口に運べないでいた。
「何や、話したいことがぎょうさんあるっちゅう顔してるで、将太」
「うん……」
将太の手はコーヒーのカップを持ち上げたまま止まっていた。
「飲むか、置くか、どっちかにしたらどやねん」ケネスは呆れたように言った。
将太はコーヒーを一口飲んだ後、カップをソーサーに戻した。
「俺、どうしたらいいか、わからなくなってきた」
「何をや?」
「何もかも」
ケネスもコーヒーを一口飲んだ。「もがいとる、っちゅうことやな」
しばらくの沈黙の後、将太は唇を噛みしめてケネスの顔を見た。「じいちゃんに……」
ケネスは黙って将太の目を見た。
「いや……」将太は再び目を伏せた。
「たった一人の孫やし、志賀のおやっさんにとってはおまえは宝モンや」
「じいちゃんは……全然悪くない」
「誰か悪いやつがおるんか? 恨んどるやつが」
「あの女っ!」将太はいきなり拳でテーブルを乱暴に叩いた。「俺を捨てた、あの女が全部悪いんだ!」
それは将太が高一の時、外に男を作って家を出て行った母親のことだった。
「それでも偉いやないか、将太。グレもせんと、ここまでようがんばって来たやないか」
「復讐してやった……」将太はケネスを上目遣いに睨み付けながら言った。
「復讐?」
「あの女に似てる担任を犯してやった」
「なんやと?」
将太は口元に怪しげな笑みを浮かべて言った。「毎週水曜日、俺と担任の鷲尾は音楽室でやってるんだぜ、おっちゃん」
「お、おまえ、学校でそないなこと……」
「あいつも拒まないし、結構楽しんでるみたいでさ」
「楽しんでる、って、ほんまか?」
「ああ。昨日もあいつ、びしょびしょに濡らしながら腰振ってヨがってた。好きモンなんだ。俺も遠慮なく腹の上に出してやったさ」
ケネスは眉を寄せて、そのいきなり饒舌になった将太を見た。
「その先生が、おまえを捨てた母親に似とるっちゅうんか?」
「そうさ。だから俺は復讐してんだ」
「毎週やっとるんか? その音楽室で」
「そ。進路相談っていうことになってる」
「やった後とか前とかに実際相談に乗ってくれるんか?」
「夏に初めて音楽室に連れ込まれた時は、真面目に相談してた。でも今はそんなこと全然なし。やったら終わり」
ケネスは、そうふてぶてしい態度で言い放つ将太の目の奥に、隠しきれていない不安の色を見過ごさなかった。
「将太、おまえ、本当に言いたいこと、別にあるやろ」
将太は一瞬肩をビクン、と震わせて突然黙り込んだ。
ケネスは静かに話し始めた。「おまえはほんまは優しい少年や。ちっこい頃から見とるからようわかっとる。そんなおまえがただの復讐のためだけにその先生に乱暴するわけあれへん。そやろ?」
「……」
「それに、おまえ、先生の中に突っ込んだこと、まだあれへんのやろ? セックスまでいってへんのやろ?」
将太は唇を噛みしめて黙っていた。
「おまえは、その先生に惚れとるんとちゃうか?」
「……違うし……」
「ひょっとしたら、その先生もおまえに心奪われ始めとんのかもしれへんぞ」
将太は動揺したように身を固くして目を伏せた。「た、単なるエロ教師なんだろ」
「考えてみ、学校の中っちゅうリスク満載の場所でやで、昼間っから、しかも毎週決まって水曜日に、おまえの相手しとるんや。ただのエロ教師やったら、おまえをホテルに連れ込むなり、自分の部屋に連れ込むなりするもんやろ? しかも曜日関係なく。彼女がなんでそんな危険を冒してまで学校で毎週毎週おまえにつき合うとるんか、っちゅうことが問題なんや」
「……」
「水曜日、っちゅう決まった日に、覚悟を決めておまえにぶっかけられて汚されとる。その先生には、何か思いがあるはずや」
ケネスは静かに言った。「好きなんやろ? 将太」
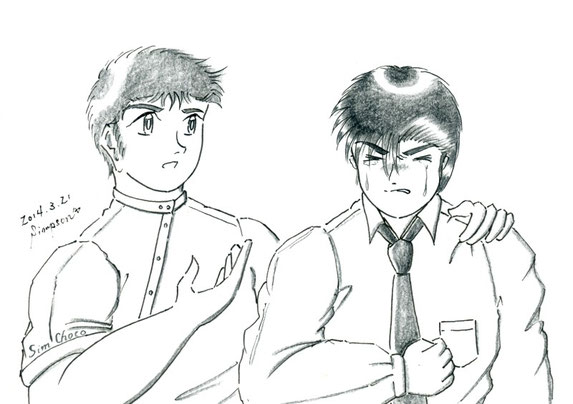
「あいつが、あいつがかあちゃんに似てるからいけないんだ!」将太は拳を握りしめた。「俺、俺、かあちゃん大好きだったんだ!」将太の目から涙が溢れ始めた。「なのに、なのにっ! んっ! んっ!」
「将太……」
「俺、鷲尾先生に初めて抱きしめられた。昨日。俺、復讐のつもりで出して、ぶっかけてやったのに、先生は俺を抱きしめてくれたんだ。縛ったり、服破ったり、乱暴なことばっかしてたのに、あの人、俺をぎゅって……」
将太は肩を震わせて泣いた。
ケネスは立ち上がり、将太の横の椅子に座り直して、その肩に手を回した。
店の奥から開店の準備をしていたマユミがケネスに視線を送った。ケネスはマユミに目を向けてかすかにうなずいた。
「ケニーおっちゃん……」
「なんや?」
「おっちゃんは、なんで俺を殴らないんだ?」
「なんや、おまえ殴られたいんか? M男なんか?」
将太は涙を拭って呆れたように笑った。「違うし」
「おやっさんから殴られたりしたこと、ないんか? 将太」
「じいちゃんは……」将太は一瞬言葉を詰まらせた。「中学校の頃までは、俺をたたいてくれてた」
「中学校?」
「病気の親父からは、そんなことされたことない」
「そうやろな……」
「でも、かあちゃんが出て行ってから、俺、今まで一度も殴られたことない」
「そうなんか?」
「あんまり厳しくなくなったんだ、じいちゃん」
「……」
「……なんでかな」
「おまえが不憫でしかたないんやな、おやっさん……」
「ふびん? ふびんって?」
「ちゃんとしつけなあかん、思てるけど、可愛い孫が自分から離れていくのんも怖い。親のいないおまえをどう扱うていいか、わからへんねんな、おそらく……」
将太は顔を上げた。「じゃあ、じいちゃんの代わりにおっちゃんが殴ってよ、俺を」
「実はな、さっきおまえが先生を犯した、言うた時、危うく殴りかかるとこやった」
「殴ってもよかったのに」
「おまえを殴れば、テーブルがひっくり返って壊れーの、上に乗っとるカップが落ちて割れーの、床がコーヒーで汚れーの。後が大変や。わい逆上したら手加減なしやからな。健太郎がタバコに手え出した時は、リビングのテーブル一台、コーヒーカップとソーサー2客、ほんで健太郎のシャツと前歯おしゃかにしてしもた。」
「えっ? あの時の健太郎、おっちゃんの仕業だったの?」
「仕業てなんや、わいは親としてあいつを指導したんやないか」
「顔、思いっきり腫らしてたじゃん。高一の時だったよね……」
「友達に誘われた、言うて言い訳しくさったから、わい許さへんかってん」
将太は神妙な顔で、ごくりと唾を飲み込んだ。
「お、おっちゃん、そんなに厳しい人だったんだ……」
「親の責任や。子がまっとうに生きていくためには、心を鬼にせなあかんことかてある」
将太は意を決して立ち上がった。「殴ってよ、ケニーおっちゃん」
「おまえ、どうなってもええんか?」
「目を覚ましたいんだ、ちゃんと」将太は真剣な顔でケネスの目を見た。「お願いだよ。じいちゃんの代わりに……」
「そうか。ほな」ケネスも立ち上がり、将太を自分の方に向けた。「覚悟せい!」
パアーン!
乾いた音が店中に響き渡った。店の隅のマユミが驚いて駆け寄ろうとしたのを、ケネスは目で制止した。
将太はぎゅっと目をつぶって身体全体を硬直させていた。

ケネスは将太の肩に優しく手を置いた。「終わりや、将太」
「え?」将太は意表を突かれたように目を瞬かせた。
「こ、これだけでいいの?」
「わいが健太郎どつき回した後な、あそこにおるマユミおばちゃんにわいがどつき回されてもうた。大事な息子に何てことすんねん! やり過ぎや、ってな」ケネスはウィンクして見せた。
「おっちゃん……」将太は少し涙ぐんでケネスの顔を見た。
「ええか、よう聞くんやで、将太」
将太はケネスに殴られた左頬を押さえて、脱力したように椅子に座り直した。
「わいが今殴ったんは、おまえがその先生をちゃんと守ってやらんかったからや」
「守る?」将太は顔を上げた。
「おまえが毎週水曜日にやっとるんは、レイプやない。もはや和姦や」
「わかん?」
「おまえも、先生もお互いに惹かれあっとる。同意の上での行為や」
「え?」
「そやけどな、おまえの行為がエスカレートして、避妊もなんもせんと、何かの拍子に先生と繋がって、もし妊娠させでもしたらどないするつもりや? 責任とれるんか?」
「そ、そんなこと……」将太はまたうつむいた。
「妊娠したところで中絶したらええ、なんて簡単に思てたら、今度こそ承知せえへんぞ。テーブルひっくり返してでも、おまえをしばき倒したるからな」
ケネスは席を立ち、何も言わず店の奥に消えた。
取り残された将太は不安そうに周りを見回した。
ケネスはすぐに戻ってきた。手には小さな箱が握られていた。
将太の横に座り直したケネスは、その箱を将太に握らせた。
「たぶんな、おまえは初めからその先生のこと好きやったはずや。自分で気づいてへんかっただけや。そやからそうやっておまえの心を守ろうとしてくれてはる先生をおまえも守らなあかんやろ? 心も身体も」ケネスはウィンクをした。
将太は小さくコクンとうなずいた。
「先生もおまえのその気持ちには早よから気づいてはった、思うで」
「え?」
「そら、初めはおまえを担任として相手してはったんやろけど、教師の責任感っちゅうか、おまえを何とかしたらなあかん、思て、おまえの身体の要求にも嫌々応えとったんやろな。そやけど、そんなこと繰り返す内に、おまえの中の苦しみにも気づいていった、そんなとこやろ。それに」
ケネスはにやりとして声を潜めた。「おまえ、先生の好みの生徒やったんとちゃうか?」
将太は赤くなって慌てた。「そ、そんなわけ、ないだろ! な、何言ってんだよ、おっちゃん」
「いやいや、大いにあり得るこっちゃで。おまえ、なかなかのイケメンやしな」ケネスは笑いながらカップを口に持って行った。
将太がぽつりと、しかしはっきりした声で言った。「俺、先生に謝らなきゃ……」
ケネスはカップを口から離した。「そうやな」
将太は立ち上がった。ケネスは彼を見上げた。
「コーヒー代、いくら? それに、こ、これも……」将太はケネスに手渡された小箱を持ち上げた。
「かめへん。持っていき」
「え? でも……」
「ほたら、出世払いせえ」
「『出世払い』?」
「おまえが働き始めて、最初にもろた給料から払え、っちゅうこっちゃ」
「おっちゃん……」
「コーヒーはたった450円やけど、その金も働かな手に入らんのやで。おまえのじいちゃんのように誠実に働かな」
「わかってる……」
ケネスも立ち上がり将太に歩み寄って、その肩を軽く叩いた。
「今からどないすんねん?」
「学校に行くよ」
「学校に?」
「だって、俺、鷲尾先生に土下座しなきゃなんないし」
ケネスはふっと笑った。「その後、抱きしめてやり」
将太は頬を赤く染めて笑った。
将太が自転車に跨って、焦ったように学校の方角に走り去った後、見送ったケネスの鼻に冷たい雨粒があたった。
「降り出したみたいやな……」
1.音楽室での出来事|2.明かされる秘め事|3.目覚めの朝|4.ずぶ濡れのキス|5.門出
ホーム|Chocolate Time シリーズ 本編第1期 本編第2期 外伝第1集 外伝第2集 外伝『雨の物語集』 外伝第3集|Chocolate
Time シリーズ総合インフォメーション




































