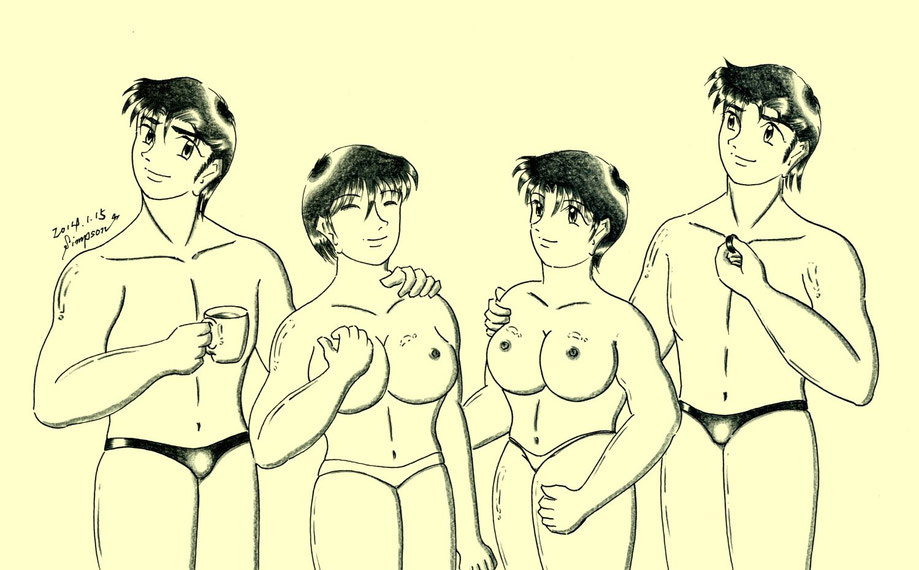Twin's Story 外伝 "Hot Chocolate Time" 第2集 第12話
夫婦交換タイム
1.幸せな夫婦|2.フラッシュバック|3.交渉|4.キス|5.ホテル|6.浴室|7.ドリンク|8.前戯|9.昔話|10.クライマックス|11.もう一つのクライマックス|12.余韻

〈12.余韻〉
▼
龍とミカの身体は動かなくなった。しかし二人の息はまだ荒い。
龍と繋がったミカの谷間から、どくどくと白い液が溢れ出ていた。
「龍、おまえもすごいな。量が……。どんどん溢れてるぞ。さっきもあたしの口にあんだけ大量に出したくせに」
「って、父さんもでしょ?」龍の顎から汗がぽたりとミカの首筋に落ちた。
「ああ。いつも中出しされた後はシーツを取り替えなきゃなんない」ミカは笑った。「おまえも真雪の中に出した後はそうなのか?」
「俺たちは、中に出すって時はバスタオルを二枚ぐらい敷いてやるよ」
「へえ。用意周到だね」
「そのまま抱き合って眠りたいしね。シーツが濡れてると、気持ち悪いじゃん」
「こんどあたしたちもそうやってやろう。いいこと聞いた」
「お勧めですよ、母上」
「それにしても」龍はミカの顔をしげしげと見た。
「なんだ?」
「すごいテクニックだった……俺、二度もイかされるなんて思わなかったよ」
「ふっふっふ……」
「わざとやってたの? あれ」
「おまえも知ってるだろ? 必殺『搾精ダブルスクリュー』」
「あれがそうなの? ケン兄(健太郎)を快楽の海に突き落としたっていう」
「その通り」
「もう気が遠くなりそうだったよ。尋常な気持ち良さじゃなかった」
「そうか。そりゃ良かった」ミカはにっこりと笑った。
「そういうお前だって」
「え? 何?」
「真雪から聞いてはいたけど、お前の抱擁はハンパないな」
「抱擁?」
「お前の腕に抱かれただけでイきそうになる」
「そうなの?」
「ああ。真雪も言ってた。聞いた時はほんとかよ、って思ったけど、ほんとにそうだった」
「ふうん」
「何だよ、自覚ないのか?」
「そんなこと考えたことないよ」
「何て言うか、抱く力も、温かい手の感触も、撫でる場所も全部ツボ。これ以上のものはない、っていう気持ち良さだったぞ」
龍は頭を掻いた。
ミカは龍の目を見つめた。「ありがとうな、龍」
「満足させられたかな? 俺。母さんを」
「もちろん。でも、あたし、途中からおまえが龍なのかケンジなのか区別がつかなくなってたよ」
「え? そうなの?」
「中に入っている感触が、全く同じ」
「感触?」
「動き方も、身体の温かさも、呻き声も、それに、」ミカは龍の顎にキスをした。「出し方も」
「出し方?」
「弾けるように中で噴き出すのがわかるんだ。親子なんだね、やっぱり」ミカはひどく嬉しそうに言った。
「とりあえずは合格ってことかな」
「もう完璧だ。おまえを息子として愛し直せた。同時にケンジへの想いも強くなった気がするよ。あたしこそ、いろいろ無理言って悪かったな。龍」
「気にしないで。それより、母さんの身体、病みつきになりそうだよ」
「そうか。またケンジと取り合いになるのかな」
そして二人はまた熱く深いキスをした。
しばらくして口を離したミカが言った。「龍」
「うん?」
「抱いて。また、きゅうって」
「いいよ」
龍はミカの背中に腕を回し、ゆっくりと抱きしめた。
ミカは声にならない喘ぎ声を上げ、ため息をついて、目を閉じた。
▽

ケンジと真雪の身体は動かなくなった。しかし二人の身体はまだ熱かった。
ケンジと繋がった真雪の谷間から、どぷどぷと白く濁った液が溢れ出ていた。
「ま、真雪、ごめん、溢れてる……」
「ふふ。大丈夫。慣れてるよ。龍もそうだから」
「そ、そうか……」
「噂通りだね。ケンジおじも大量に出すんだね。さっき口の中にあれだけいっぱい出した後なのに、すごいね。絶倫だよ、ケンジおじ」
ケンジは照れたように笑った。「さ、三回分だからな。気持ち悪くないか?」
「だから龍ので慣れてるってば」
「俺がミカに中出しした後も、一枚や二枚のティッシュじゃ全然足りないんだ」
「でしょうね。この量じゃ」
「俺たちはいつも絞った濡れタオルを用意しとく」
「いい考えだね。あたしたちもまねしよ」
「しかし……」ケンジは困ったように真雪の笑顔を見下ろした。
「どうしたの?」
「すごかった……」
「何が?」
「おまえ、イくときいつもああなのか?」
「ああなのか、って?」
「もう、俺、どうにかなっちまうかと思ったよ。吸い込まれて、押さえ込まれて、ぶるぶる刺激されて……。おまえの中全体がバイブレーターだった」
真雪は小さく噴き出して、少し赤くなって言った。「気に入ってくれた? ケンジおじ」
「イくにイけなくて……もう限界って時にいきなり突き落とされる。あんな経験は初めてだった。拷問されているようで……。でも無茶苦茶気持ち良かったよ、真雪」ケンジは照れたように笑った。
「良かった。ケンジおじを満足させられて」
真雪もにっこり笑った。
「あんなワザ、いつ覚えたんだ?」
「二人の子どもを産んでから、あたし膣トレに励んでたんだよ」
「へえ!」
「龍をずっと気持ちよくさせてあげたかったしね」真雪はぱちんとウィンクをした。
「その成果なのか? あのワザ」
「結果的にそうなるかな。いつの間にか自然とできるようになってた」
「龍は幸せモンだな」ケンジは微笑んだ。
「いつもいっぱい汗かいて、死にそうな顔をして、大声上げてるよ」
「だろうな。いやあ、凄まじかった……」
ケンジは真雪の髪を撫でながら言った。
「真雪はどうだった?」
「もう完璧だよ。ありがとうケンジおじ。すっかり元通り。もう100㌫回復」
「そうか、それは良かった」
「あたし、あんな場所で動かれるの、初めてだった。すっごくいい気持ちで、今まで感じたことのない快感が身体中を突き抜ける感じがしたよ」
「オトコってヤツは、どうしても奥まで押し込みたがるものだけど、女性の浅いところって、結構敏感で感じやすいんだ」
「あたしオンナなのに知らなかったよ、今まで」
「龍にもちゃんと教えとくよ」ケンジは真雪の顔を見て微笑んだ。
「最後はちゃんと奥まで来てくれたね。ありがとう、ケンジおじ」
「真雪に残っていた1㌫を消し去るため。そうだろ?」
「うん」
「っていうか、おまえが奥まで吸い込んだんだろ」
「えへへ……」
「でもな、俺もオトコだから、やっぱり最後は奥深いところでイきたかった。それも本音」ケンジは照れたように笑って頭を掻いた。
「いいんだよ、それで」真雪も微笑んだ。「それにケンジおじ、続けて三回、イってくれたね。約束以上」
「な、なんだか一回じゃ収まらなくて……」
「おじさんほんとに絶倫だね。でも嬉しかったよ。あたしもとっても感じてた。すごく気持ち良かった」
「おまえの身体が、あまりにも魅力的で、俺も何だか、目一杯燃えちまった」
「不倫してるみたいだった?」
「いや、したことないから」
「ごめんね、あたし最中におじさんのこと、呼び捨てにしちゃって……」
「構わんよ。かえって冷静に『ケンジおじー』なんて呼ばれたら、冷めちまう」
「そうだね」真雪は笑った。「ほんとにありがとう。最高の癒しだった」
「俺もだ。真雪」
「ケンジおじに身体の奥に出してもらったら、なんだか、」真雪は顔を上げてケンジの目を見つめた。「龍のことが今までよりももっと好きになっちゃった」
「なんでそうなる?」
「貴男の息子への愛情そのものをあたしも手に入れた気がして……。それに、」
真雪は悪戯っぽく笑った。「ケンジおじが中にいる時、あたし龍のものが入ってるのか、って思ってた」
「え? な、なんだよそれ」
「龍のものとケンジおじの、すっごく似てる。っていうか、ほとんど同じ感触」
「そ、そうなのか?」
「うん。さっき咥えたときも思った。カタチや大きさもそうだけど、温かさも同じ。それに中に出すときの衝撃が、もうびっくりするぐらい同じだった」
「衝撃?」
「うん。力強く噴き出す衝撃だよ。それにイく時の腕の力の込め方も、呻き声も同じ。苦しそうな表情も。あたし、途中から龍に抱かれてるのか、って錯覚してたよ」
「そうなんだな……」ケンジは照れたように頭を掻いた。「やっぱり親子なんだな」
真雪はケンジの鼻を人差し指でつついた。
「ケンジおじの素敵な染色体が、確実に次世代に受け継がれてるってことが、あたしよくわかったよ」真雪は微笑んだ。「身をもって」
「大げさだぞ、真雪」ケンジも真雪の鼻の頭を人差し指で軽くつついた。
「息子の健吾もきっとこんな素敵な紳士になるんだね。楽しみ」
「いつの話だよ」

「ねえ、ケンジおじ」
「うん?」
「キスして」
「いいよ」
少し恥ずかしげにケンジは微笑み、真雪を抱き直して静かで熱く深いキスをした。
しばらくしてケンジは口を離して真雪の目を見つめた。
「ケンジおじのキスは、本当に最高。龍もかなわない。悔しいけど」
「そうか?」
真雪は小さな声で言った。「また濡れて来ちゃった……」
「おいおい……」ケンジは困った顔をした。
真雪はケンジの背中に腕を回して、その逞しい胸に顔を埋めた。
――翌週
真雪が毎月定期的に訪れる酪農研究所のロビーで、ロマンスグレーの髪をきちんと整えた所長が温厚な微笑みをたたえて彼女を出迎えた。
「やあ、シンプソンさん、いつも来て頂き、感謝します」
その初老の男性は右手を思わず出そうとしてすぐに引っ込めた。
真雪は左肩のバッグをかけ直し、にっこり微笑みながら彼に近づいて、すっと右手を差し出した。
所長は意外そうな顔をして一度真雪の顔を見た後、それでもすぐに真雪の手を握り返した。
「こちらこそ、所長さんにはいろいろとお気遣い頂いて」そして真雪はまた柔らかく微笑んだ。
所長は声のトーンを上げた。「暑かったでしょう。どうぞ、こちらに。冷たいカフェオレをごちそうしましょう」
「恐れ入ります」
真雪は小さく頭を下げて彼の後をついて歩いた。
2014,1,3(2014,1,20) 脱稿
※本作品の著作権はS.Simpsonにあります。無断での転載、転用、複製を固く禁止します。
※Copyright © Secret Simpson 2014 all rights reserved
「夫婦交換タイム」あとがき
僕がこの「Chocolate Time」シリーズを書き始めた時、双子の兄妹による恋物語、と銘打っていました。要するに近親相姦をテーマにした、というわけです。その後、主人公の二人は別々のパートナーと結婚しましたが、それでもこの兄妹の繋がりは続き、妻や夫の公認の元で抱き合い、癒し合う関係を続けています。
この『不倫でないセックス』は、一つの理想としてこのシリーズ全体にずっと流れています。「理想」と書きましたが、もちろんそれは現実の世界における理想というわけではなく、僕の中で、こういう関係だったら素敵だろうな、ぐらいの非現実的な「理想」です。
「Chocolate Time」はその全てのエピソードがハッピーエンドです。読者を(作者も)ほのぼのとした幸せな気分にさせることが目的の一つ。現実にはなかなか起こりえないだろうけれど、こんな家族、こんなきょうだい、こんな友達の関係だったらきっとみんな幸せな気分になれるに違いない。そう思いながら日々ペンを走らせています。
今回のこの「夫婦交換タイム」は、その一つの到達点。ラブラブでアツアツの若い夫婦が、それぞれ別々の異性と交わる。しかもそれは母と息子、伯父と姪の間柄をパートナーとして。
思いがけない事故や、ふらついた気の迷いではなく、ちゃんとした理由があり、それを当事者がみんな納得して臨む夜の営み。こういった「合法的な」行為を、いかに自然に描くか、ということを、実はこれまでずっと考え、文章にする時の表現に力を注いできたのです。
だから今回、一度不倫をさせてひどく辛い目に遭わせてしまった真雪が、伯父でもあり夫の父親でもあるケンジと繋がり合うという出来事を、読者にも納得のいくように描く。これは僕に与えられた一つの大きな試練でもありました。
「Chocolate Time」の登場人物たちは、決して軽はずみな気持ちで肌を合わせることはしない、というのが僕の中での鉄則。だから僕の小説は巷のアダルト小説に比べて刺激が少なく、あまりどきどきしないのです。「ああ、このまま流されたらこの女は……」とか、「この男、我慢できずにきっと押し倒すな」とか、「やばいだろ、こんなことしちゃ」という、現実離れした緊張感が読者の心に生まれにくいのです。同じように現実離れしていても、やはり「和姦」より「強姦」、「癒し合い」よりも「貪り合い」の方が、アダルト小説をわざわざ読みに来る人にとっては面白いのだと思いますし、そもそもそういうドキドキ感を求めてこういう物語を開かれるのでしょうから。
そんなわけで、この「夫婦交換タイム」の登場人物を始め、僕の話の中のキャラクターは、たとえ正規のパートナー以外が相手でも、いざコトに及ぶ時、みんな「和姦」で「癒し合う」ような行為を繰り広げるのです。ただ、このエピソードを読まれて「結局エッチ好きなだけなんじゃ?」とか、「誰でもいいからセックスしたいって思ってるんでしょ?」と感じられるのは、僕にとって非常に不本意なこと。仮にもしそう思われたのであれば、それは僕の文章力の弱さや表現力の拙さが原因であって、決して元来品行方正な登場人物のせいではありません。
Simpson