Twin's Story 外伝 "Hot Chocolate Time " 第2集 第8話
《精通タイム 後編》

5月。鈴掛南中学校恒例の校内クラス対抗リレー大会が行われることになっていた。
その日は、そのリレー順を決める話し合いが行われていた。
健太郎ともう一人の女子生徒が教室の前に立ち、司会をしていた。
その話し合いは紛糾していた。誰が第一走者になるか、誰からバトンを受け取り、誰にバトンを渡すのか、誰がアンカーを務めるのか……。
「えー、いやだよ、俺、加奈子の後なんて、あいつ遅いからきっと最下位で来るよ。目立っちゃうだろ」
「なんであたしがスタート? 他のクラスはみんな男子なんでしょ?」
「冗談じゃないよ。アンカーなんて他にやるやついるだろ!」
健太郎は困り果てていた。「みんな協力的になってください!」
がやがやとクラス内に耳障りな声が充満し、それが三分程続いた時、ばん! と机を叩く大きな音がした。教室は水を打ったように静まりかえった。
「いいかげんにしろ!」修平は立ち上がり、いつもの大声を張り上げた。「クラス対抗なんだろ? 目的はクラスの団結力を強めるってことだろ? 何だよ、おまえら勝手なことばっか言いやがって!」
健太郎はぽかんと口を開けて、修平の興奮して赤くなった顔を見た。

「みんなやりたかねえって言った時点で俺たち一組は負けてら。それより、」修平は席を離れ、つかつかと前に進み出て健太郎の横に立った。「おまえら司会してるこの二人の気持ちも少しは考えたらどうなんだ? 思いっきり困ってんだろ!」
担任が窓際に立って腕組みをしたまま、小さくうなずいた。
「この二人は、俺たちのリーダーだ。一組をまとめようとしてんのに、おまえらが協力しねえでどうすんだ。リーダーを頑張らせるんじゃなくて、周りの俺たちが頑張んなきゃいけないんじゃねえのか?」
修平は健太郎に向き直った。「俺がアンカー走ってやるよ。あんまり速くねえけどな」
「え?」
「こんだけ偉そうなこと言った責任をとらなきゃな」そう言って修平は健太郎にウィンクした。
◆
その日の夕方、プールの脇にある水泳部の部室から着替えを済ませて出てきた健太郎は、修平に呼び止められた。「シンプソン」
健太郎は緊張したように少し顔をこわばらせて足を止めた。
「何か、おまえのこと『シンプソン』って呼ぶの、変な感じがすっから、今からケンタって呼んでいいか?」
修平は少し赤くなって頭を掻いた。
「え? ケンタ?」
「健太郎のケンタ。イヤか?」
健太郎の頬の筋肉が弛んだ。
「いいよ。じゃあ、俺も君のこと、修平って呼ぶ」
「わかった」修平はにっこり笑った。
「一緒に帰ろうぜ」修平が言った。
「いいよ」健太郎も笑った。
二人は自転車を押しながら正門を出た。
「俺んち、河岸団地なんだ。」
「河岸小の近く?」
「ああ」
「あの、修平、ごめんな。」
「何が?」
「入学式の日、いきなり殴りかかっちゃって……」
「あれは俺が悪いんだ。謝らなくていいよ。おまえは」
修平は爽やかな顔を前に向けた。「でも、いいな、おまえ守りたくなる妹がいて。俺、兄貴しかいねえから、その気持ち、よくわかんねえけど」
「シスコンって思われたかな……」
「シスコンなのか?」修平は健太郎の顔を見た。
「そうかもしれない」
「へえ。じゃあ、おまえあの胸、いつもじろじろ見てんの? おっと! また殴られっかな?」修平は自転車を止めて身構えた。
健太郎はふっと笑った。「心配するなよ。もう君には手は出さないよ」
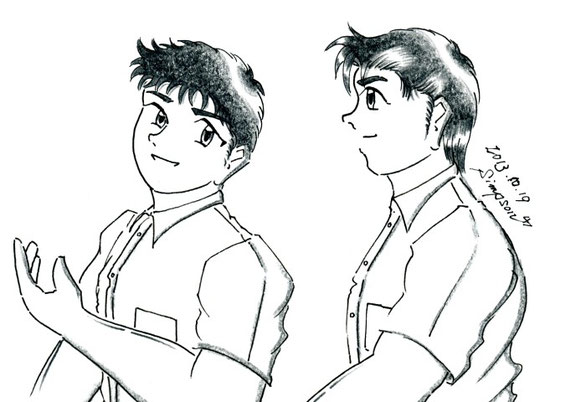
「おまえも、そういう事には興味あんだろ?」
「そういう事?」
「女子のカラダだよ」
健太郎は赤くなって目をそらした。
「あんな妹と一緒に暮らしてっと、変な気になるんじゃねえの?」
「どうかな……」
二人はT字路にたどり着いて自転車を止めた。
「今度、おまえんちに遊びに行っていいか?」修平が唐突に言った。
「え? あ、ああ。いいよ。いつでも」
修平は嬉しそうに声のトーンを上げた。「そうか。じゃあ、今度の土曜に行くから。部活終わったら」
「剣道部は午前中?」
「そうだ。水泳部も土曜は午前中で終わりだろ?」
「うん」
「じゃあな。約束したから」
修平は交差点を左に折れて、手を振りながら健太郎から離れていった。
★修平と健太郎はこの時からずっと親友同士です。
◆

――土曜日の午後。
修平は自転車を『Simpson's Chocolate House』の駐車場、プラタナスの木陰に止めた。店の入り口から健太郎が出てきた。
「修平」
「よ、ケンタ」修平は小さく手を上げた。
健太郎は修平を店に招き入れた。そして店内の喫茶コーナーのテーブルに彼を座らせた。
「なんか、すげーな。甘い匂いが充満してる……」
「チョコレートハウスだからな」健太郎は笑った。「来たことないのか? うちに」
「家族と一緒に来たことはあっけど、何かこっぱずかしくて中には入ったことねえな」
「なんで恥ずかしいんだ?」
「だってよ、女ばっかじゃん。客」
「女の人に興味があるんじゃなかったっけ? 修平」健太郎は悪戯っぽく笑った。
「うっせえよ」

店の奥から所々に茶色の染みのついた白いユニフォーム姿の、目の青い男性が、グラスを二つ持って、そのテーブルにやって来た。
修平は思わず立ち上がった。「こんにちは」
「おお、なかなか礼儀正しい少年やないか。君が修平君やな?」
「お邪魔します、おじさん」
ケネスはグラスをテーブルに載せると右手を修平に差し出した。修平は一瞬戸惑った後、ケネスの目を見てその手を握り返した。
「入学した日に、この健太郎と殴り合いのケンカしたんやろ?」ケネスが面白そうに言った。「めっちゃおもろい話やって、家族で大爆笑やったわ」
「す、すんません……」修平は赤くなってうつむいた。
「健太郎の人生初の殴り合いのケンカやってんで。感謝しとるわ」
「え? 感謝?」
「そや。胸襟開いてぶつかり合えるのんが、ほんまの友だちや。仲良うしてやってな」
ケネスはそう言ってにこにこ笑いながらその場を離れた。
「おやっさん、外国人なのに、関西弁なんだな」
「いや、ダブル。じいちゃんがカナダ人。ばあちゃんは大阪の人なんだ」
「そうなんだ。だから関西弁なんだな。でも見かけは思いっきり外国人だよな。目も青いし」
「確かにな」健太郎はグラスを手に取った。「君も飲めよ」
修平もそのアイスココアのグラスを手に取ってストローを咥えた。
「うめえ!」修平は目を見開いて大声を出した。「すんげーうめえよ、これ」
「チョコレート屋だからな、うちは」健太郎は笑った。
健太郎は、店の裏手にある離れの別宅に修平を案内した。
その玄関先で、修平はぽかんと口を開けたままその建物を見上げた。
「何だ、どうした? 早く入れよ」
「お、おまえんち、めちゃくちゃ金持ちなんだな……。家が二つもある……」
「チョコレート買いに来てくれるお客さんのお陰だよ」健太郎は修平の手を引いて、玄関の中に連れ込んだ。
健太郎は修平を部屋に招き入れた。
「隣が妹の部屋なのか?」
「うん」
「隣同士って、やっぱいろいろ考えるんじゃねえの?」
健太郎は呆れ顔をした。「まだそんなこと言ってる」
「どきどきしねえのか?」
「生まれた時からずっと一緒の妹だからな。あんまりそんな気にはならないよ」
「そうか……。でも、妹も同じ水泳部なんだろ? 水着姿見てどきどきすんだろ? あんだけの巨乳だし」
「いいかげんにしろ」健太郎は笑った。「修平って、もうそんなことに興味があるのか?」
「ある」修平は真面目な顔で即答した。「あんだろ? おまえも」
「え?」
「中学生になったからには、エロいこと考えるだろ、普通に。男だったら」
「そ、そうなのか?」健太郎は落ち着かないようにベッドの端に座り直した。
修平は持ってきたバッグをごそごそ探って、中から一冊の雑誌を取り出した。「兄貴が持ってた雑誌」
それは表紙にきわどい水着姿の女性が大写しになった雑誌だった。
「な、何だよ、それ!」
「エロ雑誌」
「なんでそんなもの持ってくるんだよ」健太郎は思いきり赤面していた。
「こんなの見たい、なんて思わねえの? ケンタ」
「お、おも、おも……」
「思うだろ? 思うよな」
「そ、そんなの見て興奮してるのか? 修平」
「兄貴に貸してもらって、ヌいてるぞ、ここんとこ、ほぼ毎日」

「毎日? ぬいてる?」
「は? 知らねえの? おまえ、まだ」
「な、何のことだよ」
「出したこと、ないのか?」
「何を?」
修平は雑誌を傍らに置いて、健太郎の横に座り、肩に手を掛けた。「そうか、おまえまだ未経験なんだな」
「な、何のこと、言ってるんだよ……」
「いいか、よく聞け、ケンタ。将来女とセックスするのに、男は射精しなきゃなんない」
「セ、セ、セッ……クス」健太郎は思いきり赤面して修平の顔を見た。
「射精、ってことぐらいわかるだろ?」
「しゃせい? 画を描くこと……じゃないよな?」
「ばあか。セックスすんのになんで画を描かなきゃなんねえんだよ。精液を出すんだよ。」
「よくわかんないよ。」健太郎はどぎまぎしながら修平の手を肩から離させた。
「おまえのここも、時々でかくなったりするだろ?」修平はそう言いながら健太郎の股間に、穿いていたジーンズ越しに手を当てた。
「やめろよっ!」健太郎は焦って修平の手を払いのけた。
「今日、風呂場で、やってみろよ」
「何を?」
「自分のこれを握って、しごくんだ」
「しごく?」
「エロいこと想像しながらこうやって」修平は自分の股間辺りに手をやり、ペニスを握る仕草をした。「前後にしごいてっと、だんだん気持ち良くなって、最後には先から白いどろどろした液が出てくんだ。それが精液」
「……」
修平は健太郎の顔を覗き込んだ。「ほんとに知らねえのか? ケンタ」
「し、知らないよ……」
「やってみろよ、今夜。絶対、最高に気持ちいいから」
「……」健太郎は言葉をなくしてただうつむいていた。
◆
その日の夕食時、健太郎は隣に座った真雪からいつもより少し距離を置いていた。
「何や? どうかしたんか? 健太郎。顔、赤いで」
健太郎はちらりと真雪を見て、すぐに食卓に目を戻した。「べ、別に……」
「どうしたの? ケン兄」
「何でもない」

「そう言えば、今日、天道くんが来たんだって?」
「う、うん」
「すごいね。ケンカしたのに友だちになったんだね」真雪は笑った。
真雪の向かいに座ったマユミがサラダを小皿に移して健太郎の前に置いた。「礼儀正しくて、元気な子なんでしょ? 健太郎」
「なかなかええ子やで」ケネスがワイングラスを手にした。「大事にするんやで、これからも」
「なんで仲良しになったの? ケン兄」
「なんか、いいやつなんだ」
「いいやつ?」
「正義感が強くて、ちゃんと意見を堂々と言う」
「へえ」
「今までに会ったことのない性格のヤツなんだ。教えられることもいっぱいありそうで……」健太郎はご飯を口に入れた。
「でもさ、なんでケンカしたの? ケン兄と天道くん。何が原因だったの?」
「え? そ、それは……」健太郎は真雪の顔を見てますます赤くなった。
「あたし、びっくりしちゃったよ、あの時。ケン兄があんなに暴れるの、初めて見た」
ケネスがマユミをちらりと見た後、真雪に向き直った。
「些細なことや。真雪。中学生男子の他愛もない感情のぶつかり合い、っちゅうかな」
健太郎はケネスを見て頭を掻いた。
真雪が言った。「ふうん……。そうだったんだ」
「ごちそうさま」健太郎は立ち上がり、食器をキッチンに運んだ。「風呂に入ってもいい? 母さん」
「いいわよ」
健太郎は脱衣所で服を脱ぎ、バスルームの戸を開けた。中に立ちこめていた白い湯気が健太郎の身体にまつわりついた。
彼は一度掛かり湯をして、バスチェアーに腰掛けた。そして右手で自分のペニスをそっと握りしめた。
少しずつ、彼のペニスが大きくなってきた。そしてそれはどくんどくんと脈打ち始めた。
健太郎は思わず手を離した。
大きくなったペニスはびくびくと上下に脈動している。
『手に石けんの泡をつけてやると、すんげーいい気持ちなんだぜ』
健太郎は昼間、修平が言っていた言葉を思い出していた。
彼は石けんを手に取り、両手で泡立てた。そして再び右手で自分のものを恐る恐る握った。そして静かに前後にしごき始めた。
ぬるぬるしたその感触に、今まで感じたことのなかった疼きが下腹の辺りに蠢き始めた。健太郎のペニスはますます大きく、硬く、熱くなっていった。
いつしか、健太郎は何かに取り憑かれたように激しく手を動かしていた。
カラダの奥から次々に沸き上がる、じんじんした痺れが、彼の全身をどんどん熱くした。
「あ、な、何だ……これ!」
健太郎は思わず声を上げた。「あ、あ、あああ!」

腰の辺りに強い脈動を感じて、健太郎は思わず仰け反った。その瞬間、彼が握りしめていたペニスの先から勢いよく白い液が迸り出た。
びゅくっ! びゅくっ! びゅくびゅくっ!
「あああああーっ!」
生まれて初めて感じる、その衝撃的な快感は、何度も繰り返し彼の身体に襲いかかり、その度に健太郎のペニスの先端から白い液が噴出し続けた。
「わああっ! な、何だ、これっ!」
健太郎はバスルームのタイルの床に大量に放出された白くどろどろした液が、シャワーの湯にゆっくりと流されて、排水口に吸い込まれていくのを、荒い息のままいつまでも見ていた。
◆
翌週の月曜日。健太郎は、教室に登校してきた修平の腕を焦ったように掴んで廊下に連れ出した。
「ケンタ、おはよう。何だ? どうした?」
健太郎はトイレの前まで修平を連れてくると、赤い顔をしてその友人の顔を見た。
修平はにやりと笑って、健太郎の肩に手を置いた。「そうか。やったか、ケンタ」
健太郎はかすかにうなずいた。
「す、すごかった……」健太郎はやっとそれだけ言った。
「だろ? これでおまえも俺と同じ一人前だ」修平は笑った。そして健太郎の肩を叩いた。「俺が毎日やってる、っていう気持ちわかんだろ?」
修平は上目遣いに健太郎の顔を見て、小声で言った。「昨夜もやったのか?」
健太郎は恥ずかしげにまたうなずいた。
その日の放課後、修平は教室を出る健太郎を捕まえて耳元で囁いた。「部活終わったら一緒にいいとこ行こうぜ」
「いいとこ?」
「ああ。勝負しようぜ」
「勝負?」
「楽しみにしてな」修平は笑って、剣道の道具袋を担ぎ直した。
部活帰り。修平に連れられて、健太郎はいつもと違う道を自転車で走っていた。先を行く修平が時々振り返って笑いかけた。健太郎は少し不安そうにぎこちない笑顔で返した。
すずかけ町の北西を南北に走る大きな川があった。その川沿いに『すずかけ河岸団地』が拡がり、その一角に修平の家があるらしかった。
修平と健太郎はその川の堤防沿いの道をしばらく進んだ。
不意に修平が自転車を止めた。健太郎も自転車を降りた。
彼らの横をジョギング中の初老の男性が通り過ぎた。
学校を出た時にはまだ西の低い空にあった太陽はもうすっかり姿を隠している。薄暮のすみれ色の空が、広い川面に写って穏やかに揺らめいていた。
自転車を止めた二人は、堤防から川岸に伝う小さな獣道を降りて行った。
「こ、こんなとこで、何するんだ? 修平」
「いいから、着いて来いよ」
修平はにやにやしながらそれだけ言うと、健太郎を従えて小さなプレハブ造りの小屋を目指した。
その小屋の外壁を伝う鉄筋も、屋根の縁も、すっかり錆びて茶色になっていた。小屋の脇には大小の廃材が積み上げられていた。
修平は健太郎をその廃材に囲まれたスペースに連れ込んだ。
「秘密の場所なんだ。ここ」
「秘密の場所?」
「ここはこの小屋の陰になってて上の道からも見えねえし、向こう岸からも見えねえ、絶好のオナニースポットなんだぜ」
「オ、オナニー?」
「おまえが昨夜風呂でやったことをそう言うんだ。知らねえのか? ケンタ」
健太郎は小さくうなずいた。
「おまえ、ほんとに何にも知らねえんだな」修平は遠慮なく呆れ顔をした。
「じゃ、じゃあ修平はなんでそんなこと、いろいろ知ってるんだよ」
「兄貴に教えてもらった」
「兄ちゃんって幾つなんだ?」
「エロ盛りの高校生だ」
「なんだよ『エロ盛り』って」
「そのエロい兄貴が教えてくれて、俺もオナニーやるようになったんだぜ」
「そ、そうなんだな……」
「ってか、おまえ、小学校でも習っただろ? 性教育で」
「性教育? ああ、あれは意味が全然解らなかったよ」
「意味?」
「うん。オトコとオンナのカラダの違いとかは解るけど、オトコのあれをオンナの中に入れて赤ん坊ができる、なんて言われても、何のことだかさっぱり解んなかった」
「ううむ……、ずいぶんいいかげんな教え方だったんだな」
「河岸小じゃ、もっと詳しく教えてくれたのか?」
「精液の中に精子が何億って泳いでて、セックスしてそれがオンナのカラダの中に入ると妊娠する。そのためにはおまえが昨夜やったような射精をしなきゃなんない」
「じゃ、じゃあ、あのどろどろしたのが精液?」
「そうだよ」
「あ、あれを女の人のカラダに入れるのか?」
「そうだよ」
「あ、あの中に、その、せーしが何億って泳いでるのか?」
「そうだよっ」修平はいいかげんいらいらしてきた。
「何億って、そ、そんなにたくさん……」
「人間の細胞の中で最も小さいんだと、精子って」
「精子って泳ぐんだ……。でもどうやって……」健太郎は頭を抱えた。
「俺もよく知らねえよ。そこんとこはな。でもよ、ピュピュッって出てくる、あんだけの精液の中に何億って精子がいるって、ちょっと信じらんねえよな」
健太郎は顔を赤くして言った。「セ、セックスって大変そうだ……」
「ま、俺たちがオトナになったら、解るんじゃね? セックスのしかたなんてよ」
「そ、そうだな……」
修平は健太郎の肩を叩いた。「よし、ケンタ、やろうぜ。暗くなる前によ」
「え?」健太郎は修平の顔を見た。その友人はにこにこ笑っていた。
薄暗くなって、向こう岸のビルの窓がいくつも白い四角形をランダムに並べ始めていた。
修平は出し抜けにベルトを緩め、学生服のズボンを下ろした。
「なっ!」健太郎は驚いて大声を出した。「な、何やってる、修平!」
「おまえも脱げよ。ここでやろうぜ、オナニー」
「こ、こ、こんな所で?」
「だから、誰も見てないって。それにかなり暗くなってるしな」
「で、で、でも……」
「おまえもオナニーの気持ち良さに目覚めたんだろ? どっちが遠くまで飛ばせるか勝負だ!」
健太郎は顔を赤くしたまま、しばらくじっと修平の顔を見ていた。修平は構わず穿いていたボクサーパンツを膝まで下げ、下腹部を露わにした。
「しゅ、修平……」
「早くやれよ!」修平が少しいらいらしたように言った。「俺だけやらせんな」
健太郎は慌ててベルトを緩め、修平と同じように下着を下ろした。川面を吹きすぎる風が、股間を撫でて、彼は小さく身震いした。
修平はすでに大きくなっていた自分のペニスを左手でしごき始めた。
健太郎も覚悟を決めて、右手でペニスを握った。手の中のそれはぐんぐん大きさと熱さを増してきた。
「くっ!」修平は目を閉じて苦しそうに短く呻いた。
「あ、ああ……」健太郎もカラダの奥から湧き上がる痺れを感じ始めた。
「出、出るっ!」修平のカラダがビクン、と震え、握りしめたペニスの先端から白い液が飛び出した。
それは何度も繰り返され、彼が立っている場所から2㍍ほど先の草むらに吸い込まれていくのを健太郎は見た。
「うっ!」健太郎も呻いた。そして彼のペニスからも白い液が迸り出た。
どびゅっ!
健太郎の身体から力が抜け、彼は思わずその場にひざまずいた。それでも射精の反射は続いた。
びゅくっ! びゅくびゅくっ!

白い雫が何度も何度も大きなアーチを描いて川の方に向かって発射された。
「す、すげえ……」横に立って、力尽きたペニスをまだ握っていた修平が小さく呟いた。「あんなとこまで……」
びゅくびゅくっ! びゅくっ!
健太郎は苦しそうに顔をゆがめ、その強烈な快感に耐えていた。
「ま、まだ出してやがる……」
飛ぶ勢いが落ちても、健太郎のペニスからはどろどろと精液が垂れ続け、彼の膝元にぼたぼたと落ちて草の中に広い水たまりを作った。
二人は自転車を止めた所まで戻った。辺りはすっかり暗くなっていた。
「完敗だ、ケンタ」修平が困ったように微笑みながら健太郎の手を取った。「信じらんねえよ。あんなに出すなんて」
健太郎は赤くなってうつむき、修平を上目遣いで見た。「そ、そうなのか?」
「おまえの精液の中には、何百億って泳いでんじゃね? 精子」
「修平は、いつもあれぐらい……なのか?」
「あれでも小学校の頃に比べっと、増えた方だぜ、量」
「そ、そうなんだ……」
「羨ましいなー」修平は星が瞬き始めた空を仰いだ。
「何が?」
「だって、ずっと気持ちいいんだろ? 出してる時」
「う、うん」
「いいなー、ケンタ」
修平は健太郎の顔を見てにっこりと笑った。「寄ってくか? うちに」
健太郎も微笑み返した。「いや、もう遅いから今日は帰るよ」
「そうか」
「またゆっくり遊びに行くよ。おまえんちに」
「そうだな」
「じゃあ、また明日な」健太郎は自転車に跨がった。
「今夜も風呂でやんのか? ケンタ」
「え?」
「あんまりやり過ぎっと、身体中の水分がなくなっちまうぞ。あんだけ出すんだから」
「ばかっ!」健太郎はまた赤面してペダルを踏み込んだ。
「ほどほどになー」
健太郎の背中に修平の声が届き、振り向くと、修平が左手を大きく振っていた。
Simpson 2013,10,13 脱稿
※本作品の著作権はS.Simpsonにあります。無断での転載、転用、複製を固く禁止します。
※Copyright © Secret Simpson 2013 all rights reserved

《精通タイム》あとがき
男にとって、初めての射精=精通は、それぞれいろんなきっかけで体験するものです。
自分でごそごそいじっているうちに気持ちよくなって出してしまった、とか、エッチな夢を見た時に、知らないうちに起こってしまっていた(『Chocolate Time』シリーズの登場人物では、海棠 龍がこのタイプ)、とか……。
こうして男というイキモノは、それ以降、この現象の虜となってしまうわけです。
もちろん、これがないと人類は滅びてしまうわけで、大切な生殖の営みのひとつであることは言うまでもありません。しかし、こと人間に限って言えば、このことが、その強烈な快感のあまり、生殖以外の目的で行われることの方が多いのは周知の事実。
健太郎も修平も、その快感を知ってしまったからには、しばらくはこの行為に執着し続けることでしょう。
さて、このエピソードは、健太郎と修平が初めて出会い、親友同士になるきっかけになった出来事を描いています。彼らはその後、中学を卒業して同じ工業高校に進学。得意だった剣道を修平は続け、高校では剣道部の主将に。健太郎も水泳部でインターハイの県大会レベルまで上達します。
二人とも高三で彼女持ちとなり、結局そのまま結婚します。「セックスって大変そうだ」と言った健太郎も、もうこの時はパートナーの春菜をたっぷり満足させられるようなテクニックを身につけているのですが、それはまだまだ先の話です。
Simpson



































