Twin's Story 10 "Cherry Chocolate Time"
《3 浄化》
『Simpson's Chocolate House』の駐車場で龍は真雪の帰りを待っていた。
「お帰り、真雪」
「龍」真雪は笑顔を作って龍に駆け寄った。龍は真雪の手を取った。「会いたかったよ」
真雪の胸の奥に、針で刺されたような鋭い痛みが走った。
龍はシンプソン家の夕餉に混じっていた。
「龍、きっと溜まってるぞ、マユ」健太郎が言った。「今夜は眠らせてもらえないかもな。わっはっは」
「もう、ケン兄ったら」
「どうやった? 真雪、実習は」
「う、うん。とても役に立つ実習ばっかりだった。いっぱい勉強になったよ。勉強に……」
「そうか」ケネスはテーブルのワイングラスを手に取った。真雪はそんな父親の仕草をちらりと見て、すぐに目を伏せた。母親のマユミがそれに気づいたが、特に何も言わなかった。

「龍、高校は楽しそうだな」健太郎が今度は龍に向かって言った。
「う、うん」
「写真部なんだろ? どんなもの撮ってんだ?」
「風景とか、いろいろだよ」
「日曜日に白鳥を撮りに行ったって言ってたじゃん、龍」真雪が言った。しかし龍と目を合わせなかった。
「え? ああ、そうだったね」龍は言葉少なにそう言った後、箸を置いた。「ごちそうさま。美味しかったです、マユミおばさん」
「そう。良かった。先にお風呂いいわよ」
「うん。じゃあ、先に」
台所に立って、二人で食器を片付けながらマユミは真雪に向かって言った。
「何かあったのね」
「え?」
「雰囲気が変」
「そ、そんなこと……」
「あなた食事の時、一度も龍くんと目を合わせなかったじゃない」
「そ、そうだったっけ?」
「それに龍もな」二人の背後から声がした。残った食器を運んできた健太郎だった。「お前たち、離れている間に、何かあったんだろ?」
真雪は黙っていた。
「そのままにしといちゃいけない気がするな」健太郎が言った。
真雪は一つため息をついた後、小さく言った。「あ、あたし……、実は、」「ちょっと待った!」健太郎が制止した。
「まずは龍と直接話せ」
「ケン兄……」
「俺たちが話を聞くのは、その後」
「いってらっしゃい、龍くんのところに」マユミが優しく真雪の肩に手を置いた。
「う、うん」
◆

真雪の部屋のベッドに、龍は腰掛けていた。いつもシャワーの後は下着一枚の姿だったが、今は上下スウェットを身に着けている。
真雪がドアを開けて入ってきた。龍はちらりと彼女の顔を見たきり、手を後ろについて天井を見上げた。真雪はドアを閉めて、そこに立ちすくんだ。
「おいで、真雪」龍が小さく言った。
「う、うん」
龍は真雪をベッドに横たえた。そしてそっと髪を撫でた。彼は無言で唇を彼女のそれに重ねた。一瞬固く結んだ真雪の唇は異様に乾いていて、龍は思わず舌で舐めた。そして彼女の口の中に舌を差し込んだ。真雪の唇は怯えたように細かく震えていた。龍はキスをやめると、真雪の服を少しためらいながら脱がせた。そしてブラも取り去りショーツ一枚にすると、自分もスウェットを脱ぎ、下着だけの姿になった。
ベッド脇に立ち、龍はその白い真雪の身体を見下ろした。真雪は目と口を固く閉じ、彼から顔を背けていた。
龍は小さくため息をついて、再び静かにベッドに腰掛けた。「今夜はやめとこうか、真雪」
「いやっ!」突然真雪が叫んだ。そして背中を向けていた龍に背後から抱きついた。「抱いて! 龍、あたしを抱いて! 今すぐ! お願い!」
龍は顔を後ろに向けて言った。「真雪……」
「今抱いてくれないと、あたし、永遠に元に戻れない! お願い、あたしを抱いて、浄化して!」
「浄化?!」
その一言で、龍は真雪の身に起こった何かを感じ始めた。
「いったい、何があったんだ? 真雪……」
「抱いて! あたしを抱いて! 龍!」真雪は答えなかった。ただ龍の名を叫び続けた。「龍、お願い、龍、龍! あたしを一人にしないで!」
龍はもう一度真雪を横たえた。「君を一人になんか、しないよ」そして両頬を手で包み込むとそっと唇を重ねた。真雪の息はすでに荒かった。キスで塞いだ龍の口の中に、真雪の熱い息が吹き込まれた。それは大きなため息のようだった。
龍は口を開き、その吐息を吸い込みながら彼女の上唇を舐め、舌を絡ませた。「ああ……うううう……」真雪が今までに発したことのない呻き声を上げた。そしてがたがたと震え始めた。龍は思わず真雪の身体を強く抱きしめた。「安心するんだ、真雪。大丈夫。大丈夫だから……。俺、ここにいるよ」真雪はとっさに龍にしがみつき、さらに大きく肩で息をした。「りゅ……龍……」真雪は苦しそうに喉から絞り出すような声で言った。
龍の口が乳首を捉えた。真雪は仰け反った。龍は念入りに両方の乳首を咥え、舐め、味わった。「ああ……」その度に真雪は熱い吐息を吐いた。その声はいつもの真雪の声だった。
龍は彼女のショーツに手を掛けた。真雪の身体がビクン、と跳ねた。そしてもう一度、ビクビクッ! 真雪の身体が大きく反応した。それも今までに龍が真雪との時間に経験したことのない現象だった。

「真雪、大丈夫?」
「りゅ、龍、早く、早くあたしの中にきて、早くしないと、あたし、あたしっ! 龍、龍、早く!」
焦ったように龍は自分の下着を脱ぎ去った。「真雪、入っていいの?」
「来て、早く、龍、お願い、早く!」真雪は異常に興奮して叫んだ。
龍はサイドテーブルの引き出しから小さなプラスチックの包みを取り出した。すると、真雪が大声で叫んだ。「そんなものいらない! いらないの。あたしの中に、あなたのを出して! お願い、龍!」
「ま、真雪、い、いいの? 中に……」
「ゴムなんか着けないで! 早く中に!」
龍はその大きくなったペニスを、少しためらいながら真雪の谷間に宛がった。すでにそこは豊かに潤い、さらに雫が外へ流れ出すほどになっていた。「ぐっ!」龍は思い切って真雪を貫いた。真雪の身体ががくがくと痙攣し始めた。
「イかせて! 龍! あたしをいっしょに連れて行って! あなたの身体でイかせてっ!」
龍は激しく腰を動かし始めた。「んっ、んっ、んっ!」
はあはあはあはあ! 真雪はまるで過呼吸の症状のように速く激しい息をし始めた。
「ま、真雪っ!」
「イって! 、あたしもイく。あなたと一緒にすぐにイけるから!」
真雪の身体が細かく震え始めた。
「真雪っ!」龍が真雪の身体に覆い被さり、二つの乳房に顔を埋めて、背中を強く抱きしめた。「出るっ! 出、出る、出るっ!」
龍の真雪への想いの全てが、彼の身体の奥深くから真雪の中にほとばしり始めた。
「ああああーっ! 龍! 龍っ!」今までに何度も聞いた真雪の叫び声だった。そして真雪も龍の背中に腕を回し、きつく、きつく抱きしめた。
「んっ! んんっ! 真雪、真雪っ!」龍も腕に力を込めて叫び続ける。
絶頂の息が収まるのを待たずに、真雪はまた龍の背中に回した手に力を込め、激しく叫んだ。「龍! 龍! 龍龍龍龍龍っ! 龍龍龍!」
「真雪?」
真雪の目から涙がどんどん溢れていた。ベッドのシーツがびしょびしょになるぐらいに。それでも、彼女の目からはとめどなく涙が溢れ、とどまることを知らなかった。「龍、龍龍龍龍! 龍、龍龍龍っ!」
龍が真雪から身を離した途端、真雪はベッドにうつ伏せになり、わっと泣き崩れた。そして涙で濡れたシーツに顔をこすりつけながら叫んだ。「ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい! ごめんなさい! ごめんなさい!!」
龍は静かに真雪の側に横たわった。そして背中を優しくさすった。
「真雪、こっちまで辛くなるよ。もう大丈夫だから」
「ごめんなさい、ごめんなさいごめんなさい!」真雪はいつまでも激しくしゃくり上げていた。「龍っ、龍っ、ごめんなさいっ、ごめんなさい! ごめんなさいごめんなさいごめんなさい!」

龍は真雪の身体の下に右手を差し込み、横から抱いた。
「もう、いいよ。わかったよ。一生分のごめんなさいを言うつもり?」
「龍、あたし、あたし……。っ、んっ……」ようやく真雪はしゃくり上げながらも顔を横に起こして龍を見た。
「ひどい顔。俺、いやだな、そんな真雪の顔見るの。切なくなってくる」
真雪の目からまた涙が溢れ始めた。
「よしっ!」龍が上半身を起こした。「シャワー浴びようか。二人で」
「え?」
「そうさ。君がいつか俺を浄化してくれたように、今度は俺が真雪を浄化してあげなきゃ」
二人は裸のまま下着の着替えだけ持って一階への階段を降りた。真雪は龍にしっかりと身体を抱かれ、弱々しい足取りだった。健太郎はドアをわずかに開けて、二人の姿を見た。「え? 二人とも全裸? ま、また鼻血、出るかも……」そして静かにドアを閉めた。「何だか龍の方が大人に見えるな。今日は」
◆
シャワールームに入ると、龍は真雪をバスチェアーに座らせた。そしてシャワーが適温になったことを確認して、静かに首筋からそれを当てた。
「熱くない?」
「うん。丁度いい」
龍はしばらく無言で真雪の全身にシャワーをかけ続けた。
真雪が小さなため息をついた。
龍は手を止めて言った。「いつ見てもきれいな肌だね」
「…………」

龍は手にボディソープを取ると、泡立てて真雪の身体を優しく撫で始めた。
「もう、鼻血出さないから、俺」龍は小さく笑った。そして彼女の背中から手を回し、乳房、腹部、そして愛らしい茂みまで丁寧に泡をたてて洗った。真雪はじっとしていた。
「立って、真雪」
「うん」
真雪を立たせると、龍は座ったまま真雪の白い脚を上から下まで洗った。
「龍、あたし何だか、また感じてきちゃった……」
「それは嬉しい。俺はいつでもいいよ。でも、その前に、」
「え?」
「顔、洗いなよ。もう君の涙は見たくないよ、俺」
「うん。ごめんね、龍」
龍が真雪の身体にまつわりついたソープの泡をシャワーで洗い流している間に、真雪は洗顔用の石けんで自分の顔をごしごしと洗った。
「何て乱暴な洗い方! もう大人なんだから、もっと大人らしく優雅に洗いなよ」龍はそう言ってシャワーのノズルを真雪に手渡した。真雪は少し顔を仰向けて、額からそのシャワーを浴び、ついていた泡を洗い流した。
「よし、すっかりきれいになった。これでいい? 真雪」
「ありがとう、龍。あたし……やっと……」龍の手を握りしめて真雪はようやく笑った。
「俺も洗うから、真雪は温まってなよ」
「洗ってあげようか?」
「君に洗ってもらうのは、俺が『マユ姉』って呼んでた頃までにしといてよ」
「えー、つまんない」
「とにかく、今日はいいよ。そこで見てるだけにして」
「わかった」
真雪は、はあっと一つ大きく息をすると、バスタブの心地よい温かさに身を浸した。
「真雪、」龍は自分の身体を洗いながら真雪の顔を見た。
「なに?」
「さっきはさ、ゴム着けずに君の中に出しちゃったけど、大丈夫なの?」
「うん。心配しないで、龍、今は安全」
「そうか。ごめんね、確かめもしないで」
「でも、あたし、今なら龍に妊娠させてもらってもいい……」
「そ、それはだめだよ」龍は手を止めて慌てて言った。
「わかってる。ごめんね。言ってみたかっただけ。大丈夫」
しばらくの間、バスルームのドアの前に立っていたマユミは、安心したように小さなため息をついて、階段下のキッチンスペースに向かい、キャビネットからココアパウダーを取り出した。
◆

暖炉の前のカーペットに二人は並んで座っていた。ぱちぱちと燃える暖炉の火を見つめ、右手で龍の手を強く握りしめながら、真雪は実習の時の出来事を話し始めた。時々声が詰まり、また涙ぐんだりもしながら、長い時間を掛けてようやく彼女は話し終わった。
大きく一つ、長く震えるため息をついた後、真雪はトレイからホットチョコレートの入ったカップを手に取った。龍の手を握った手を放すことなく。
「マユミおばさんの作るホットチョコレートは、いつ飲んでも最高だね」龍も片手でカップを持ち上げて言った。「真雪、君が今抱いている罪の意識は、半分は俺のせいだ」
「え?」真雪は顔を上げた。
「俺が君に電話をした内容、あまりにも無神経だった。今になって言っても遅いけど……」
真雪は黙ってうつむいた。
「君が俺のことを想う気持ち、俺、過小評価してた」
「ううん、違うの。確かにあたし、龍がカスミ先輩のことを嬉しそうに話すのを聞いて、胸が燃えるように熱くなった。でも、だからといってそれはあたしがあんな人に抱かれる理由になんかならないもの」
「俺、君をもっと愛したい。愛しとけば良かった」
「龍……」
龍はカップをトレイに戻した。
「そうすれば、君を迷わすことなんかなかったのに。そう思うと俺、情けなくなってくる」龍はうつむいた。「君が迷ったのは、お酒のせいなんかじゃなく、間違いなく俺のせい」
真雪もカップを置いた。「でも、」
龍は真雪の言葉を遮り、まっすぐに目を向けて、強い口調で言った。「君だけに苦しみを味わわせるの、俺、いやだ!」
「龍……」
「だから、俺も苦しみたい。真雪と一緒に苦しみたいよ……」
龍の目に涙が溜まっているのを見た真雪は、彼の背中に腕を回し、そっと抱きしめ、右頬を龍の首筋に当てた。龍の瞳からこぼれた雫が真雪の耳に落ちてつっと流れた。
「龍……。ありがとう……」
「そうじゃない、って思っても、そういうことにしておいてよ、真雪。その方が俺も、救われる……」
真雪は手を龍の両肩に置き直して言った。「……あたし、もっと強くなりたい」
龍は顔を上げて真雪の目を見た。
「信じる力を持ちたい。もっと」
「俺ももっと信じたい。真雪のことも自分の気持ちも」
真雪の左手が龍の頬に触れた。「真雪……」龍が小さく言った。
真雪は彼の唇に自分のそれを重ねた。龍は真雪の背中に腕を回し、強く抱きしめながら、彼女の口を吸った。真雪も龍の唇を強く吸った。そして二人はそのままそこに倒れ込んだ。
下になった龍が真雪の耳元で囁いた。「ここでやるの? 叔父さんや叔母さんに聞こえちゃうよ、俺たちの声や音」
「別にいいんじゃない? 秘密にするようなことでもないんだし」
「えー、何だか恥ずかしいよ」龍は赤くなった。
「やった! あたしの龍に戻った! 年下の龍に」真雪は小さく言って龍の背中をぎゅっと抱きしめた。
龍が真雪にまた囁いた。「ねえねえ、やっぱり部屋に行こうよ」
真雪は少し考えた。そして言った。「そうだね」
◆
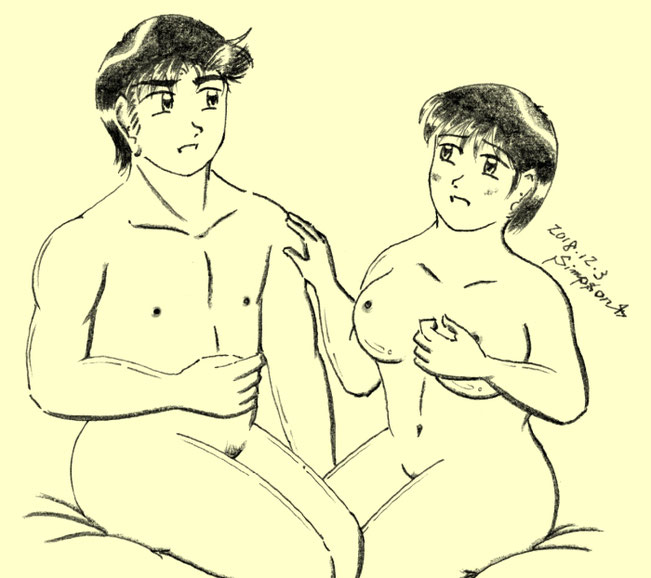
真雪の部屋で下着姿になった二人は、ベッドに並んで座っていた。
「龍、あたしのわがままを聞いてくれる?」
「え?」
「龍はいやだ、って言うと思う。きっと」
「どうしたの?」
真雪は顔を上げて龍を見た。少し目が潤んでいる。「でも、譲れないことなんだ。これだけは……」
龍は少し間を置いて、優しく言った。「君がそう思っていることを、今は拒否できない。そんな気がする」彼は真雪の肩にそっと手を置いた。「言って。君のわがまま」
「うん」真雪はこくんとうなずいた。
「あたし、あたしね、」真雪はためらいがちに言った。「龍が高まって出すものを、全部、飲んでしまいたい」
「ええっ?!」
「あたし、それを龍が嫌がるから、今までお願いしなかったけど、どうしてもやりたい。今」
「ど、どうしてそんな、」
「聞きたくないかも知れないけど、我慢して聞いて、龍」
龍はうなずいた。
「あたし、あの人に無理矢理口に出された。もちろんあたしはそれを望んでいたわけじゃない。お酒のせいにするのは卑怯だと思うけど、グランマが言った通り、あたし、あの時『もう、どうでもいい』って思ってた。自暴自棄になってた気がする」
「…………」
「気持ちは強烈に拒絶してたのに、身体が何かを求めてた、そんな感じ」真雪はうつむいた。「いやだった、とてもいやだったのに……」
「真雪、俺、君のその時の状態を想像すると、胸が破裂しそうになる。その時の、その場所にタイムスリップして真雪を奪い返したい」
「あなたのものを一度も口にしたことないのに、あんな人のものをこの口で受け止めたことが、あたしどうしても許せなくて……」
「飲んだのか? 真雪!」龍が少し強い口調で言った。
「飲まない! 飲むわけないよ! あたし、全部吐き出した。吐き出したよ、ちゃんと……」真雪の目からまた涙が溢れ始めた。「だから、あたし、龍のものを飲みたい。あなたのものだけを……。最初から最後まで、あなたがあたしのことを想いながらイって出してくれるものを、全部」

「真雪……」
「薬なの。あたしが正常な心と身体に戻るための薬なの。わかって、龍。お願い……」
龍はそっと真雪の背中に腕を回し、抱いた。龍の耳元ですすり泣く真雪の声だけが残った。そしてそれに続く長い沈黙があった。
一つため息をついて、龍は真雪の髪を優しく撫で、親指の腹でその涙を拭った。「ごめん、真雪、君を責めるような言い方しちゃって……」
「龍、龍……龍龍……」
「今は君が一番辛い気持ちでいるのにね。俺が過ぎたことにむやみに嫉妬している場合じゃないのにね」
真雪は龍の身体をきつく抱きしめた。「龍、もうどこにも行かないから。あたし、あなたが見えない、手の届かないところになんか、もう二度と行かないから」真雪の声はずっと震えていた。「許して……許して、龍」
「よしっ」龍が真雪の背中をぽんと叩いた。「じゃあ、やって。真雪。薬を飲ませてあげるよ」
「ありがとう、龍」真雪は涙を拭いた。「ごめんね。わがまま言って」
「普通のオトコなら喜んでしてもらうところなんだろうけどね。やっぱり俺は苦手だよ」龍は頭を掻いた。「だって、美味しくもないものだって言うだろ? 真雪がかわいそうだ」
「いや。飲む。飲ませて。龍のなら、ぜったい美味しいはず。お酒なんかよりずっと」真雪は少しムキなって言った。
「わかったわかった」龍は照れたように笑った。そして続けた。「どうしたらいい?」
「立ったままでいいよ。あたしがあなたを口で刺激してイかせたら、そのまま飲み込むから」
「うーん……」龍は考えた。「俺、とっさに逃げ出しちゃうかもしんない」
「えー、だめだよ、そんなの」
「だって、俺だけイくの、いやだよ。真雪も一緒にイかせたい。……そうだ!」
「え?」
「お互いに口で刺激し合おうよ。それがいい!」龍はにっこりと笑った。
「龍……。龍って本当に優しいね……」
「それならできそうな気がする」
「じゃあ、あたしが下になる」
「え? 俺が下でしょ」
「だめ。それじゃ全部飲めない。溢れちゃう」
「そ、それはそうか……」
真雪は下着のままベッドに仰向けになった。龍も下着をつけたまま反対向きに真雪に覆い被さった。「ああ、キスができない……」
「ふふ……後でいっぱいして」真雪は目の前の龍の黒い下着をためらわず脱がせた。大きくなった龍自身が目の前に飛び出した。真雪はそれを大切そうに両手で包み込んだ。その温かさが最高に心地よかった。龍も真雪の白いショーツを脱がせた。そしてそっと舌で茂みをかき分け、クリトリスを吸った。「ああ……」真雪が喘いだ。
真雪はおもむろに龍のものを咥え込んだ。龍は体重をかけないように慎重にペニスの位置を調整した。深すぎず、浅すぎず、真雪が口を自由に動かせるように……。その間も真雪の温かい口の感触が龍の敏感な場所を刺激し続けていた。
龍の身体が熱くなり始めた。「ああああ、真雪、むぐっ!」興奮が高まってきた龍は、真雪の両脚を抱え込み、股間に顔を深く埋めて谷間とクリトリスを交互に激しく舐め始めた。「んん、んんっ! んんっ!」真雪は龍のペニスを咥えたまま呻き始めた。そしてだんだんと口の動きを速くした。「んっ! んっ! んっ!」龍の口の動きも激しくなってきた。
真雪の身体が細かく震え始めた。それが彼女が頂上間近にいる証拠であることを龍は知っていた。龍はことさら激しく真雪の秘部を愛した。いつしか中からわき出る泉と龍の唾液で、シーツにしたたり落ちるほどにそこは濡れていた。
「んんーっ!」真雪が突然激しく呻き、龍のペニスを強く吸い込んだ。それと同時に龍の身体の中の熱いマグマも激しく噴出し始めた。
「ああああああ!」思わず口を真雪の秘部から離して龍は叫んだ。
「んんー! んんんーっ!」真雪が悲鳴に近い高い声で、ペニスを咥えたまま叫んだ。
激しく龍の身体の奥から噴き出す精液が、真雪の口の中に何度も何度も勢いよく打ち付けられた。真雪はその強力な刺激と沸騰した熱さ、そして心地よい苦さに酔いしれていた。
彼女は龍の放出の度にそれを飲み込んでいった。
射精の勢いが弱まってきたのを察知した真雪は、龍のものを咥えたまま口の中に残った液を何度も喉に、体内に送り込んだ。「ああ、あああああ!」その度に過度に敏感になっていた龍のペニスは真雪の舌と上あごに刺激され、彼は身体を大きく揺り動かしながらもだえ続けた。「ああ、ま、真雪、ああああああ!」
真雪はぬるぬるになった龍のペニスを舌で舐め、唇で吸った。一滴も残さないように彼女は龍のペニスを舐め、また深く咥え込んだ。「う、うううっ、ま、真雪、ま、また俺、」龍の身体ががくがくと激しく震え始めた。
「で、出る! 出るっ! イくっ!」真雪の口の中に再び龍の精液が放出され始めた。真雪は夢見心地でそれを味わい、飲み込み続けた。「うああああああっ!」龍は叫び続けた。

龍は汗だくになり、大きく身体を波打たせて喘ぎ続けていた。龍の身体の中から出されたものを完全に飲み下し、舐め取り、真雪の口がようやく龍のペニスを解放した。その途端、龍は身体を起こし、真雪の身体を抱き起こした。
そして身体に腕を回し、きつく抱きすくめ、ベッドに押し倒した。「真雪! 真雪っ! ごめん!」そのまま龍は上になり、真雪の口を自分の口で塞ぎ、吸った。舌を差し込み、口の中をかき回した。歯も、歯茎も、舌も、何度も何度も彼は舐め回した。「んんんん……」真雪はその度に小さく呻いた。真雪もいつしか龍の背中に腕を回し、きつく、簡単には離れないように抱きしめていた。
二人の息はまだ荒かった。そして全身がじっとりと汗ばんでいた。
「やっぱり、だめだ、俺……」
「どうして謝るの?」
「だから、強烈な罪悪感があるんだってば」
「よくわからない……」
「なんか、嫌がる真雪をレイプしてるみたいで……」
「大好きな人がイく時、あたしの身体の中に出すことを嫌がるわけないよ」
「でも……」
「ありがとう、龍。ほんとに優しい人」真雪は微笑んだ。「でも、そう言いながら今日は何だかすごく長くイってたみたい」
「俺、生まれて初めて二度続けてイった」
「そうなの?」
「自分でもびっくりしたよ」
「でも、龍はたいてい三、四回はイくじゃない。一晩に」
「いや、いつもはさ、真雪と話してたり、触り合ってたりして、また興奮が高まって、っていうパターンなんだ。でも今日は違ってた。イったあと、終わった、と思う間もなく、また押し寄せてきたんだ」
「龍も二回、イってくれたんだ。あたし、嬉しい」
「ごめん、いやだっただろ? いつまでも咥えてなくちゃいけなくて」
「ううん。龍があたしのためにたくさん出してくれてるって、とっても嬉しかった」
「本当にごめん、真雪」
「まだ謝ってる。でも龍が思う程、あたしこれ嫌いじゃないな」
「うがいしに下に行こうよ」龍は上半身を起こした。
「えー、いやだよ」真雪は横になったまま首を振った。
「気持ち悪いだろ? 口の中」
「全然。ずっと余韻を味わっていたいぐらい」
「そ、そうなの?」
「すっごく美味しかったもん。嘘じゃないよ」
「美味しいわけないじゃん、あんなの」
「味、とかじゃなくて、何て言うかな、口の中に当たる刺激とか、心地よい温かさとか、」
「温かい? それってとっても気持ち悪いと俺は思うんだけど……」
「だって、愛する人の体温を直に口の中に感じることができるんだよ。心地よいに決まってるよ」
「そ、そうなんだ……。で、どんな味なの?」
「味はねー、ちょっと苦い」
「うわ、それはつらい。さすがにいやだよね」
「それが不思議とまずいとは思わなかったんだよ」
「えー、苦けりゃまずいでしょ、いくらなんでも」
「あたし、今ならビールだってワインだって飲めるかもしんない」
「何だよそれ」龍は呆れて笑った。
「あたしもう大人だからね。ビールの味ぐらいわかるよ」真雪も笑った。
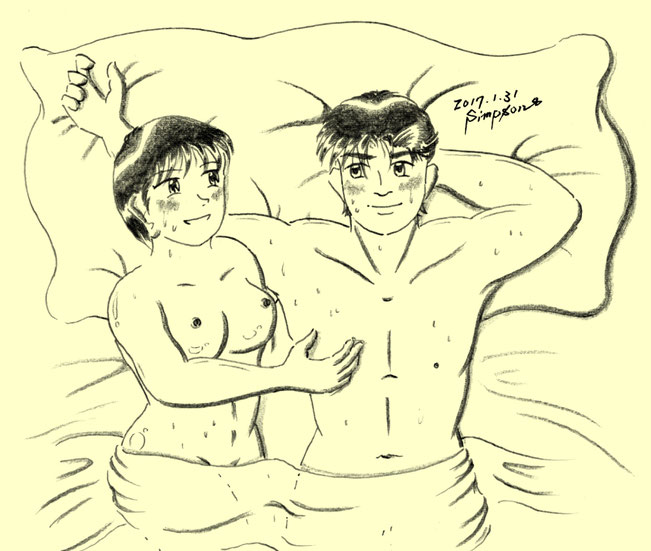
龍は再び真雪の傍らに横たわった。そして申し訳なさそうに上目遣いで言った。「真雪はイけた?」
「イけたイけた。もうすごいよ」
「え? そんなに?」
「龍だってもうわかってるでしょ、あたしがイく瞬間」
「そりゃあね」
「龍のものを咥えて、口の中に出されて、大切なところは龍が口で刺激してくれて……。いつものセックスと全然変わらなかった。上と下が逆になっただけ、って感じだよ」
「なるほど……」龍は妙に感心したようにうなずいた。「でも、もうしないからね。当分」
「わかってる。ごめんね、いやなこと、無理させちゃって」
「うん。そうだよ、いやだ。やっぱり」龍が威勢よく言った。
「なに思いついたように……」
「今日の方法だと、できないことがある」
「できないこと?」
「そう。キスができないこと。それに真雪のおっぱいがいじれないこと」
真雪は破顔一笑した。「そうか。そうだったね」
「この『サラダ』がないと、やっぱり物足りないよ、俺」龍はそう言いながら真雪の二つの乳房の間に顔を埋め、頬を何度も擦りつけた。
「俺の真雪……」
「龍ったら……」真雪は龍の頭を愛しそうに撫でた。
しばらくの沈黙を二人は満ち足りた気持ちで味わった。
「龍、」
「うん?」
「あたし、早くあなたと一緒にお酒が飲みたい」
「どうして?」
「あなたで頭をいっぱいにして、あなたで身体を満たされて、あたし、夢見心地であなたに抱かれたい」
「俺さ、」龍が慎重に言葉を選びながら言った。「真雪はもう、お酒なんか飲まない、って言い出すかと思ってた」
「あんなお酒はもう二度と飲まない。でも、自分がお酒でどうなるかわかったから、もう間違わないよ。あたし」
「そうか。そうだよね」龍は真雪の髪を指で梳いた。
「龍、」
「なに?」
「あたしの手、ずっと握っててね」
「放すわけがないよ。もう二度と」龍は真雪の指に自分の五本の指を絡ませた。「絶対に」
「好きだよ、龍。……愛してる」
「俺も。愛してる、真雪」
真雪はそっと目を閉じた。龍は彼女の唇に自分の唇をそっと押し当てた。





































