Twin's Story 7 "Milk Chocolate Time"
-第1章 2《浄化》-
明くる日の朝。
「龍、何してんだ! 遅刻するぞ!」ミカが階段の下から叫んだ。
「どうしたんだ?」ケンジがミカの横に立った。「珍しいな、龍が寝坊するなんて」
しばらくして龍が制服に着替えて階段を力無く降りてきた。
「どうした? 具合でも悪いのか? 龍」ケンジが言った。
「別に」龍は言葉少なに食卓に向かい、黙ってトーストをかじり始めた。
いつもなら黙れ、と言いたくなるほど食事の時にはしゃべりつづける龍が、今朝は一言もしゃべらず、無表情のまま食事を済ませた。ケンジとミカは思わず顔を見合わせた。
「いつもより遅いから、急いで行きな。でも焦って車とぶつかるなよ。今ならまだ雨も降ってない」ミカが玄関に立って言った。
「うん」龍はシューズを片方履いた。そしてもう一方のシューズを手に取った時、いきなり口を押さえて履いていた片方のシューズを脱ぎ捨て、トイレに駆け込んだ。
「龍!」ミカが叫んだ。
トイレの中から、龍の激しく嘔吐する音が聞こえた。
「どうした?!」ケンジもやってきた。
「龍が、」ミカがそう言いかけた時、トイレのドアが開き、龍が二階の部屋に駆け上がっていった。
ミカとケンジは後を追った。

「龍!」ベッドに制服のまま倒れ込んだ龍にミカは近づいて言った。「どうした? 腹が痛いのか?」
龍は黙っていた。ミカは龍の頬をそっと撫でた。すると龍はいきなりその手を振り払い叫んだ。「僕に触るな!」
「龍! いったい……」
「僕の汚いカラダに触らないで!」
ミカは振り向いてケンジを見た。ケンジは目配せをした。ミカは龍の部屋から出た。
「もしかしたら、」ミカが口を開いた。「いじめかもしれない……」
「いじめ?」ケンジが言った。
「あの子の頬に小さな傷がある。昨日穿いてたズボンに焦げ跡のような穴が開いてる。シャツのボタンが一つちぎれてる」
「昨日?」
「そう。昨日」
「そう言えば、龍、昨日の晩も様子がおかしかったな」
「ずぶ濡れで帰ってきてから、ずっとああだった。あたしもおかしいとは思ってた」
「これまでズボンやシャツに変わったこと、なかったのか?」
「一度もなかったね」
「いじめというより、誰かに暴行を受けた可能性も……」
「そうだね、状況を見ると、そうかもしれない」
その日は、結局龍は学校を休んだ。ミカは担任には腹痛が原因だと伝えた。その時、昨日龍に変わったことはなかったか、と訊いてみた。しかし担任は特に思い当たることはない、と返すだけだった。
ミカはとにかく龍の口から事情を聞きたかった。しかし時が経っても龍本人がそのことについて口を開くことはなかった。何かが彼の言葉を頑なに封印している。ミカは居ても立ってもいられなかったが、朝からケンジに焦りは禁物と言われていたこともあり、龍をいたずらに刺激することを我慢した。
◆

「先生、お久しぶりです」
健太郎とその友人の天道修平は自分が通っていた中学校に遊びに行った。今、中二の龍が通っている学校だ。
「よお、健太郎、それに修平、久しぶり。元気そうだな」
「ありがとうございます」
「二人とも立派になったな。で、高校総体はどうだった?」
「ま、余裕っすね」修平が言った。
「お前の剣の腕前なら軽くブロック大会まで行けるんだろ?」
「お陰様で」
「健太郎は?」
「俺もいちおう、ブロック大会には行けることに」
「そうか、それは良かった」
「龍はちゃんと勉強してますか?」健太郎が口を開いた。
「ああ、お前いとこだったな、龍の。まじめにやってるよ。礼儀正しいし、水泳もがんばってる。でも今日は休んでるみたいだな」
「え?」
「腹痛で欠席、っていう連絡があったみたいだぞ」
「腹痛?」修平が言った。
「珍しくないか? あの子が病気で休むなんて」
「そうですね、確かに……」健太郎の表情がにわかに曇った。
「そうそう、龍は理科が苦手だって言って最近沼口先生に質問に行ってたみたいだぞ。お前からも一言あいさつしとけよ」
「わ、わかりました」
健太郎は元担任の教師のもとを離れ、窓際に座ってパソコンをいじっている沼口の所へ足を運んだ。
「沼口先生、お久しぶりです」
「おお、シンプソン、それに天道じゃないか。元気だったか?」
「はい。お陰様で。それより龍のやつが先生にいろいろとお世話になっちゃって」
「え?」沼口は一瞬動揺したように目をしばたたかせた。「あ、ああ。放課後に勉強をな、ちょっとだけ教えてやっただけだ。大したことじゃない」そして健太郎たちから目をそらした。
健太郎の心にふと不吉な想像が浮かび上がった。それはちょっと現実離れした妄想にも似たものだった。
健太郎たちは沼口とそれ以上言葉を交わすことなく、職員室を出た。「失礼します」
「どうした? ケンタ」修平が学校を出たところで健太郎に訊ねた。「何慌ててんだ?」
「え? あ、いや、何でもない」健太郎は答えて自転車に跨がった。
空はどんよりと曇り、二人の頬をひんやりした風が吹き過ぎた。
「雨が降り出しそうだ。早く帰ろう」
「ああ」修平も自転車のペダルに足を掛けた。
◆
「マユ、ちょっと話があるんだ」
「どうしたの? ケン兄」
その日の夕方、健太郎は真雪の部屋を訪ねた。
「龍が今日、学校を休んだらしい」
「え? 龍くんが?」
「そう。腹痛だって」
「ほんとに? 心配だね」
「俺の予感が当たっていれば、あいつの欠席の理由は腹痛じゃない」
「え? どういうこと?」
「さっきミカさんに電話したら、昨日から龍の様子がおかしいらしいんだ」
「様子がおかしい? どんな風に?」
「俺と一緒に龍に会いに行こう」
「わかった。すぐ支度するね」
健太郎と真雪は、厚い雲のせいで薄暗くなった中を海棠家目指して小走りで駆けていった。
「よお、健太郎に真雪、よく来てくれた」
「龍くんの具合はどう? ケンジおじ」
「まだ引きこもってる」
「何か話した?」
「いや、何も」
「そう……」真雪は苦しそうな顔をした。「おじさん、あたし龍くんの部屋に行ってもいい?」
「もちろんだ。真雪になら何か胸の内を明かすかもしれない」
「行ってやって、真雪」ミカもやってきて懇願するように言った。
「じゃあお邪魔するね」真雪はそう言って玄関で靴を脱ぎ、二階に上がっていった。
「最近の龍の様子を教えてくれないかな、ミカさん」健太郎が真剣な顔で言った。
「何か思い当たることがあるんだね? 健太郎」
「うん」
リビングのテーブルをはさんでミカとケンジ、そして健太郎は向かい合った。
「突然のことにあたしたちもびっくりしてるんだ」ミカがため息混じりに言った。
「朝から学校に行きたくなさそうだったってこと?」
「それどころじゃないんだ。片方の靴を履いたところで、あいつトイレに駆け込んで食べた物を全部戻したんだ」
「拒絶反応だ。典型的な」ケンジが言った。
「学校で何かあった、ってことだね」
「おそらくはな」
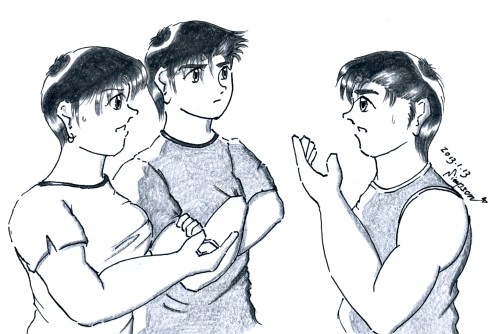
「俺、今日中学校にあいさつに行ったんだけど、何か怪しいんだ」
「怪しい?」
「そう。龍ってさ、昨日と一昨日、理科の沼口っていう教師に勉強を教えてもらった、っていう話だけど」
「そうらしいな」
「沼口先生って、真雪の中三の時の担任の先生なんでしょ?」ミカが言った。
「そう」
「とっても親切でいい先生だ、って真雪言ってたけど」
健太郎はうつむいて、一つため息をついた後、口を開いた。「証拠があるわけじゃないんだけど……」
「何かあるの?」
「沼口先生には、変な噂があるんだ」
「噂?」
「そう。男子生徒を標的にして、性欲のはけ口にしている、っていう……」
「な、何だって?!」ケンジが大声を出した。
「龍がその犠牲になった?」ミカも口を押さえて目を見開いた。
「龍のズボンに穴が開いてた、って言ってたよね」
「ああ。何か摩擦で繊維が溶けたようでもあり、でもよくわからない」
「見せてくれる? ミカさん」
ミカは龍のズボンを持って来た。「洗濯しちゃったけど、わかる? 健太郎」
その学生ズボンを受け取り、しばらくその穴を調べていた健太郎は顔を上げて言った。「これは酸性の水溶液による腐食だね」
「酸性の?」
「そう。他の部分に擦った跡やひっかき傷がないし、ここだけ丸く穴が開いている。俺の高校での実験で開いた白衣の穴にそっくりだ。ほぼ間違いないと思うよ」
「だとしたら、いよいよ怪しいな、その理科の教師」
「龍の身体を調べてみた?」
ミカはまたため息をついた。「やつは自分のカラダをあたしたちに触らせたがらないんだ。ひどく拒絶してさ」
「間違いなさそうだな」ケンジがつぶやいた。
「少し急いだ方がよさそうだね、ケンジおじ」
「龍くん、」真雪は龍の部屋のドアをノックした。龍は飛び起きた。
「龍くん、開けて、真雪だよ」もう一度彼女はドアを叩いた。
「マユ姉、入って来ないで!」龍は大声で言った。「もう僕に近づかないで」そして龍はまたベッドに突っ伏した。
「何があったの? ねえ、あたしに話して」真雪はドア越しに龍に呼びかけた。
「…………」
「あなたがドアを開けてくれるまで、あたしここにいるから」
「マユ姉……」龍は涙ぐんだ。そして覚悟を決めたようにベッドから降り、静かにドアを開けた。「鍵なんて掛かってないのに……」龍は真雪の目を見ることなくうつむいたままそう言った。
「ありがとう、龍くん」真雪は部屋に入ってドアを閉めた。
龍の部屋の壁には、たくさんの写真が掛けられている。その中で一番大きな額に納められているのは、シンチョコの店をバックに真雪が微笑んでいる写真だった。そう、かつてシンチョコのパンフレットに使われたこともあるあの写真だ。そしてそれは龍が自分のカメラで撮影したものだった。

龍は自分のベッドの端に腰を下ろした。ずっとうつむいていて、決して真雪と顔を合わせなかった。真雪は床に膝を抱えて座った。
「龍くん、あたしね、あなたが本気で好き」
「……」
「冗談で付き合いたい、って言ったわけじゃないんだよ」
「……」龍はかすかにうなずいた。
「あなたもあたしのことを好きだって、ずいぶん前から気づいてた。でもそれって思い過ごしだったのかな……」
龍は慌てて顔を上げた。「思い過ごしじゃないよ。ぼ、僕、マユ姉のことが好き。いとことしてじゃなくて、女のコとして」
「良かった……」真雪は微笑んだ。龍はまたうつむいた。
「でも、もう、僕の身体、汚れきってしまった。マユ姉に触れたくても触れられないよ」
「え? どういうこと?」
「マユ姉まで汚れちゃうよ。僕に触ったりしたら……」龍は目に滲んだ涙を乱暴に右腕で拭った。
「何があったか、話してよ。龍くん」
「…………」
その時、部屋のドアがノックされた。「おい、龍、開けるぞ」
「ケン兄……」
ドアから顔だけ出して、健太郎は言った。「俺んちに来いよ。龍」
「え?」
「こんなところに一人でこもってたって、ますます落ち込むだけだ。マユ、いいだろ?」
「そうだね、そうしよう。龍くん行こ」真雪は立ち上がり、龍の手を取った。しかし龍はとっさにその手を振り払った。真雪はそれ以上龍の手を取ろうとはしなかった。しばらくして龍はようやく立ち上がった。少し足下がふらついてよろめいた。
◆
「龍、よう来たな。早よ上がり」店の前で植え込みの花の手入れをしていたケネスが微笑みながら言った。
「お邪魔します……」龍は相変わらずうつむいたままだった。
「どこだったら落ち着く? 龍くん」
「ここでいい……」
「ここは外だ。それに雨も降りそうだ。俺の部屋に行くか」
健太郎は先に立って歩き、離れのドアを開けた。「入れよ、龍」
龍は少しの間ドアの前に佇んでいたが、真雪に促されてしぶしぶ部屋に上がっていった。
健太郎の部屋の床に龍は膝を抱えて座った。
健太郎が言った。「今日は泊まっていけよ。どうせ明日土曜日だし。いつも土曜日は部活じゃなくてスイミングスクールだろ?」
「……」
「ケンジおじやミカさんとは顔を合わせづらいだろ? 今のままじゃ」
「う、うん……」
「でもな、お前が悪いんじゃない。悪いのは沼口。そうだろ?」
「えっ!」龍は驚いて健太郎の顔を見た。
「やっぱりそうか。悪い予感が当たっちまったな……」
真雪がドアを開けて入ってきた。「龍くん、喉渇いたでしょ」
真雪は3つのグラスにパイナップルジュースをつぎ分けた。「はい。思い出のパイナップルジュース」真雪は微笑みながら一つのグラスを龍に手渡した。
「あ、ありがとう、マユ姉」龍はそれを受け取ったが、一口飲んだだけで、あとは手のひらで大切そうにそのグラスを包み込んだ。
「話によっちゃ、すぐに行動する必要があるんだ、龍、話してくれ、俺たちに。何があったのか、何もかも」
龍は健太郎と真雪の顔を交互に見て、少し怯えたようにようやく重い口を開き始めた。

「な! 何てやつだ!」龍の話を聞き終わった健太郎は激怒して大声を出した。「許せない!」
「そ、そんな教師だったなんて!」真雪も声を震わせた。
「もう僕、僕……」龍はぽろぽろと涙をこぼし始めた。手に持ったグラスの中にその数滴が落ちてかすかな音を立てた。「悔しくて、悔しくて……」
「わかる。わかるよ、龍」健太郎は龍の肩に手を置いた。
「僕、何もできなかった! あいつに、あいつに……、っ! ……っ!」龍は肩を震わせ、声を殺して泣いた。
「その胸の火傷の跡、ちょっと見せて」真雪が言って龍の肩に手を掛けた。
「マユ姉、さ、触っちゃだめだ。俺の身体、汚れまくってる!」龍は後ずさった。
「いいかげんにしろ!」健太郎が叫んだ。
「龍くん、」真雪が優しく言った。「もし汚れてるんだったら、あたしが浄化してあげるよ」
「えっ?!」
「そうしてもらえ、龍」健太郎は龍の肩をもう一度軽く叩いた。「マユ、龍を頼むぞ。俺、これからミカさんたちに報告してくる」
「えっ?! か、母さんたちに?」
「そう。親が被害届を出す必要があるからな。大丈夫だ、龍、お前には何の落ち度もないし、お前自身が恥じることもない」そして付け加えた。「自分の心まで拘束されるな」
「ケン兄……」
「いいから俺たちに任せろ」
健太郎は立ち上がり、部屋を出て行った。
「あたしの部屋に行こうか、龍くん」真雪が龍の手を取った。今度は龍は真雪の手を振り払いはしなかった。
真雪は龍を自分のベッドに座らせた。
龍はドアの横に貼ってある小さなポスターをちらりと見た。その横にはハワイで撮ったプールサイドでの健太郎、真雪、そして龍がピースサインをして写っている写真も貼られていた。
「龍くん、本当に男らしくなったね。ケンジおじさんにも似てきたし」
「マ、マユ姉……」龍は赤くなって身体をこわばらせていた。
「あたしね、あなたに抱かれたいって、今思ってる」
「えっ?!」
「時々想像しちゃうんだよね。あなたに抱かれるの」
「だっ、だっ、抱かれる?」
「龍くん、あたしとセックスしたい?」
「え? あ、あの、そ、それは……」
「もう龍くんぐらいになれば女のコとセックスしたいって思うんじゃない?」
「そ、そりゃあ、そそ、そうだけど……」

真雪は静かに龍の両肩に自分の両手を置き、そっと唇同士を重ね合わせた。龍はびっくりして目と唇をぎゅっと固く閉じた。
一度口を離した真雪は、もう一度、今度は龍の両頬に手をあてて、唇を近づけた。するととっさに龍は目を開けて真っ赤になって叫んだ。「マ、マユ姉、僕、汗かいてる。シャワー借りていい?」
龍から手を離した真雪はその手を腰に当てて笑った。「いいよ」
「ごめん。マユ姉」
「着替え、持って来てないよね」
「あ、」
「あたしのショーツ、穿く?」
「ええっ?!」
「って冗談だよ。仕方ない、ケン兄のを借りよう」真雪はそう言って、勝手に健太郎の部屋に入り、勝手に青いビキニタイプの下着と黒いTシャツを持ち出して龍に手渡した。「はい。これでいい? ビキニなんて穿く?」
「う、うん。僕も、いつもこんなのしか穿かない」
「そう。ケン兄と好み、同じなんだね」
「いいの? ケン兄に怒られない?」
「大丈夫。あたしがちゃんと断っとくから」
「ありがとう、マユ姉」
「いつもみたいにバスタオルも好きに使ってね。遠慮しないで」
「ごめん。ありがとう」
龍は部屋を出て階段を降りていった。
◆
龍は階下にある広いシャワールームに入っていった。そして彼は着衣を脱ぎ去り、自分の身体を脱衣所の大きな鏡に映してみた。左の乳首のすぐ下に赤い小さな火傷の跡がある。龍は右手の人差し指でそれにそっと触れてみた。少しがさがさとした感触だった。ほんの少しの痛みが残っていた。
龍はシャワーを全開にして自分の裸体に浴びせかけた。そして身体中を何度もボディソープで洗った。ごしごしと何かを擦り落とすように、皮膚が赤くなるまでタオルで乱暴に洗った。そして特に入念に自分の秘部を洗い清めた。まだ生えそろっていない陰毛も、石けんを泡立てて何度も何度も洗い流した。
ひとしきり身体についた石けんを洗い流してしまうと、龍は少し安心したように一つため息をついて、広いバスタブに身を沈めた。その時、シャワールームの外のドアが開く音がした。龍は慌てて叫んだ。「は、入ってます!」
「知ってるよ」真雪の声だった。
「マ、マユ姉!」
「あたしも入るね」
「ええっ!」龍はびっくりして湯に首まで浸った。「そ、そんな、だ、だめだよ、マユ姉」
「何で? ちっちゃい頃はよく一緒にお風呂に入ってたじゃない」
「だ、だってもうちっちゃくなんかないし……」
「もう脱いじゃったもん」全裸になった真雪はあっさりと浴室の扉を開けて中に入ってきた。
「マユ姉っ!」龍は全身真っ赤になって叫んだ。
「もう身体洗った?」
「あ、洗った。もう洗っちゃった。だ、だから先に上がるね、マユ姉」龍は股間を両手で押さえてバスタブの中で立ち上がり、慌てふためいた。
「じゃあさ、あたしの身体を洗ってくれないかな」
ぶっ! 龍は自分の鼻を押さえた。指の隙間から血が垂れ始めた。「マユ姉ー」
「教科書通りの反応だね」真雪は落ち着いて脱衣室からティッシュを一枚取ってきて龍に渡した。
「龍くん、洗って。あたしの身体」
龍は覚悟を決めて、鼻にティッシュを詰めたまま、真雪の背後に座った。そして手にたっぷりとボディソープを取ると、恐る恐る彼女の背中に塗りつけた。
「しっかり泡立ててねー」真雪も自分でソープを腕や脚に塗り広げ始めた。
龍は恐る恐る真雪の背中を撫でてみた。ぬるぬるとした感触が龍の身体を熱くした。真雪は自分の両腕を持ち上げた。「おっぱい、触ってみる?」
「お、おっぱい? ……」龍の動きが止まった。
「ほら、固まってないで、」真雪は龍の両手をそれぞれの手で取って、彼の大きな手のひらを自分の乳房にあてがった。「しっかり洗ってね」そして真雪は彼の手首を持ったまま上下に動かした。
「マユ姉ー」龍が情けない声を上げた。「鼻血が止まらないよー」
「あ、ああん、龍くん、いい気持ち」真雪は目を閉じ、喘ぎ始めた。そして彼の右手を取り、今度は自分の秘部に誘導した。「ここも、洗ってくれる?」
「ええっ?!」龍は思わず大声を出した。
「早く」
龍はぎこちなく、手のひらを使って申し訳程度に彼女の陰毛を泡立ててさすった。龍がそうやって手を動かす度に、真雪は自分のヒップに堅いものが当たるのを感じていた。

真雪は突然後ろを向いた。龍と向き合った真雪は出し抜けに彼のペニスを握った。
「あっ!」龍は呻いた。
「すごい! もうこんなになってる。男のコってすごいね」
「マユ姉! だ、だめ、僕、もう、」
ソープでぬるぬるになった手で龍のペニスを包み込み、真雪は前後に動かし始めた。
「で、出ちゃうっ! ああ、マユ姉、マユ姉ーっ!」びゅるるっ! びゅくっ! びゅくっ! びゅくびゅくびゅく……。あっという間に龍は射精をしてしまった。
肩で大きく息をしている龍の身体に、真雪はシャワーの湯を掛けた。「いっぱい出せるんだね。もうすっかり大人の身体じゃん」
「マ、マユ姉、僕、恥ずかしいよ……」
「どうして? 男のコでしょ? 普通じゃない」
「す、好きな人にイくところ見られるのって、すごく……」
「あたしは嬉しいな、好きな人に見られるの。たぶん」
「え?」
「その人と一緒に気持ちよくなれれば、きっともっと嬉しいよ、」
「マユ姉……」
「あたしの部屋に行こうよ。龍くん」
真雪のベッドに腰掛けて、龍は身体をこわばらせ、赤くなってうつむいていた。健太郎から借りた青いビキニショーツだけを身につけている。
「龍くんって、身体はもう大人みたいだけど、そのシャイなところはまだ子どもだね。あ、大人になってもシャイなままかな。ケンジおじの息子だもんね」
真雪は白いブラとショーツの下着姿で立っていた。
「マ、マユ姉、ぼ、僕、は、初めてで、あの……」
「あたしも初めてだよ。龍くんが」
「え?」龍は顔を上げた。
「初めてだよ」
「本当に?」
「うん。そんな風に見えない?」
「だ、だって、すごく、なんかこう、せ、積極的じゃん」
「その人のことをちっちゃい頃から知っているから安心なのと、その人は年下だから、自分がリードしてあげなきゃ、って思うのと、」真雪は龍の前に立った。
「何よりその人のことをあたし、大好きだから」
真雪は身を屈めて龍の唇に自分のそれを押し当てた。彼の背中に両手を回し、彼女は少し唇を開いてみた。龍は「ん……」と小さく呻いた。一生懸命目をつぶり、龍は長い間固く唇を結んだままだったが、真雪が舌先で彼の上唇を舐め始めると、徐々に力を抜き、自分も舌を真雪の口の中に差し込み始めた。「ん……」真雪も呻いた。二人の身体は自然とベッドの上に倒れ込んだ。
「あ、あたし、下になるね」真雪は少し緊張したように言った。龍は無言でうなずいた。
ベッドに仰向けになった真雪は目を閉じた。「龍くん、来て……」
「マユ姉……」

下着姿のまま、二人の身体は重なった。そして今度は龍の方から真雪の唇に自分の唇を重ねた。両肘と両膝をベッドについて身体を浮かせたまま、龍は唇だけを真雪に重ねた。さっきよりもお互いの唇は柔らかだった。龍の鼓動は100mをバタフライで泳ぎきった後のように速くなっていた。
龍が唇を離した。真雪が言った。「ブラ、はずして」
龍は真雪の背中に手を回した。ブラジャー越しに龍の胸に真雪の柔らかな乳房が押しつけられた。背中のホックはなかなかはずれなかった。
「はずせる?」真雪が小さく囁いた時、ぷつっ、と音を立ててホックがはずれ、真雪の乳房が解放された。龍はブラの肩ひもに手を掛け、ゆっくりと身を起こしてそれを真雪の腕から抜いた。ピンク色に上気したすべすべの乳房が目の前に現れたとたん、龍は息を呑んだ。
「マ、マユ姉のおっぱい……」
「ちょっと恥ずかしい、かな……」真雪は龍の目を見て顔を赤らめた。
「いいの? マユ姉」
「え?」
「おっぱい吸ってもいい?」
「い、いいよ」真雪はまた目を閉じた。
龍は恐る恐る唇を開いて、真雪の乳首をそっと舐めた。
びくん! 真雪の身体が反応した。龍は手で片方の乳房をさすり始めた。そしてもう一度、今度は口を大きく開いて乳首を吸い込んだ。
「あ、あああん、りゅ、龍くん……」真雪が喘ぎだした。龍は堰を切ったように荒々しく真雪の乳房を揉みしだき始め、もう片方を夢中で吸った。
やがて龍は身を起こした。真雪は目をそっと開けて言った。「龍くん、あたしに……、入れたい?」
龍は息を弾ませて言った。「う、うん」
「…………」
「ど、どうしたの? マユ姉。こわいの? 入れられるの、いやなの?」龍は小さな声で訊いた。
「いやじゃない。いやじゃないけど、なんだか……ちょっと……」
「いやならやめるよ。僕、大丈夫。我慢できるから」
「だめ」真雪は自分に言い聞かせるように強い口調で言った。「だめなの。今夜、あたし龍くんと結ばれたい」
「マユ姉……」
「でも、ちょっと危ない時期なんだ。今」
「危ない? 時期? え? 何のこと?」
「そうか、龍くん、まだ詳しく知らないんだね」真雪は枕元の小さなポーチから正方形の小さなプラスチックの包みを取り出した。
「そ、それって?」
「知ってる?」
「見たことある。ヒ、ヒニングだよね。コ、コン……、なんてったっけ?」
「『コンドーム』だよ。あなたのにつけてくれる?」
「そうか、赤ちゃんができるかもしれない時期、ってことなんだね」
「そうなの」真雪は少し申し訳なさそうに言った。「ごめんね、龍くん。ほんとはそのまま入れたいんだよね」
「ううん。大丈夫。マユ姉のためだから」龍はそう言って真雪の手からその包みを受け取った。
「付け方、わかる?」

「えっと、」包みを破って中身を取り出した龍は、丸められたそのゴム製のものを広げ始めた。「これをかぶせるんだね」
袋状に広げたコンドームを、龍は真雪に背を向けて自分の大きくなったペニスにかぶせようと試みた。「む、難しい。なかなかうまくいかないよ」龍はそうやってペニスをいじっているうちに、だんだんと興奮が高まってきた。「マユ姉、僕、我慢できなくなってきちゃった」
「あ、ここに付け方が書いてあるよ、龍くん」真雪は身を起こした。
「あ、あああ……」龍は呻き始めた。「で、出る、出るっ!」龍は広げたコンドームを先端にかぶせただけの状態で射精を始めた。どくっ、どくんどくん、どく、どく……どく……。
その薄いゴム製の袋の中に大量の精液が放出された。
「だ、出しちゃった……。マユ姉。ごめんなさい」
「最初から広げちゃだめなんだよ。ほら、」真雪はその避妊具の入っていた小箱の隅を指さしながら龍に見せた。
「そうか、こうやるんだ。知らなかった」
「初めてだしね。無理もないよ」
「ごめんなさい」
真雪は龍の手にぶら下げられていたコンドームを取って微笑んだ。「すごい、龍くん、いっぱいだね」
「どうしよう、それ……」
「こうやって、口を結んで、」真雪はそのゴムの袋の口を結んでティッシュに包み、ゴミ箱に捨てた。
「マユ姉、なんか、慣れてるみたい……」
「ふふ、これ、パパに聞いたんだ」
「えっ?! ケニーおじさんに?」
「そうだよ」
「な、なんでそんなこと、おじさんが教えてくれるの?」
「あたしが聞いたんだ」
「な、なんで?」
「さっきも言ったでしょ? 今夜、あたし龍くんと結ばれる予定だったから」
「おじさんにそう言ったの?」
「うん。あたしも初めてだし、いろいろ教えてくれたよ、親切に」
「そうだったの……」
「いやだった?」真雪は龍の顔をのぞき込んだ。
「ううん。マユ姉がそこまで本気で僕とのこの時間を考えてくれてたって、ちょっと感動しちゃったんだ」
「だって、あたし、本気で龍くんのことが好きなんだもん」
龍は真雪の顔を見て、赤くなって照れたようににっこりと笑った。
「笑顔がかわいい、相変わらず」真雪もつられてにっこりと笑った。
龍は急に悲しげな顔をした。「で、でも、失敗しちゃったね、今……」
「大丈夫。すぐにまた元気になるよ。龍くん」
「そ、そうかな……」

龍は、真雪がまだ白いショーツを穿いているのを見て、慌てて自分の膝まで降ろしていたショーツを穿き直した。
龍と真雪はベッドに並んで横になった。
「これだね、火傷の跡……」真雪は龍の左の乳首のすぐそばにあった赤い小さな斑点にそっと手を触れた。「痛かったよね……。龍くん」
「大したことないよ。もう全然痛くないんだ」
「助けてあげられなくて、ごめんね」龍の胸を優しく撫でながら、真雪は少し涙ぐんだ。
「助けられたよ。僕、マユ姉に」
「え?」
龍は真雪の乳房を手でそっと包み込みながら言った。「僕、マユ姉からコクられて、すっごく幸せな気分だった」
「ほんとに?」
「うん。前から僕、マユ姉のことが好きだったもん。知ってたでしょ?」
「知ってたよ」真雪は微笑んだ。
「だから、あんなひどいことされても、僕を好きでいてくれる人がいるんだ、って思うと、ずいぶん気が楽になった」
「龍くんを元気づけられたんだね、あたし。良かった……」
「昨日ぼろぼろで帰ってきてから、本当はマユ姉に真っ先に会いたかったんだ」
「電話してくれたら、飛んで行ったのに」
「でもね、夜の間、実はマユ姉は僕のことをそんなに気にしてくれてないのかも、って思ったりもしてた」
「一人で思い悩んでたんだ……」
「ずっと眠れなかった……」龍は小さな声で言い、真雪の右の乳房を指の腹でそっと撫でた。
「ごめんね、龍くん。あたし、あなたが一番不安な時に、そばにいてあげられなかったね」
「いいんだ。マユ姉が気にすることないよ。僕の勝手な思い込みだし」龍は笑った。「でも、」
「ん?」
「ケン兄にもすごく迷惑掛けちゃってる」
「心配ないよ。ケン兄に任せておけばうまくいくよ」
龍の指が真雪の肌から離れた。
「……僕、もう学校に行けないかもしれない……」
真雪は龍の頬を伝った涙をそっと小指で拭った。
「今回のことでは、ミカさんが被害届を出せば、沼口に警察の捜査が入るはず。そうなれば、あなたもあの事件について警察に事情を訊かれることになる」
「事情を……」
「思い出すのはつらいでしょうけど、がんばって、ありのままを話すんだよ」
「……うん」
「ケン兄が言ってた。証拠はいっぱいあるし、あなたの証言や過去の被害者の証言もあるだろうから、まず間違いなく傷害罪。未成年に対する性的虐待。学校も辞めなければならなくなるはずだ、ってね」
龍はまた涙ぐんだ。「ありがとう、マユ姉、それにケン兄……」
「さあ、元気出そ。もうあたしがお風呂であなたの身体を浄化したから、何も気にすることないって」真雪は笑った。「いつもの元気な龍くんでいてほしいな、あたし。そんな龍くんが好き」真雪は龍の首に腕を回して唇を龍のそれに押し当てた。




































