
Twin's Story 外伝 "Hot Chocolate Time" 第2集
第4話 交尾タイム
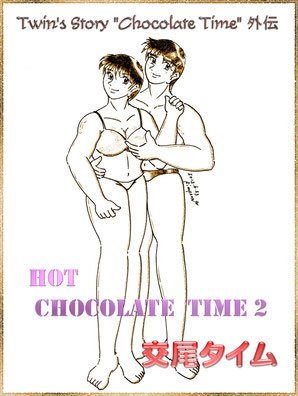
《登場人物》 海棠 龍(16)/シンプソン真雪(20)/ケネス・シンプソン(40)/春枝/香織
交尾タイム(前編)
その男は真雪の腰を力ずくで抱え上げ、不敵な笑いを浮かべながら言った。
「バックから挿れてあげるよ。気持ちいいから」
真雪はひどく焦ったように叫んだ。「だめ! やめて!」
男も真雪も全裸だった。そして無機質な白いシーツが広げられた大きなベッドの上で、二人はその身体を重ね合っていた。
「どうして拒絶するんだい? 真雪。君だって僕とこういうことをしたかったんだろう? だからついてきたんじゃないのかい?」
「いや! 放して! あたしに触らないで!」
男は構わず真雪の腰をがっちりと押さえ込み、躊躇うことなく硬く大きくなった男の武器を彼女の秘部に押し込んだ。
「いやーっ! やめて! やめてください! 板東主任!」

板東と呼ばれたその男は、始めから激しく腰を前後に動かし、乱暴にペニスを出し入れした。
「カラダは反応しているんだろう? 正直になったらどうだい? 真雪」
板東の身体に汗が光り始めた。
真雪の身体は、板東に貫かれ、激しく揺さぶられていた。真雪の豊かな乳房が大きく揺れる。男に身体の奥を突かれるたびに、彼女の目から涙が白いシーツに飛び散った。
「いやーっ!」
板東は真雪の手首を掴んだ。そしてまるで馬の手綱を引くように両手で彼女の身体を自分の腰に引き寄せ、密着させた。「も、もうすぐイくよ、イく……」
「だめ! 中には出さないで! お願いです!」
「本当は中出しされたいんだろう? このメスのカラダは僕の種を欲しがってるみたいじゃないか。あ、出、出る……」
「やめてーっ!」
「出すよっ! ぐううっ!」
板東はカラダを大きく仰け反らせた。その瞬間、男の体内から噴き上がった欲望の奔流が、一気に真雪のカラダの奥深くにほとばしり出た。
びゅっ! びゅるるっ!
板東は快感にゆがんだ表情のまま、何度もびくびくとカラダを硬直させた。
「いやあーっ!」
真雪は顎を突き出し、目を大きく見開いて絶叫した。
(→板東俊介のプロフィール)

龍はベッドの上で飛び起きた。はあはあと大きく荒い呼吸を繰り返し、全身が汗にまみれていた。鼓動も、暗い部屋中に響き渡るかと思われるほどに大きく、速かった。
「ゆ、夢……」
春の足音がもうそこまで来ている2月終わりの夜のことだった。
――海棠 龍は現在高校一年生、16歳。彼のいとこのシンプソン真雪は昨年12月に20歳になったばかりで、この3月には動物飼育の専門学校を卒業する。
龍と真雪は三年前の夏から恋人同士になっていた。当時高三だった真雪が龍に告白したのが始まりだった。龍も幼い頃から自分をかわいがってくれていた真雪に、思春期になって少なからぬ恋心を抱き始めていたこともあり、二人の交際はきわめて順調にスタートした。真雪が告白して数日後には、二人は身体を重ね合い、深い仲になった。以後、彼らはずっと熱く、甘い関係を続けていた。
――しかし、思いがけない事件が突然起きた。
昨年12月初めに実施された専門学校の重要なカリキュラムの一つ、水族館での宿泊実習で、真雪は実習生たちの世話をする研修主任の板東という男に誘惑され、夜を共にしてしまったのだ(→『Chocolate Time』基礎知識「真雪の過ち」)。
その事件は真雪と龍の心に深い傷を残した。実習から帰った夜、半狂乱になりながら自分のやったことを悔やみ、犯した罪を龍に謝り続けた真雪。その姿を見るに堪えず、胸を引き裂かれるような苦痛に苛まれながらも必死で真雪を赦し、包みこんだ龍。
それから今まで、二人は何度も抱き合い、激しく愛し合って、その忌まわしい出来事を忘れるための努力を強いられたのだった。
「いやだな……。なんで今になってこんな夢、みるかな……」
鼓動が収まった龍はベッドで身体を起こしたままうつむき、一人呟いた。
窓の外から小鳥の声がかすかに聞こえてきた。
仰向けになった彼は、それから眠ることができずに、しらじらと明け始めた朝の冷たく白い光が染め始めた天井を、じっと見つめていた。
店の駐車場に立っているプラタナスは、すっかり葉を落とし、その根本の土には白い霜柱が立っていた。
龍はその木の枝を見上げた。「もうすぐ新しい芽が吹き始めるんだよな。寒い冬を堪え忍んで……」
その時、店のドアに取り付けられた小さなベルを派手に鳴らして、真雪が飛び出してきた。

「龍っ!」
黒いタイツの上にデニムのショートパンツを穿き、ショートブーツを履いて白いピーコートを羽織った彼女は、満面の笑顔で龍に駆け寄り、抱きついた。
「真雪」龍も彼女の身体を抱きとめ、背中に回した腕に力を込めて、耳元で囁いた。「今日もかわいいね」
「ほんとに? ありがとう」真雪はまた笑った。
「今日はすごく冷えるね。もうすぐ春とは思えない。寒くないの? そんな格好で」龍は真雪の脚を見ながら言った。
「どこ見てるの? 龍のエッチ」
「だ、だって、そんな短いショートパンツ……」
「タイツ穿いてるから大丈夫。とっても温かいんだよ。龍にも買ってあげようか?」
「いや、遠慮しとく」
町の繁華街のど真ん中にあるチョコレート専門店『Simpson's Chocolate House』(『Simpson's Chocolate House』について)が真雪の家だった。
彼女の父親ケネス・シンプソンは、その父アルバートの代から続いているこの店のオーナーである。ケネスの妻、つまり真雪の母マユミは、龍の父親のケンジと双子の兄妹の関係。
真雪自身にも双子の兄、健太郎がいた。彼も現在ショコラティエの修行中で、菓子作りの専門学校に通っている。
店のドアからケネスが顔を出した。「ええなー、デート」
「ケニーおじさん」龍が笑顔で応えた。
「楽しんでくるんやで」
「うん。ありがとう、パパ」
「帰りは明日なんやろ?」
「そ、そうだね……」真雪が赤くなって答えた。
「夜もベッドでぎょうさん楽しむんやで、真雪」
「ちょっとパパ、恥ずかしくなるようなこと言わないで……」
「龍、真雪をちゃんと満足させへんかったら、承知せえへんぞ」
「いや、おじさん、露骨だから……」龍も赤面した。
「ゴム、持っとるか? 龍」
「も、持ってるよ。心配しないで」
「一個や二個じゃ足れへんやろ。一箱は用意しとかなあかんのとちゃうか?」
「もう! パパ引っ込んでてよ」真雪が叫んだ。「行こ、龍」そして龍の腕を取って歩き出した。
土曜日の賑やかな街の舗道を歩きながら、真雪は手に持っていたタータンチェックのマフラーを龍の首にふわりと巻いた。
「え? あ、ありがとう。でもこれ、真雪のでしょ?」そのマフラーは柔らかで甘い真雪の香りがした。
「あたしは大丈夫。このコートとっても温かいんだ」
「初めて見る気がする。そんなコート、持ってたっけ?」
「これ、ママのなの」
「え? マユミ叔母さんの?」
「そ。高校生の時に使ってたんだって」
「物持ちいいね。叔母さん」
「冬のデートの時は必ずこれを着てたんだってよ」
「え? デートって、うちの父さんとの?」
「そう」
――真雪の母マユミと龍の父ケンジは、双子の兄妹でありながら、高校時代は秘密の恋人同士だった。二人はその頃、夜になるとどちらかの部屋でチョコレートとコーヒーを楽しみ、なだれ込むように身体を求め合い、そのまま一つのベッドで朝まで眠る、という日々を送っていたのだった。
「父さんたちも、よくデートしてたのかな」
「そりゃあ、恋人同士だもん」
「で、でも、高校生の兄妹でしょ? 端から見たら、異様だよ」
「ママは平気でケンジおじと腕組んで歩いてたんだってよ」
真雪は龍の腕に自分の腕を絡めた。
「マユミ叔母さんって、大胆だったんだね」
「ケンジおじは、その時きっと照れて赤くなってたんだろうね」真雪は妙に嬉しそうに言った。
昼食の後、アーケードを抜けたところで真雪が言った。
「龍、『Haru』に寄っていい?」
「いいよ。もちろん」
そのペットショップ『Haru』は『シンチョコ(Simpson's Chocolate House)』の近くのビルの一階にあった。入り口にはセントバーナード犬の大きな置物。その首には小さな洋酒樽。そこに『Welcome』とペイントされていた。
真雪は小さなチャイムがつり下げられ、薄い緑色の縁取りの施されたドアを開けた。「こんにちは」
「まあ! 真雪ちゃん。いらっしゃい」
初老の小柄な女性が真雪と龍を出迎えた。「龍くんもいっしょなのね。今日はデート?」
「は、はい」龍は頭を掻いた。
「これ、スタッフの皆さんで召し上がってください」真雪はシンチョコのアソートチョコレートの箱を、その物腰の柔らかな店長に差しだした。
「あらあら、いつもありがとうね」店長の晴枝はそれを微笑みながら受け取ると、二人を奥の部屋へと促した。
スタッフルームに通された二人の前に紅茶のカップが置かれた。
「よく来てくれたわね。どう? 学校は。もうすぐ卒業だけど」
「はい。資格もいろいろ取ることができて、お役に立てそうです」
「そう。それは良かった。私も貴女のような人がこの店のスタッフの一員になってくれると、とっても助かるわ。心おきなく隠居できるってものだわ」
真雪は4月から、行きつけのこのペットショップへの就職がすでに決まっていた。
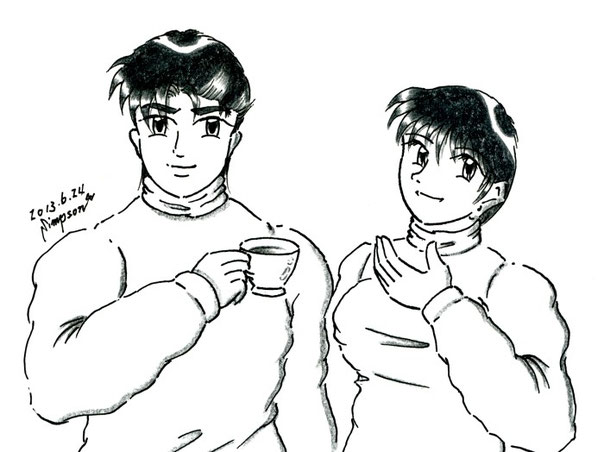
「龍くんは、どう? もうすぐ高校二年生ね」
「はい。なかなか楽しい毎日です」
「写真の勉強してるんでしょ?」
「部活ですけどね」
「龍くん、もう写真はプロ並みなんじゃない? お客様もみんな褒めて行かれるのよ。才能あるのよね、きっと」晴枝は壁の写真に目を向けた。
このショップで売りに出されている犬や猫、うさぎなどの写真は、龍が撮らせてもらっていた。それは店のパンフレットや店内装飾に利用されていた。
「貴男の写真、この店にいる子たちのかわいらしい表情をとってもうまく写してくれてて、私、いつも感心してるわ。ありがとう」
「い、いえ、まだまだ半人前です」龍は照れて頭を掻いた。
「晴枝店長、ポメラちゃんのごはん、そろそろ、」一人の若い女性スタッフが部屋のドアを開けて顔をのぞかせた。「あっ! 真雪さん!」
「こんにちは、香織ちゃん。相変わらず元気いいね」
「海棠くんとデートなんだー。いいなー」
「こ、こんにちは」龍は緊張したように香織を見て微笑み、小さく手を振った。
「香織ちゃんって、龍くんの同級生だったわね?」晴枝が言った。
「そうです」
「え、えらいよね、香織さん」龍が言った。「休みなのに、アルバイトずっとやってるんでしょ?」
「土日は稼ぎ時だからね」香織は龍に茶目っ気たっぷりのウィンクをした。
香織は母親を早くに亡くし、父親と二人で暮らしていた。龍と同じ高校に通っているが、こうして休みの日は家計を助けるために、このショップでアルバイトをしていたのだった。
「大変だね。香織さん」龍がぽつりと言った。
「あたし、動物好きだし。苦にはなってないよ。店長も親切だからね」香織は愛らしい顔で微笑んだ。
真雪がソファから立ち上がった。「ポメラちゃんのごはん、あたしがあげていいですか? 店長」
「もちろんよ」
真雪は部屋を出て、香織といっしょにペットのレストルームに向かった。
晴枝と龍が部屋に残った。
「龍くんと真雪ちゃんは、いつも熱々で素敵ね」
「え?」飲みかけたカップを口から離して、龍は晴枝を見た。
「ほんとにお似合いだと思うわ」
「そ、そうですか?」龍は顔を赤らめた。そしてまたカップを口に持っていった。
「ちっちゃい頃から仲良しだったんでしょ? いとこ同士だし」
「はあ、まあ……」
店の奥から、犬の声が聞こえてきた。それは唸るような、聞き慣れた犬の吠える声とはちょっと違っていた。
耳をそばだてている龍に向かって晴枝は言った。「今、交配させてるのよ。犬」
「交配?」
「そう。赤ちゃんを産ませるの。純血種同士を掛け合わせてね」
「そ、そうなんですね」
「血統書がついてるワンちゃんを飼いたいっていう人、多いからね」
「で、でも高いんでしょ?」
「そうねえ。だけど、生まれる赤ちゃんの命に変わりはないのに、どうしてそんなことにこだわるのかしら、って思うことも時々あるわね」
「あ、あの、」
「なに?」
「メ、メスが、そのオスを嫌がって交配に失敗する、なんてこと、あるんですか?」
「そりゃあね。相性は動物にだってあるわ」
「そ、それでも無理矢理、あの、や、やっちゃうオスなんて、いたりするんですか?」
「オスは子孫を残そうってする本能があるからね。でも、女の子の方がひどく拒絶したりすることもある。おもしろいわね。そういうところは人間とあんまり変わらない」晴枝は紅茶のカップを取り上げた。
「あ、あの、見ること、できますか? その、こ、交配」
「ええ。いいわよ」店長はあっさり言った。「でもそっとね。あんまり刺激しないように。結構あの二匹いい雰囲気だから」
晴枝に促されて、龍はその柔らかな光が満ちている部屋にそっと足を踏み入れた。その部屋の中はどことなく神秘的な雰囲気さえ感じられた。
大きめのケージの中で、小さな斑のビーグル犬の背中に、それより少し大きめのビーグル犬が後ろから覆い被さっている。そして腰を細かく震わせ、落ち着かないように小さく足踏みをしていた。
龍はその様子をじっと見ていた。鼓動がだんだん速くなってきて、それをすぐ後ろに立った晴枝に悟られないか、と動揺し始めた彼は、思わず振り返り、焦ったようにそこを出た。
「あれ、龍、どこ行ってたの?」
いつの間にか真雪がもとの白いソファにかけ直して紅茶を飲んでいた。
「え? いや、ちょ、ちょっとね」
「犬のラブシーンを見てもらってたのよ」晴枝がにこにこしながら言った。
「交配、うまくいきそうですか?」
「たぶん大丈夫。あの二匹、幼なじみだしね。きっと暖かくなる頃にはかわいいベビーが誕生するはずよ」
店長は真雪と龍を交互に見た後、微笑みながらまたカップを口に運んだ。
◆

日が傾いて、冷たい風が街の通りに小さな木の葉の渦を作っていた。
「やっぱり暗くなってくると、一段と寒いね」真雪が龍の腕にしがみついた。
龍は腕時計を見た。「そろそろ予約してた時刻だ」
「え? もうそんな時間?」真雪も腕時計に目をやった。
中南米系多国籍料理の店『ユカタン』は、その出入り口の周りにモアイのレプリカやサボテンの鉢植えなどが置かれた、何かそこだけ違う世界のような雰囲気をたたえていた。
「変わったお店。ここ、食事するところだったんだね」
「いつか真雪といっしょに来たいな、って思ってたんだ」
「家族ではよく来るの?」
「父さんのお気に入りなんだ。母さんも辛いモノとか好きだし」
「ミカさんもお気に入りなんだね」
「特にあの人、ここでしか飲めない『ボエミア』っていうビールが大好物なんだよ」
「へえ」真雪は笑いながら龍の後について店内に入った。
龍は真雪のコートを脱がせ、ハンガーに掛けた。そして壁に取り付けてあった象のように長い鼻のついた変わった顔の彫刻のフックに吊した。
真雪はそのフックをまじまじと見た。「中南米、って感じの顔だね」
「それは『トラロック』。アステカの水の神様だよ」
「そうなんだ。よく知ってるね、龍」
「前に父さんが訊いてた。店の人に」
暗い店内の隅のテーブルに落ち着いた二人は、向かい合わずに横に並んで腰掛けた。龍は真雪の腰に手を回して自分に引き寄せた。真雪はほんのり顔を赤らめた。
まもなくホールスタッフが水の入ったグラスを運んできた。「いらっしゃいませ」




































