Twin's Story 3 "Mint Chocolate Time"
《3 海へ》
海棠家の夕餉。夕方だというのに外ではまだやかましく蝉が鳴いている。
「ねえ、今度の休みに海に行っていい?」マユミが両親に向かって言った。横でケンジは黙ってトマトに箸を伸ばした。
「誰と?」母親が聞き返した。
「ケニー」
「ケニーくん? あんたら付き合ってんの?」
「別にそういう訳じゃないけど」
「お父さん、どう思う?」母親は冷や奴に醤油をかけていた父親に話を振った。
父親は厳しい顔でマユミに目を向けた。
「付き合ってもいないオトコと二人で海。父親としては賛成しかねるが……」
「じゃああたし、ケニーとつき合うことにする。それならいいんでしょ?」
「いや、そういうことじゃなくてだな、」
「大丈夫だと思うよ、ケニーなら」

父親は醤油差しを手に持ったまま言った。「つき合っていようといまいと、まだ高校生のおまえの身に何かあったらどうするんだ。おまえに手を出さないという確証がない以上、うんとは言えんな」父親は少し考えて、醤油差しをテーブルに戻しながら言った。「そうだ、ケンジ、おまえもいっしょに行け」
「そうね、それがいいわ」母親も言った。
「おまえがついていれば、ケニーも劣情の波に呑み込まれることはないだろう」
「いや、ケニーはそんなやつじゃないから」ケンジが言った。
「もしも、ってこともあるじゃない。ね、ケンジ、いっしょに行ってあげて」
「えー、ケン兄もいっしょなのー」マユミは残念そうに言った。
「何よ、あんたこないだケンジは自分に優しくしてくれるって言ってたじゃない」
ケンジは横目でちらりとマユミを見て、気づかれない程に頬を赤らめた。そして、そのちょっとした動揺を押さえ込みながら言った。
「ま、しかたないな。めんどくさいけど見張っといてやるか、マユを」ケンジはコップの水を飲み干した。
「3人でいってらっしゃい、マユミ。ケンジお兄ちゃんが一緒なら安心だわ」
父親も安心したように豆腐に箸を伸ばした。
ケニーというのは、フルネームをケネス・シンプソンと言い、カナダ人の男性と大阪人の女性を両親に、日本で生まれたケンジの親友だ。見た目は思いっきり外国人だが、こてこての大阪弁をしゃべる、根っからのオプティミストである。
彼の父親アルバートは日本で修行を重ねた腕の良いショコラティエ。ケネスは10歳から17歳まで、家族で父親の母国カナダで過ごしたが、その最後の年、彼が高校二年生の時、日本に水泳の部活留学生としてやって来ていた。そしてケンジが在籍するすずかけ高校に通いながら、水泳部に所属してケンジと共にバタフライの技術を磨いた。
その縁もあり、父親アルバートは、家族共々日本に定住することを決意。ケンジたちの住むすずかけ町にこの春チョコレートハウスを構えた。以後、ケンジはもちろん、マユミもケネスとは友人として親しいつき合いを続けていた。
ケネスは自他共に認めるバイセクシャルで、ケンジたちもそのことは承知していた。また、彼はケンジとマユミの秘密の関係を知る唯一の人物でもあった。
夕食後、二人はケンジの部屋でチョコレートタイムを愉しんでいた。
「大成功」マユミが嬉しそうに言った。
「あんなに上手くいくとは思わなかったなー」
「悩んだ甲斐があったね」
「父さんが言い出さなければ、俺が言うはずだったんだけどな」
「杞憂だったね」
「マユ、母さんに言ったのか? 俺がおまえに優しくしてるって」
「だって事実じゃん」
「怪しまれてるんじゃないか? 俺たちの関係」
マユミは二人の間に置かれた箱から薄いチョコレートをつまみ上げた。「怪しんでるんだったら、初めからあんな提案しないはずでしょ? ケン兄といっしょに行け、なんて」
「そうか。それもそうだな」
チョコレートを口に入れたマユミは目を閉じて小さく深呼吸した。
「このチョコ、何だかすーっとする」
「ミント入りなんだ。ケニーの父ちゃんの手作り。まだ試供品段階なんだと」
「ケニーにもらったんだ」
「そう」ケンジもその爽やかな味と香りのチョコレートをつまんだ。「夏をイメージしたチョコなんだってさ。早ければ来週にも製品化されるってケニー、言ってた」
「確かに爽やかで、夏って感じがするね」
◆
電車の窓から見える風景が、トンネルを抜けた途端青く広がった。
「何でわいが悪モンにならなあかんの?」
向かい合ってケンジ兄妹と座ったケネスが、カップ入りのポテトスナックの封を切りながら言った。
「悪い悪い。ああでも言わなきゃうちの親が賛成してくれなくて」
「わいがマーユを襲わんように、ケンジがついて来る、ってことなんやな?」
「そうだ」
ケンジはケネスが手に持ったスナックを一本取り出した。
「ほんま、何もわかってへんな、おまえんとこの両親」
「俺がずっとおまえのそばにいて、オオカミケニーから守ってやるからな、マユ」
ケンジはつまみ上げた細長い菓子をマユミに渡した。
「嬉しい、ケン兄」
「何言うてんねん。劣情の波に呑み込まれるんは、ケンジやないか。ほんまに……」
よく晴れていた。ビーチにはたくさんの水着姿の人がいた。海の家、スイカ売り、アイスクリームや焼きトウモロコシの屋台。まさに夏真っ盛りの海辺の風景だった。

「どうだ、ケニー、おまえ好みのオトコやオンナがいるか?」
「最近の水着はセクシーさが足りんな。例えば、」ケネスは一人の20代ぐらいの女性に視線を投げた。「あの姉さんなんか、スタイル抜群やねんけど、せっかくのビキニにパレオ巻いてはる。今しか人に見せられへんのに、もったいないと思えへんか? ケンジ」
「確かにな」
「それから、あの兄さん」ケネスは別の場所で彼女とおぼしき女性といっしょに歩いている若い男に目を移した。「わい好みの筋肉質のカラダやねんけど、膝までの丈のだぶだぶのサーフパンツやろ? ほんまもったいないわ」
「だけど、今のメンズの水着はみんなあんなもんだぜ。おまえみたいなぎりぎりのローライズ競パン穿いているやつはなかなかいない」
「カナダやアメリカのオトコはあんなもん穿けへんねん。夏の海っちゅうたら、もう露出してなんぼや。体型に関係なくオトコもオンナもちっちゃい水着着る者の方が圧倒的に多いで」
「そうなんだ。でもな、見る方としては、体型にも気遣って欲しいものがあるな」
「見る方としてはな」ケネスは笑った。「そういうケンジもなかなかきわどい水着やんか。日本人離れしてるで」
ケネスもケンジも極端に丈の短いピッタリしたビキニの水着を穿いている。
「わいはともかく、ケンジもそういうシュミがあんのんか?」
「動きやすいから好きなのと、荷物が少なくて済むのと、」
「何やの、その理由」
「一番の理由は、マユが選んでくれたからだ」
「へえ、マーユは好きなオトコにそういうパンツ穿いてもらいたいんやな」
「そうらしいぞ。自分の水着買ってきた時、これも一緒に買ってきてくれたんだ」
ケネスは少し驚いて言った。「へえ、マーユは平気なんやな、そんなメンズの水着買うのん」
「あいつ、結構大胆だからな。見た目以上に」
「ま、ケンジほどのガタイなら、そういうパンツの方が似合うな、確かに。わいもちょっとムラムラするわ」
「ケニー、おまえここで俺を押し倒すんじゃないぞ」
「隙を見せたらアブナイで」
ケンジとケネスは笑い合った。
「楽しそうね」二人の背後で声がした。
ケンジとケネスはいっしょに振り向いた。
「マユっ!」ケンジが大声を上げた。
ヒュッ! ケネスが短く口笛を吹いた。「マーユ! ええな、ええな、ええな、その水着、イけてるわ」
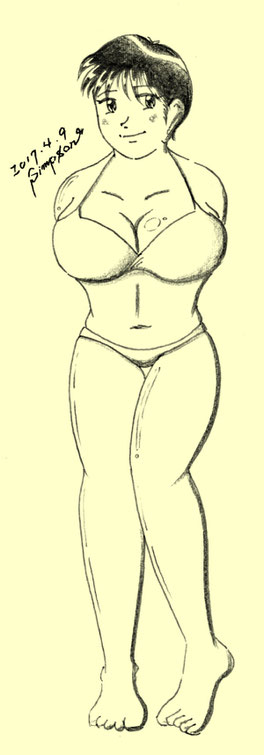
マユミが水着に着替えて二人の所にやってきたのだった。それはセパレート型で明るいスカイブルーのシンプルなビキニだった。
「あらためて見ると、マーユ、巨乳やな。あ、すんまへん、下品な言葉使こてしもた」
「いいの、ケニー。ケン兄もおっぱい大きい方が好きなんだよ」
「オトコはみんなそんなもんや。それにそのちっちゃなビキニ! 最高やな、な、ケンジ、ん? どないしたん、ケンジ」
「い、いや、ちょっと鼻血が……」ケンジはティッシュを丸めて鼻に詰め込んでいる最中だった。
「はあ?!」ケネスは思い切り呆れた。「お、おまえマーユの裸、いやっちゅうほど見てきたんやろ? なんで今さら興奮せなあかんの?」
「こ、こんな明るいところで、しかもこんなぎりぎりの水着姿見せられたんじゃ、誰だって興奮するに決まってるだろ!」顔を真っ赤にしたケンジはムキになって反論した。
マユミはケンジに近づき、耳元で囁いた。「白い水着は、夜に披露してあげるね」
ケンジは思わずティッシュを詰めた鼻を押さえた。
「や、やばい、鼻血の流出量が増えた……」
「まったく……やってられへん」ケネスは眉尻を下げて遠慮なくため息をついた。
「うれしい。まだケン兄を興奮させられるカラダなんだ、あたし」
マユミは一人で焼きトウモロコシと飲み物を買いに行った。
「ところで、」ケンジが言った。「ケニー、おまえのそのでかい荷物は何なんだ?」
「これか? これはおまえらのためにわいがわざわざ持ってきてやったボートや」
「ボート?」
「大人二人乗りのゴムボートや」
「なんでそれが俺たちのためなんだよ」
ケネスはケンジの目をじっと見つめて、諭すように口を開いた。
「ケンジ、おまえマーユの水着姿見とるだけでは満足せえへんやろ? そのうちきっとおまえらは我慢できんようになるはずや」
「そ、そんなこと……」
「いいや、間違いなく、なる。そやけど、人目があったら思う存分愛し合うことはできへん。そこでこのゴムボートが必要や、ってことやんか、鈍いやっちゃな」
「ケニー……。おまえ本当に俺たちのことを思ってくれてるんだな」
「思とる。それに加えてケンジ、おまえの習性もよー解っとる」
「習性って……」
「納得したら手伝うてや」
ケネスは足踏みポンプでそのゴムボートに空気を入れ始めた。
「こ、これは思った以上にハードな作業……」ケンジは汗だくになりながらその作業を続けた。「おい、ケニー、交代してくれ」
「よっしゃ」
そうして二人は小一時間かかってようやくその二人乗りゴムボートを完成させたのだった。ケネスはへとへとになって砂浜に大の字になった。「あ~しんど」
「お疲れさま、ケニー。はい、トウモロコシ食べて」
「おおきに、ありがとう」ケネスはマユミから焼きトウモロコシを受け取ると貪るように頬張った。
「ケン兄も、はい」
「ありがとう、マユ」




































