Chocolate Time 雨の物語集 ~雨に濡れる不器用な男たちのラブストーリー~
『ずぶ濡れのキス』 (1.音楽室での出来事|2.明かされる秘め事|3.目覚めの朝|4.ずぶ濡れのキス|5.門出)
《1.音楽室での出来事》
引き裂かれた黒いストッキング。ロープで縛られた両手首。言葉を封じる猿ぐつわ……。
生徒用の机にカラダを倒し、尻を後ろに突き出した若い女教師。
「ほら、先生、じっとしてなよ、すぐ終わるって」
その男子生徒は制服のズボンと下着を下げた格好で、いきり立った凶器を背後から彼女のショーツに擦りつけ始めた。
「うううっ!」教師は涙をこぼしながら呻いた。
「変な声出すと、誰かに気づかれるじゃん」
生徒はにやにや笑いながら激しく腰を前後に動かし始めた。
教師は苦痛に顔をゆがませ、声を殺して全身を震わせた。
「イ、イく……」生徒が彼女の腰を両手で鷲づかみにしてカラダを硬直させた。
どびゅびゅっ!
女教師のショーツ越しの尻とブラウスをめくり上げられた背中に、生徒のカラダから噴き上がった熱い液が何度も迸り、その白い肌をどろどろに汚し続けた。
◆
初秋の少しひんやりとした風が、駐車場に散り落ちたプラタナスの葉を弄びながら吹き過ぎた。
すずかけ町の老舗スイーツ店『Simpson's Chocolate House』の正面玄関に二人の男が立っていた。
「悪いな、おやっさん。忙しいのに来てもろうて」
頭を掻きながら申し訳なさそうに言っているのは、この店の主、名ショコラティエのケネス・シンプソン(38)。
「なんのなんの。いつも贔屓にしてもらってっから」
もう一人の白髪頭の老人が威勢良く言った。彼は玄関脇にしゃがみ、三和土の角にメジャーを当て直していた。
その老職人、志賀建蔵(69)は腰を伸ばした。「明日、モルタルとタイル持って来て修繕するよ。開店前にやっちまうか。7時頃大丈夫かい? ケネス」
「そんな朝早くに? もう結構寒いで」
「構わんよ」建蔵は日焼けした、しわの深く刻まれた顔をほころばせた。「仕事は苦にならん」

ケネスは建蔵を店の中に招き入れ、喫茶スペースの椅子に座らせた。建蔵は首に巻いていたタオルを取り、出されたコーヒーカップを持ち上げ、一口飲んだあと、遠慮なく大きなため息をついた。
「ここのコーヒーはうまいな。いつ飲んでも」
「おおきに」ケネスも彼に向かい合って座った。
二口目のコーヒーを飲んで建蔵がカップをソーサーに戻した時、ケネスが低い声で少し躊躇いがちに言った。
「将太はちゃんと学校行っとるんか?」
老職人はちらりとケネスを見て、すぐにうつむいた。「何とかな……」そして小さなため息をついた。
「来年、卒業やろ? 就職……」
「学校行くだけで精一杯ってとこじゃからな。先のことなんぞ、考えてねえよ。やつは……」
「『志賀工務店』の跡継ぎにせえへんのか?」
「もう、将太にその話するのはやめちまったよ。」
「そやけど、手先も器用で、モノ作るのん、得意なんやろ?」
「素質はあると思うんだがな。やつがその気にならねえと、こればっかりはな……」
その老職人は静かにコーヒーを口に運んだ。
「おやっさんがうちの裏口改造してくれた時、将太も一緒に来てたやろ? まだ小学校上がる前やったかな。あん時将太が板の端切れで作ってたちっちゃな車、今でも置いてあるで。ほら」
ケネスは店の商品棚の一画を指さした。子ども向けのチョコレート菓子が並べられているコーナーに、それはディスプレイの一つとして置かれていた。
建蔵は、照れたように微笑んだ。「ケネス、あんたにゃ感謝してるよ。将太を気遣ってくれる人は少ねえから。ケンちゃんや真雪嬢ちゃんにも将太のやつ、気に掛けてもらってんだろ? 学校で」
「健太郎も真雪も将太とは違うクラスやけどな。ちっちゃい頃におやっさんと一緒に来てた時から、将太とは何や仲良うしてるみたいやで」
「感謝してるよ、ケネス」建蔵はケネスの目を見て数回瞬きをした。「ヤツのオヤジが死んで、母親が男作って出て行ってから、わし一人じゃ手に余るようになっちまった。あんたら親子がヤツを救ってくれてるようなもんだよ」
「おやっさんにとっちゃ、たった一人の肉親やないか。今が踏ん張り所やで」
「そうだな……」
「わいも将太にできるだけのことはしてやるよってにな。困ったことがあったら、いつでも言うてや」
「すまん……すまんな、ケネス」
建蔵は涙ぐんでケネスの手を取った。
◆
――シンプソン家の夕食時。
ケネスはテーブルの向かい側に座っている健太郎(17=高三)に声を掛けた。
「健太郎、将太は学校ではどんな様子なんや?」
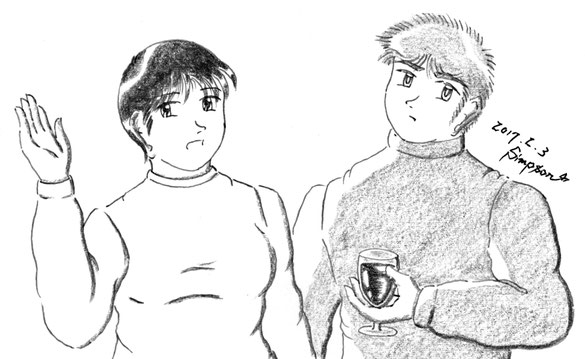
健太郎はすぐに顔を上げた。「何とか学校には来てるみたいだよ」
健太郎の横に座っていた双子の真雪(17=高三)が言った。「授業中は教科書も出さずに机で寝てるらしいけどね」
「そうか……」
「何? 何かあったの?」
「いや、今日玄関の修繕頼むのに、志賀のおやっさんに来てもろうて、ちょっと話したんや」
「将ちゃん、卒業したらどうするんだろうね……」ケネスの妻マユミが箸を置いてワインのグラスに手を掛けた。
「工務店を志賀のおっちゃんといっしょにやればいいのにな……」健太郎が独り言のように言った。
真雪が言った。「担任の先生が毎週水曜日の午後に進路相談してる、って話だけど」
「何で水曜日やねん」
健太郎が口を開いた。「将太の担任の鷲尾彩友美(わしお さゆみ)先生って音楽の先生なんだけど、水曜日の午後には授業がなくて、時間が空いてるらしいんだよ」
「なるほどな。で、その先生、大丈夫なんか? 将太の相手ちゃんとできてるんやろな? 女性なんやろ?」
「若いけど一応先生だし。大丈夫なんじゃない?」
「怒る時は怒るよね、鷲尾先生。それに、しょっちゅう将太を呼びつけてるよ」
「職員室に?」マユミが言った。
「さあね。でも将太くんも素直について行ってるみたいだよ」
マユミがグラスをテーブルに置いて、小さなため息をついた。「ちゃんと卒業できたらいいね、将ちゃん……」
◆
将太は風呂から上がって、工務店の二階にある自分の部屋に入るなり、畳に大の字になった。そしてしばらく天井を見つめていた。古くなった天井のシミを見ながら、彼は忘れることのできない人の面影をそれに重ねてみたりした。

のっそりと起きあがった将太は、タンスの前にあぐらをかいて座り、一番下の引き出しをそっと開けた。そして中に手を入れた。
将太が取り出したのは、黒いパンストだった。
しばらくじっとそれを見つめていた将太は、おもむろにそれを丸めて、自分の鼻に押し当てた。そして目をつぶり、大きく何度も息をした。
しだいにその息は荒くなっていった。
突然、将太は目を開いて、それを乱暴に元の引き出しに投げ込むと、またばたん、と畳の上に寝転がった。
◆
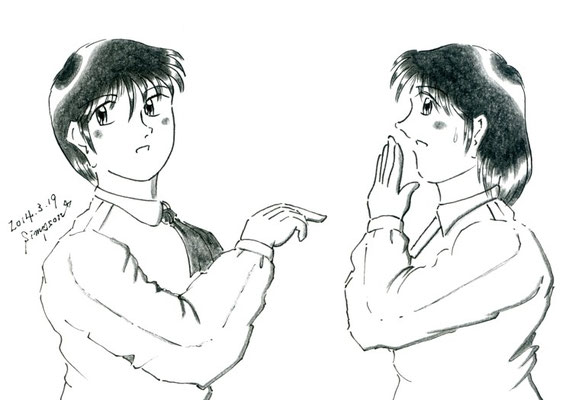
翌週の水曜日。朝から真雪は音楽科教師鷲尾彩友美と廊下ですれ違った。
「あ、鷲尾先生」真雪が言った。
彩友美は立ち止まり、振り向いた。「え? どうしたの? 真雪さん」
真雪は彩友美に近づき、耳元で囁いた。「ストッキング、伝線してます」
「ほんと? ありがとう、教えてくれて」
真雪は少し不思議そうに言った。「鷲尾先生は、いつも水曜日は黒いストッキングなんですね」
「え? そ、そう……かな」
「何かワケがあるんですか?」
「ううん、偶然じゃない?」
彩友美は焦ったように真雪から離れていった。
真雪は、少し首を傾けて、そのほっそりした教師の背中を見送った。
昼休み、職員室で弁当を食べていた彩友美の元に、教頭が湯飲みを手にやって来た。「鷲尾先生」
「はい」彩友美は振り向き、その小太りで髪の薄い中年男を見上げた。
「今日も午後から志賀の進学相談ですか?」
「はい。いつものように」
「どうです。何とかなりそうですかな?」
「少しずつですけど、あの子、私に心を開いてきてます。頑張ります」
「あまり無理しないでくださいよ。それに、」
教頭は口元にうっすらを笑みを浮かべた。「ヤツに変なことをされたら大変だ。くれぐれも気をつけて」
彼はそれだけ言ってそこを離れた。
この高校の音楽室は校地の端にある『芸術棟』と呼ばれる建物の二階、一番奥にあった。
彩友美は教室の入り口のドアを恐る恐る開いた。
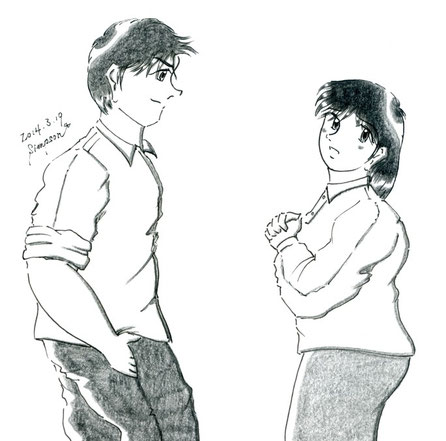
カーテンが閉めきられて薄暗くなった教室の真ん中に、制服をだらしなく着崩し、ずり下げたズボンのポケットに手を突っ込んだ男子生徒が一人立っていた。彼は彩友美の姿を認めると、まるで死んだ魚の目のようにくすんだ瞳を向けてにやりと笑った。
「待ってたよ、先生」
彩友美はドアを入ったところで一瞬立ちすくみ、息を呑んだ。
「やろうよ、先生」
若い女性教師は覚悟を決めたようにドアに内鍵をかけて生徒に近づいた。
その生徒、志賀将太は、机を動かし、床にスペースを作った。そして、ピアノに掛けられていた黒いカバーを乱暴に剥がし、そこに広げた。
「寒くないように暖房入れといたから」将太はそう言って、彩友美のグレーのジャケットに手を掛けた。
「待って! 自分で脱ぐから……」
将太は手を離した。「ブラとストッキングは脱がないでね、先生」
彩友美は黙って着ていたものを脱いでいった。将太も上着を脱ぎ、ズボンのベルトを緩めた。
彩友美は床に広げられた黒いピアノカバーの上に、仰向けに横たわった。
「あれえ、先生、今日はノーパンじゃん」将太は小さく口笛を鳴らした。「いいね!」
将太は乱暴に彩友美の両脚を広げ、太股の内側に張り付いた光沢のある黒いストッキングを鷲づかみにして、一気に裂き破った。
「んっ!」彩友美は目を固く閉じ、顔を背けた。
「どう? 俺に犯されるのが好きになってきた?」
むき出しになった彩友美の股間に顔を近づけて将太は、谷間に指を這わせ始めた。
「あ、あああっ……」
「すごい! 女のここって、こんな風になってるんだ」
将太はにやにや笑いながらその行為を続けた。
化学実験教室で試験管を握っていた健太郎は、ふと窓の外を見た。
中庭を挟んで向かい側に建っている芸術棟の二階、その一番端の音楽室に目をやった健太郎は小さく呟いた。「あれ、カーテンが閉まってる……」
「どうした? ケンタ」同じように白衣を身に着けた友人の修平が健太郎の元にやって来た。
「いや、音楽室だけカーテンが閉まってる」
修平も、窓の外に目をやった。「ワシオっち、律儀モンだからな。授業がない時は閉めてるんじゃね?」
「そうだったかな……ん?」
「どうした?」
「エアコンの室外機が回ってるみたいだ……」
彩友美はブラを着けたまま、破られたストッキングをそのままに顔を上げて懇願するように言った。
「しょ、将太君も脱いで……」
「は?」ズボンと下着を下げただけの姿で、いきり立ったペニスをそそり立たせていた将太は、意表を突かれたように動きを止めた。
「私、こんなレイプみたいなの、いや……」
「何言ってる? いいじゃん、レイプでも」
「将太君、お願いだから……」
将太は眉をひそめた。「何か企んでるんじゃないの? 隠しカメラとか……」
「違う、あたしはただ……」
「何だよ」
「……」
将太は肩をすくめた。「ま、いっか。教師の言いつけは守らないとね」
将太はシャツを脱ぎ、ズボンと下着も脱ぎ去って、靴下だけの姿になった。
「じゃあ、先生もブラ、外さなきゃ」将太はそう言って、彩友美のカラダに覆い被さり、腕を背中に回した。
「ああ……」彩友美はうっとりしたような声を出した。
少し手間取りながら、将太は背中のホックを外し、身を起こした。彩友美は自分でブラから手を抜いた。張りのある乳房がぷるんと揺れた。

「へえ!」将太が膝立ちのまま腰に手を当てて感心したように言った。「なかなかそそるおっぱいじゃん。初めて見たけど……」
将太は彩友美の両脇に手をつき、しばらく息を潜めてじっとしていた。
やがて、彼は彼女の顔をまじまじと見ながら言った。「な、舐めてもいい?」
彩友美は顔を赤くしてコクンとうなずいた。
将太は出し抜けに彩友美の乳首を咥え込んだ。
「んあっ!」彩友美は大声を出した。
口を離した将太はにやにやしながら言った。「やっぱ感じるものなんだな、おっぱいって」
そして再び彼はその硬く隆起した乳首を咥え込み、舐めた。時折歯で軽く咬んでみた。彩友美はカラダをよじらせ、息を荒くしていった。
「なんか、本気でエッチしてる気になってきた」彩友美から身を離した将太は、彼女の両脚を抱え込み、天を指してびくびくと脈動しているペニスを彼女の股間に宛がい、そのまま柔らかな茂みに擦りつけ始めた。
「ああ……」彩友美はカラダを仰け反らせ、喘いだ。
「何? こんなことされても感じてるの?」将太は言って、腰を乱暴に動かし始めた。
二人の荒い息の音が教室内に響いた。
「何か、いつもより感じてない? 先生……」
「しょ、将太君」
「中に入れなくても感じるものなんだね」将太はふふっと笑った。
彩友美は激しく胸を上下させて喘いでいる。
将太の腰に痺れが走った。「も、もうすぐ出る……かも」
「将太君!」
「出、出る、出るっ! ぐうっ!」
将太のペニスが大きく脈動を始め、熱く沸騰した将太のエキスが勢いよく発射されて、彩友美のヘアと白い腹に大量にまつわりついた。
その瞬間! 彩友美は腕を突っ張っていた将太の背中に腕を回し、ぎゅっと抱き寄せた。

「えっ?」将太はびっくりして身体を硬直させた。柔らかく、温かい二つの乳房が将太の胸に押し付けられ、彩友美の速く大きな鼓動がそこから将太の身体の中にまで伝わってきた。
射精の快感が次第に弱まり、将太は焦って息を整えようと身を起こしかけた。しかし、彩友美の細い腕のどこにそんな力があるのか、と思うぐらいに強く身体を締め付けられ、将太は身動きできないでいた。
「将太君、まだ、まだ離れないで……」
「せ、先生?……」将太は戸惑ったように彩友美を見つめた。その目からはいつの間にか灰色のくすみが消え失せ、元の優しく気弱な、しかし澄んだ将太の瞳に戻っていた。





































