
Twin's Story 外伝 "Hot Chocolate Time" 第2集
第7話 追憶タイム
海棠ケンジ(28)と海棠ミカ(30)夫妻は、同じ東京の保健体育系大学の出身だ。ミカの方が二学年上。当時は二人とも水泳サークルに所属していて、先輩、後輩の関係だった。
ミカが4年生だった12月から二人は交際を始め、ケンジが卒業した後結婚した。
今はケンジが生まれ育った町でスイミングスクールを夫婦で経営している。
――10月。海棠家の前の街路樹の葉も、黄色や赤に染まりかけていた。
「すっかり秋だね」
「思い出に浸るにはいい季節だ」
「浸るような思い出なんて、あったっけ? ケンジ」
「あるだろ? 君との今までの時間。いつまでも浸っていたいほどの甘い思い出だらけじゃないか」
ミカが呆れたように笑った。「本気で言ってるのか? ケンジ」
「本気に決まってるだろ」ケンジも笑った。「そうだ、今度さ、久しぶりに大学に行ってみない?」

ミカは、自分の横に座らせている4歳になる息子の龍がテーブルにこぼしたご飯粒を拾って口に入れながら顔を上げた。「いいね」
「何年ぶりだっけ?」
「ケンジが卒業してからは6年ぶりじゃない」
「そうだね」ケンジは微笑みながらビールを煽りかけ、ふと手を止めた。「んっ?」
ケンジはグラスをテーブルに置いて向かいに座った幼い息子に向かって言った。
「こらっ! 龍、食事中にママのおっぱいを触るヤツがあるかっ!」
ミカが呆れて言った。「なに言ってるの? 四歳児の息子にヤキモチやいてどうするんだ」
「ママのおっぱいー」
ミカの隣に座った龍は、構わずその小さな手でミカのバストを執拗に触ったり揉んだりし続けた。
ミカは龍の頬を両手で包みこんで優しく言った。「龍はおとなしくお留守番できる?」
「おるすばん? できるよ。マユ姉ちゃんとこ、行くもん!」龍は大声で叫び、目を輝かせた。
「あははは、おまえマユ姉ちゃん、大好きだもんな」ミカは乱暴に龍の頭を撫でた。
龍が叫んだ『マユ姉ちゃん』というのは、彼のいとこのシンプソン・真雪のことである。
ケンジには双子の妹がいる。その妹マユミは、ケンジの高校時代からの親友ケネス・シンプソンと結婚した。
ケネスの家は、この町の老舗スイーツ店『Simpson's Chocolate House』(愛称『シンチョコ』)だ。ケネスとマユミの間には、これも双子の兄妹健太郎、真雪がいて、龍より4歳年上だった。今年小学校二年生になったこの二人のいとこは、龍のことが大のお気に入りで、特に真雪はいつも龍をまるで実の弟のようにかわいがってやっていた。
★この龍と真雪は先々恋人同士になり、結局結婚してしまいます(→基礎知識『真雪と龍』)
◆
二人が在学していた大学の敷地のすぐそばに大きなスポーツショップがあった。そこはミカが卒業後勤めていた店だった。ショップの前の通りには、おしゃれな店もたくさん軒を連ねていて、休日の今日は、若者や家族連れなど、たくさんの人が行き交い、活気に溢れていた。
「おお! ずいぶん垢抜けた感じ」ミカが店内をぐるぐる見回した。
「確かに。あの頃とだいぶ変わったね」
「じゃあ、ちょっとあいさつしてくる」
「ああ、行っておいで」
ミカは『Simpson's Chocolate House』のチョコアソート大箱を手に、広い店内の奥にある事務所に足を向けた。
ケンジは売り場を眺めながら時間をつぶすことにした。
ケンジがスイミング関連商品が陳列されているエリアを歩いていると、不意に背後から声がした。
「あの、」
ケンジは振り向いた。
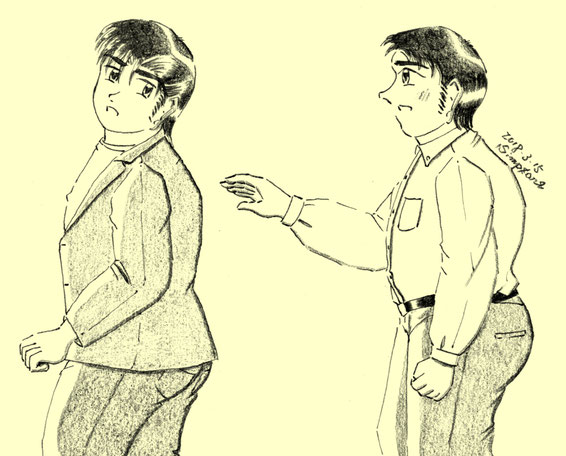
ほっそりした端正な顔立ちの男性が少し緊張したような面持ちでケンジに近づいた。自分と同じぐらいの年齢か、とケンジは思った。
「あの、」男性はもう一度そう言って、一度口ごもると、決心したように顔を上げ、ケンジの目を見つめた。「もしかして、あなたと一緒にいた女性は、兵藤ミカさん……ではないですか?」
「はい。そうですよ」ケンジは微笑みながらそう言った。
「やっぱりそうでしたか」男性は恥じらったような、申し訳ないような複雑な顔をした。
「このお店でのお知り合いですか?」
「いえ、じ、実は、僕は彼女の高校時代の先輩なのですが、」
少し意表を突かれたようにケンジは首をかしげた。「あ、そうなんですね」
「そ、その、同じ水泳部に所属していて……」
男性はまた口ごもり、うつむいた。
ケンジは、今、目の前に立っているのは、以前ミカから聞いたことがある、彼女の初恋の男性ではないか、と思い立った。
「ひょっとして、拓郎さん、ですか?」ケンジが言った。
「えっ?!」男性は驚いて顔を上げた。
「加賀拓郎先輩でしょう? ミカから聞いたことがあります」
「そ、そうでしたか……」男性は少し赤くなって頭を掻いた。「ミカ……さんが……」
「もし、お時間がおありでしたら、会ってやってくださいませんか?」ケンジが微笑みながら提案した。「お茶でも飲みながらお話でも。いかがです?」
「え? あ、そ、そうですね」
ケンジはケータイを取り出して、ボタンを押した。
「ミカは今、前にお世話になったこの店のオーナーに会いに行ってます。メールしました。僕らが今から行く喫茶店を教えましたから、二人でお話ししてる間に来ると思いますよ」
「す、すみません……気を遣って頂いて……」男性は縮こまって頭を下げた。
レトロな雰囲気の静かな喫茶店だった。ケンジとミカは大学時代、よくこの店でコーヒータイムを楽しんだものだ。当時と同じように、煎られたコーヒー豆を挽く香りと、ビル・エヴァンスのピアノが、賑やかな通りとは対照的な、どこか懐かしさを感じさせるような落ち着いた雰囲気を演出していて、ケンジはドアを開けるなり、思わず小さなため息をついた。
ビル・エヴァンス「Waltz for Debby」
二階席の窓際のテーブルに二人は相対した。秋晴れの戸外からの光が、拓郎の片頬を明るく照らした。
大学生のアルバイトとおぼしき若い男性のホールスタッフが、二人の前にホットコーヒーのカップを置いた。
「始めまして」ケンジは拓郎に手を伸ばした。「ミカの夫の海棠ケンジです」
拓郎はその手を握り返した。
柔らかく、絹のような肌触りだとケンジは思った。
「ケンジさんが僕とミカさんとの過去をご存じだとは意外でした」拓郎は穏やかな顔つきでそう言った。
「彼女からは、あなたはオーストラリアに留学して、そのまま定住された、って聞いてましたが……」
拓郎は目の前のコーヒーカップを見つめながらゆっくりと口を開いた。
「はい。その通りです。その後いっしょに留学していた女性と付き合って、結婚して、そのままシドニーに住んでいました」拓郎の言葉が詰まり、少しの沈黙があった。「でも、二年前、妻は病気で先に逝ってしまって……」
「そうでしたか……」ケンジはようやくそれだけ言って、カップを持ち上げた。
「彼女との思い出の場所に住み続けるのが苦しくて、日本に戻ってきたんです」
「今はどちらにお住まいですか?」
「はい。シドニーで勤めていた企業の関連会社が東京にあるので、そこに配属替えをしてもらって、今はこのすぐ近くに住んでいます」
「お一人で?」
「はい。子どもはいません」
「お寂しいですね……」
拓郎は顔を上げた。「いえ、会社の同僚や部下がとても賑やかだし、会社の業績も悪くないし、仕事も順調で寂しいと感じたことはあまりありません」そして笑った。
胸が痛むほどの優しい笑顔だった。
「そうですか。それは良かった」ケンジは少しほっとしてカップをソーサーに戻した。
「すみません。いきなり声をかけてしまって。驚かれたでしょう?」
「あの店で偶然ミカを見かけられて、どうでした? 高校時代からずいぶん変わっていたでしょう?」
「いえ、あの……」拓郎は焦ったように腰をもぞつかせた。「ぐ、偶然ではないんです」
「え?」
「僕、あの店でミカさんを探してたんです」
「探してた?」
「はい。彼女の通っていたここの大学を高校の時の後輩に教えてもらって、おそらく所属していただろう水泳のサークルの方に情報をいただき、ミカさんがあの店に就職していたことを知りました」
「でも、よく僕らが今日あの店に行くことをご存じでしたね」
「それは偶然です」拓郎は笑った。「丁度店の前を歩いていた時、あなた方が中に入っていくのを見つけたんです」
ケンジは少しだけ肩をすくめた。「なるほど」
拓郎は躊躇いがちに言った。
「ミカさんの最愛のパートナーであるケンジさんに、こんなことを言うのはとても失礼だと思うのですが、僕は彼女への思いが、ずっと心の奥にひっかかってた」拓郎は慌てて付け加えた。「いえ、思い、というのは、その、決してよりを戻そうとかいう意味ではなくて、あ、あの人に対する申し訳なさ、というか……」
ケンジには何となくわかりかけてきた。拓郎はシドニーに発つ直前に、付き合っていたミカと初めて肌を重ね合わせたのだ。その時、確か彼はミカにいきなり別れを告げたということだったはずだ。
★この経緯はここで語られています(Twin's Story 11 "Sweet Chocolate Time")
「僕の方から付き合ってくれ、って言っておきながら、一方的に別れを突きつけたんですから……」
「ミカは――」ケンジが穏やかな顔を拓郎に向けた。「その時はとても辛くて悲しかったでしょうけど、あなたの優しさにも触れられて、ある意味幸せだったんではないでしょうか。別れ際まであなたに大切に、優しくされたことは、今の彼女にとっては温かな思い出になっていると思いますよ」
「ケンジさん……」
「是非、ミカと会って、その思いを伝えてくださいよ。あ、」ケンジは窓の下の通りに目を落とした。「来たみたいです、ミカ」
「な、なんだか緊張しますね……」拓郎はそわそわし始めた。
拓郎は、店の一階の入り口ドアが開く音が聞こえた時、さらに落ち着かないそぶりで、手に持ったカップを少し震わせながら口に運んだ。
螺旋階段を上がってきたミカは、奥のテーブルから手を振っているケンジにすぐ気づき、近づいた。そして、一瞬立ち止まり、意外な顔をしてケンジの横に立った。「あれ、一人じゃなかったんだね。どなた?」
「まあ座れよ、ここに」
ケンジはミカを自分の隣に座らせた。
ミカは拓郎に目をやった。
拓郎はうつむいていた。
「とっても懐かしい人だよ。君にとって」ケンジは微笑みながらコーヒーカップを手に取った。
拓郎は顔を上げた。
怪訝な表情で向かいに座っているその男性を見たミカは、すぐに目を見開いて思わず立ち上がった。「たっ! 拓郎先輩っ!」
「ひ、久しぶりだね、ミカさん。元気だった?」拓郎は思いきり赤くなって右手を少しだけ挙げた。
「どっ、どっ、どういうこと? ケンジ!」ミカはひどく狼狽していた。
「ミカに会いたかったんだってさ」
「えっ? えっ? あ、あたしに?」ミカは顔を真っ赤にしてうろたえた。
ケンジは眉間に皺を寄せてミカを見上げた。「いいから座れよ、落ち着いてさ」
ミカは相変わらず目を皿のようにしたまま、ゆっくりと再び椅子に腰を下ろした。
「ミカがこんなに慌てふためくの、俺、初めて見たよ」ケンジは笑った。
カフェオレ色のポロシャツに白い前掛けをつけたホールスタッフによってコーヒーが運ばれてきて、ミカの前に置かれた。
「そ、そりゃ慌てもするよ。もう二度と会えないって思ってた人と再会したわけだし……」
「しかも初めての人、だからな」
拓郎はますます真っ赤になった。「そ、そんなことまでご存じなんですか?」
「ご、ごめんなさい、先輩、軽々しくこの人に話しちゃって……」
拓郎はふっとため息をついた。「いや、ケンジさんは知っておくべきだな……」

椅子に座り直し、背筋を伸ばして少しうつむいたまま拓郎は穏やかに語り始めた。「今更、ミカさんを身勝手に捨てた僕が、こうして再会することを考えちゃいけなかったのかもしれません。でも、そんなことをしたからよけいに貴女にお会いして、お詫びしなきゃ、って思ったんです」
「先輩……」
「ずっと心にひっかかってた……」拓郎は顔を上げた。
「あたしも、」ミカがカップの載せられたソーサーの縁を指でなぞりながらうつむき加減で言った。「先輩にはもう一度お会いして、お礼を言いたかった。今になってこんなことを言い出すのもわざとらしいけど……」
「お礼?」
「あたしを真剣に想ってくれてたことに対する、お礼」
ミカは静かにカップを持ち上げた。
「あの、」ミカが一口コーヒーを飲んだ後、顔を拓郎に向けた。「先輩はどうしてこんなところにいるんですか? オーストラリアからいつ帰って来られたの?」
「ああ、」拓郎は目を伏せた。
ケンジはちらりと拓郎とミカを見比べた。
「シドニーでいっしょに暮らしていた妻が二年前に他界して、今はこの近くに住んでいるんです」
「えっ?!」ミカは口を押さえた。「な、亡くなった?」
拓郎は小さなため息をついて独り言のように呟いた。「貴女によく似た女性でした」
「え? あたしに?」
拓郎は涙ぐんでいた。「彼女を忘れたくても忘れられない。一人、あっちで暮らしていても、その思いは強くなるばかり。耐えきれなくなって帰国したんです」
「…………」
拓郎は顔を上げて右目を照れたように拭った。「でも、もう二年前のことです。早く思い出にしてしまわなきゃね」
ホールスタッフが、テーブルに近づいてきた。
「お冷やのお代わり、いかがですか?」
「あ、いただくよ。それから、」拓郎がメニューを手にして、そのスタッフの若い女性に目を向けた。「このケーキを三つ、持ってきてくれないかな」
「かしこまりました」
拓郎はミカとケンジに向き直った。「ミカさんに再会させてくださったお礼です。食べてください」
「そ、そんな気を遣わないでください、先輩」ミカが恐縮したように言った。
「こんなお店で、こんな風に、貴女とデートしたかったです」拓郎は恥ずかしそうに笑った。
「お互い部活で忙しかったですからね」ミカも微笑んだ。
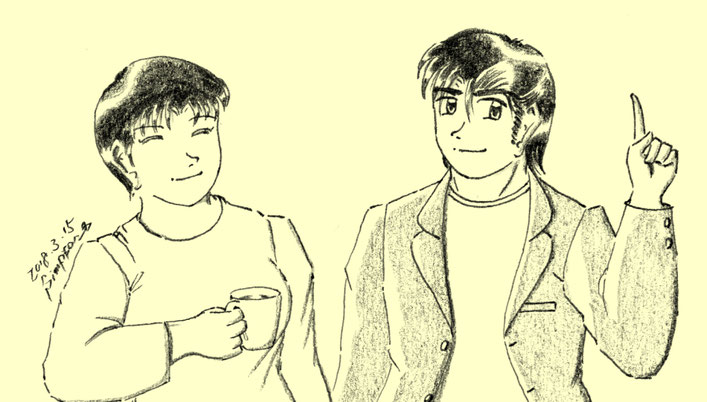
しばしの沈黙の後、ケンジがゆっくりと口を開いた。
「今夜、拓郎先輩と二人きりの夜を過ごしたらどうだい? ミカ」
「え?」ミカはカップを口から離してケンジを見た。
ケンジはかすかにうなずいてミカの目を見つめ返した。「募る話も、心の奥にしまってある思いもたくさんあるだろ?」
「そ、そんなことできません」拓郎が慌てて言った。「あ、あなたの大切なミカさんと二人きりになるなんて……」
「拓郎さんの、そのお人柄を見る限り、世間一般の者や貴男自身が心配するようなことにはならないと思いますよ」
「え?」
「今のミカは、僕の妻であることを忘れて、貴男との時間を過ごすことはありません。これは断言できます」
「ケンジ……」ミカが少し潤んだ目で横に座った夫の顔を見た。
「それが間違いないから、僕は貴男とミカが一夜を過ごすことを勧めているんです。その時、もし、思いが高まったら、身体を重ね合ってもいいじゃないですか。高校時代のように」
「ええっ?!」拓郎は大声を出した。
「僕らはもう、そういうことを乗り越えています。セックスは言葉にはできない思いを伝えたり、安らぎや癒しを与え合うものだって知っています。そしてそれは夫婦や恋人だけの特権ではないと僕もミカも解っています」
「で、でも、そ、そんなこと……」
「大丈夫」
「素敵」ミカも言った。「先輩、おつきあい頂けませんか?」
「ミ、ミカさんまで!」
「あの時みたいに、『ミカ』って呼んでください」
「えっ? えっ!」
「あたし、あの時先輩に伝えたかったこと、山ほどあるんです。是非」ミカは目を輝かせた。
「きっ、君たちは一体どういう夫婦なんですかっ!」
ケンジは拓郎にウィンクをした後ミカを見て微笑んだ。「じゃあミカ、先輩との今日の夕食の場所と時刻を、今ここで決めといたら?」
「そうだね」
「え? あ、あの……」拓郎はもはや言葉を失い、おろおろするばかりだった。
拓郎はミカとの約束を確認して、先に喫茶店を出て行った。拓郎の前のケーキは半分しか手がつけられていなかった。
ケンジは店を出て窓の下の通りを小走りで駆けていく拓郎を目で追った。
不意にミカはケンジの手を取った。
ケンジはミカに顔を向け直した。
「ほんとにいいの? ケンジ」
「何が?」
「あたしが先輩に、もしかしたら抱かれちゃうこと」
「うーん……」ケンジは困ったように目を閉じた。
「やっぱりいやでしょ?」
「おもしろくはない」
「何よ、それ」
ケンジはミカに身体を向けた。
「俺、君のことを疑ってるわけじゃないし、君が今更脇目もふらず先輩に突っ走ることはないって信じてる。だからさっき彼に言ったことは本心なんだ」
「もしかして、」ミカは両手でテーブルに頬づえをついて言った。「あなたが妹のマユミさんと、今も年に一度逢って愛し合ってるってことが引っかかってる? あたしに対して負い目を感じてるの?」
ケンジは軽く肩をすくめた。
「それはないと言えば嘘になる。俺だけそんな都合のいい思いをしてる、ってことは、やっぱり引っかかってる。だから君が先輩に流れで抱かれることになっても、俺にはそれを責める権利はないと思うんだ」
「おあいこ、ってこと?」
「乱暴な言い方をすればね」
――ケンジと彼の双子の妹マユミとは、実は高校二年から二年半程の間、実質恋人同士だった。強く想い合い、熱く繋がり合っていた二人だったが、兄妹で結婚できない現実に、ケンジが大学一年の冬に泣く泣く別れた。
その後ケンジは大学の先輩ミカと、妹のマユミはケンジの親友ケネスと結婚したが、ミカもケネスもケンジたち兄妹の繋がりを断ち切ったりはしなかった。二人の、兄妹を超えた強い絆と熱い想いを大切にするべく、毎年8月初めに一夜だけ、二人が高校時代のように愛し合うことを勧めていたのだった。
「でも、ケンジがマユミさんを抱くことについては、あたしに対して負い目を感じて欲しくないな」
「え? そうなのか?」
「うん。だって、マユミさんを抱くこと、って、あなた達の癒しや安らぎを求めてのことでしょ? ケンジもさっき言ってたじゃない」
「そうだけどさ」
「それって恋愛感情とは別物でしょ?」
「まあ、そうだね」
「だからマユミさんとケンジが抱き合って繋がり合うのを、あたし嫉妬したりしてないよ」
「じゃあ、俺も同じ。ミカが先輩に抱かれても嫉妬する気持ちにならないと思うよ」
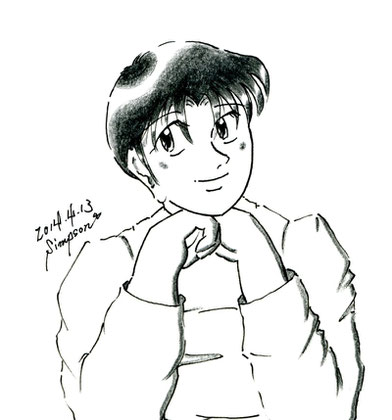
ミカはにやりと笑って言った。「ほんとにそう断言できる? 明日、ケンジが嫉妬に狂って、あたしや先輩を刃物で切りつけたりしない、って保証できる?」
ケンジは指を組んで、そこに顎を載せた。「あの加賀拓郎っていう男性と話してて、何となく感じることがあるんだ」
「感じること?」
「あの人が本当に望んでいるのは、君に会うこととは別のことのような気がする」
「え? どういうこと?」
「拓郎さんは、君に亡くなった奥さんを重ねてるんだ。たぶん」
「重ねてる? あたしに?」
「先輩自身も言ってただろ? 君によく似た奥さんだったって」
「そうだね」
「彼はもがいてる。過去の呪縛から解き放たれたくて、もがいてる。そんな風に見える」
「呪縛……」
ケンジは指をほどき、右手の親指を立てて自分を指さした。
「俺が同じ立場だったら、亡くなって二年も経つ奥さんへの想いに縛られて生きることは苦痛だよ。そりゃあ熱烈に愛していた奥さんだったろうから、そう簡単に忘れられるわけはないと思うけど、同じ彼女への想いでも、彼が新たに歩き始めるのを妨げるような気持ちは、彼自身早く手放したいって思ってるはずだ」
「何となく……わかる」
「それに、」
ケンジは一度言葉を切ってミカを見た。
「あの人は偶然って言ってたけど、先輩、君に会おうとした手段を選んでないよ」
「え? どういうこと?」
「この近くのアパートに住んでる、って言ってた。でも君が勤めてたあのショップの近くに偶然アパート借りるかな。彼の会社もこの近くにあるとは思えないし」
「確かに……」
「ショップの近くどころか、店の目の前のアパートに住んでると俺は踏んでる。ショップの入り口が窓から見える部屋に」
「あるね、アパート。確かに」
「その窓からいつも下を見ながら、いつか君がまたショップを訪ねてくるのを待ち続けていた。そんなところだね」
「そこまで?」
「信じられないぐらい気の遠くなるような無謀な賭けだけどさ」
「そうだよね」
「とにかく、どうしても君に会いたかった。会ってどうする、というより、会えば奥さんへの想いもいっしょに過去の記憶に変えてしまえる、そう思ってたんじゃないかな」
「記憶……」
「後で聞いてごらんよ、先輩にさ」
ケンジはカップを手に取った。
「もう一つ。これは単なる想像だけど、あの人、今、気になっている女性がいるような感じがする」
「え? そうなの?」
「って、断定するわけじゃないよ。あくまで想像だよ。ただ、彼の複雑な表情を見てると、今、彼がいろんなことを思いながらもがいているってことはわかる」
「ケンジって、人の心を読むのが得意だったんだね」
「そんなんじゃないよ。ただ、あの人の考え方、感じ方って、俺にちょっと似てる気がする。行動とか」
「やっぱり抱かれない方がいいんじゃない? あたし、あの人に。迷ってる先輩を混乱させたりしないかな」
「いや、もし、俺の考えている通りだったら、かえってミカは先輩に抱かれるべきだね」
「どうして?」
「彼は君を抱いて、心の奥にずっと残っていた想いを全部はき出すことで、亡くなった奥さんへの未練も断ち切れるんだよ」
「あたしの立場は?」
「ミカにも先輩への伝えられなかった想い、ってものがいっぱいあるだろ? それはそれで彼に伝えて、君自身がすっきりしなきゃ」
「そうだね。それは実現させたい」
「彼は君のその想いを受け取って、君との関係を本当の意味で精算するのと同時に、おそらく奥さんへの想いにも区切りがつけられるはずさ」
「そんなものなんだ……」
「だから俺は今夜のことについては何も言わない。君も拓郎先輩も後に引きずらないことがわかってるから」ケンジはコーヒーを飲み干してソーサーに戻した。「今度こそ、きっと本当の意味での最後の夜になるよ。君と拓郎先輩との。だから遠慮なく行っておいで」
「うん。そうだね」ミカは穏やかに微笑んだ。「ありがとう、ケンジ」
「でも、」ケンジは横目でミカを見た。
「え? 何?」
「毎年俺が妹のマユとの夜を過ごした明くる日は、君からきっちりいたぶられているから、俺もそうする」
「いたぶってるか?」
「いつも俺は、明らかに嫉妬している君から攻められてるじゃないか、この夏もなかなかイかせてくれなかったし、去年なんか何度も、尽きるまで無理矢理イかせただろ」
ミカは笑った。「そのぐらいは覚悟しなきゃ。あたし以外のオンナと繋がったわけだし」
「だろ? だったら明日、俺は君をたっぷりいじめてもいいってことだろ?」
「今夜、拓郎先輩とあたしが繋がるって、まだ決まったワケじゃないのに?」
「間違いなく繋がるね」
「何よ、その自信」
「繋がろうと繋がるまいと、結果は同じ。明日、俺はきっちり君をいたぶらせてもらうから」
「ううむ……覚悟しとかなきゃいけないか」
「うん。覚悟しときな」





































