Twin's Story 11 "Sweet Chocolate Time"
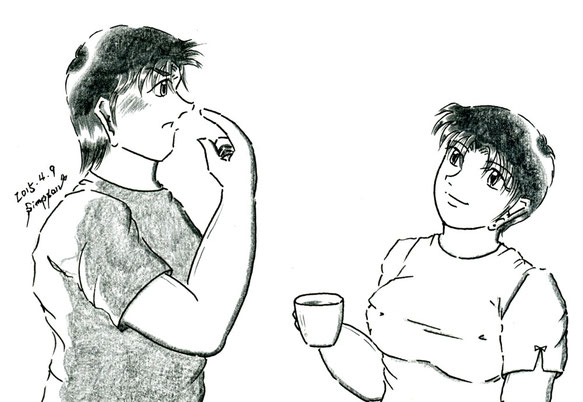
《1 陽子への癒し》
「だから、あたしが許すから、抱いてやってよ、陽子をさ」ミカが言った。
ケンジは困惑した表情で言った。「おまえな、普通は自分の夫が他の女性を抱くことを嫌うもんだろ? 場合によっちゃ、離婚モノだ」
「だから、あたしは心が広いから大丈夫だってば」
「いや、心が広い、とか、そんなことは関係ないだろ、だいたい、」
「何? 今日はえらく突っかかるね。どうして?」
「どうしてもこうしてもあるかっ! それが世間の常識ってもんだ」
「ケンジの口から常識云々のコトバが出てくるとは思わなかったね。特にことセックスに関して」
「な、なんでだよ」
「実の妹を抱いてたじゃん」
「そ、それは……」ケンジは言葉を詰まらせた。
ミカはふっとため息をついた。「ごめん、ケンジ」彼女は口調を和らげ、ケンジの手を取って優しく言った。「無神経な言い方だった」
「え?」
「あなたの言う通り。あたしはあなたの愛する妻だよね」
「そ、そうだよ」ケンジは少し赤面して言った。
「セックスは心と身体を癒す行為。そして夫婦の絆を確認する作業」
「そうだよ。わ、わかってるじゃないか、ミカ」
「それはそれでいい。あたしはケンジとのセックスに満足してるし、愛されているっていう実感もある」
「それで十分だろ」
「でも、そんな恵まれたあたしと違って、陽子はそうじゃない」
「…………」
「例えば、」ミカは少しケンジに身を乗り出して言った。「オトコだったら、風俗に行ったりできるでしょ?」
「ふ、風俗?」
「ケンジも何度かあるはずよ」
「……」
「そんなことで怒らないよ、あたし。それってオトコの生理だからね。だから、その時どうだったかとか、詳しいことを訊くつもりもない」
「でも、俺、とっても罪悪感があった、おまえに対してさ」
「お金払ってやったんでしょ? それに、そのコに愛情を感じてた?」
「愛情なんてないよ。単に身体を満足させただけだからな」
「でしょ? だったらあたしがあなたを責めることでもないじゃない」
「そりゃそうだけど……」
「でも、女はそういう機会がほとんどない。ホストクラブなんて妖しすぎて行く気もしない。第一、オトコ相手の風俗と比べて敷居が高すぎるよ」
「確かに……」
「かといって、安直に不倫なんてなかなかできるもんじゃないし。ローリスクでそうそうカラダの火照りを鎮めてくれるような人はいるもんじゃない。そうでしょ?」
「そうだよな」
「オトコはオンナと見るやすぐに抱きたくなるもんだけど、だからといって、見ず知らずの、行きずりのオトコなんかに陽子を抱かせたくないんだよ、あたし」
「ミカ……」
「あなたはオトコだから理解しづらいかもしれないけど、ずっと一人身の陽子みたいなオンナは、たとえ恋人の関係でなくても、心を許せる誰かに抱かれて癒されれば、きっと幸せな気分になれるはず。そんな人に陽子を抱かせてやりたいんだ」
「……」
「誰の助けも借りることなく一人ぼっちでしゃかりきになってがんばって、夫の忘れ形見の夏輝を大切に育て上げて、立派に社会に送り出したじゃない。自分がオンナであることを封印してまで……。あたし、そういう陽子が不憫なんだ」
「お、俺が、彼女を癒す?」
「陽子が心を許せる相手って言ったら、今のところあなたしかいないでしょ?」ミカは微笑んだ。「あたしが後ろにいるから大丈夫」
「で、でも万一陽子先輩がそれから俺に惚れ込んで、おまえから奪おうなんて考えたりしたら、」
「そうならないようにするのも、あなたの役目でしょ?」
「ええ? な、なんだよそれ」
「陽子なら大丈夫だと思うよ。それより、ケンジこそ陽子の身体が病みつきになる可能性もあるね」
「そうなったらどうする? ミカ」
「しょうがない。ケンジを陽子に譲って、あたしは時々ケネスに抱かれて癒されよう」
「冗談止めろよ」ケンジは苦笑いをした。
「愛のないセックスは不毛だけど、癒やしのセックスはあってもいいと思うけどね」
「癒し……か」
「常識的な大人なら、わきまえるはずだよ」
「そういうもんかな……」
海棠ケンジ(44)は、現在の妻ミカ(46)とは大学の水泳サークルで知り合った。同じ水泳サークルに所属していた日向陽子(46)はミカの同級生で親友だったが、大学3年生の時、ある男性と恋に落ち、大学を退学して駆け落ちした。
陽子はすぐに男性の子を身体に宿したが、その子が生まれた日に、陽子はその最愛の彼を交通事故で失ってしまう。それから彼女は女手一つでその子――夏輝と名づけられた娘――を育て上げたのだった。
◆
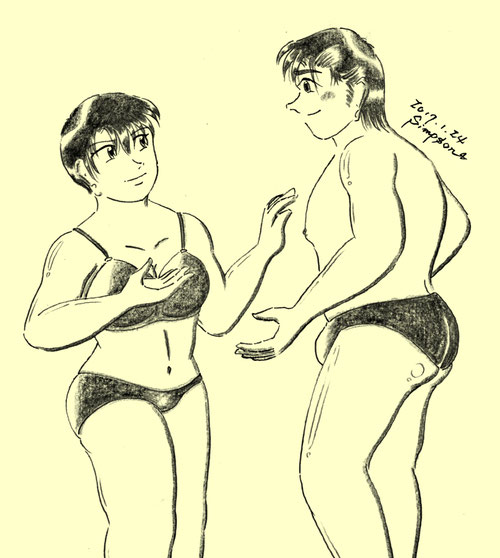
「よ、陽子先輩……」ケンジはすでに赤くなっている。
ここは街中のシティホテルだ。
質素な白い壁に囲まれた部屋のダブルベッドの縁に腰掛けて、陽子が少しはにかみながら言った。「ケン坊、ありがとうね。それからミカにも」
「は、はい」
「始めに誓おう。あたしはケン坊とセックスしても、それ以降は引きずらない。ケン坊も誓って」陽子は目の前に立ったケンジの手を取り、立ち上がった。
「え?」
「どんなことがあっても、ミカを悲しませるようなことに発展させない」
「で、でもそれって、やってみないとわからないでしょ?」
「大丈夫だよ。あたしけっこう淡泊だから。ケン坊がまた抱きたいとは思わないよ、きっと」陽子は笑った。「それに、もしケン坊があたしの身体が忘れられなくなったりしたら、ミカの親友のあたしが許さない」
「いや、陽子先輩、あなたその本人だから」
「レクレーション。気晴らし。気分転換。その程度の軽さでいいんじゃない?」
「そ、そうですね」
「でも、遊びはイヤ」
「もちろんです。俺、陽子先輩を遊びで抱くつもりはないから」
「気晴らしこそ、やるときは真剣に」
「わかってます」ケンジは陽子のブラに手をかけた。そして指を滑らせ、背中のホックをそっと外した。陽子の乳房がぷるん、と解放された。
「陽子先輩の乳首、きれいなピンク色ですね」
「嬉しいこと言うじゃん、ケン坊」陽子はケンジの首に腕を回した。ケンジはそっと陽子の唇に自分の唇を合わせた。メントールの煙草の匂いが彼の口の中に流れ込んだ。
「んんっ……」陽子は甘い呻き声を上げた。
口を離してケンジは微笑みながら陽子の目を見つめた。
「陽子先輩、今でも煙草、吸ってるんだ」
「あ、いやだった? ケン坊。ごめん。もっとしっかり歯磨きしとけばよかったね」
「平気ですよ」ケンジは微笑んだ。「歯磨きしてもミントの香りがしますからね。あんまり変わらないでしょ」
「ケ、ケン坊……」陽子は潤んだ目でケンジを見つめ返した。
「はい?」
陽子は出し抜けにケンジに抱きつき、両手で頬を押さえて、自分の口を彼のそれに押し当てた。
「んぐ……」ケンジは思わず目を見開いた。
陽子の舌がケンジの唇を割って侵入した。ケンジはそれに応え、柔らかく自分の舌先でその熱く火照ったものを慈しんだ。
がくがくっ!
陽子はその場にしゃがみ込んだ。そして大きく息をしながら胸と股間に手を当てた。
「よ、陽子先輩!」
ケンジは慌てて彼女の身体を抱きかかえた。
「だ、大丈夫ですか? 気分でも悪いんですか?」
陽子は顔を上げて、照れたように頬を赤く染め、ケンジを見つめた。
「ケン坊……。もうあたし溶けちゃいそうだよ……」
「え?」
陽子はゆっくりと立ち上がった。
「ケン坊のキスは、身体に毒だ」
「ご、ごめんなさい、気持ち悪かったですか?」
陽子はふふっと笑った。
「ううん。違うよ。逆だよ。最高に気持ちいいキスだ、って言いたかったんだよ」
「そ、そうですか?」ケンジも頬を染めた。
「あたし、もうすでに臨界点に達してる。どうしてくれるんだ」
陽子は悪戯っぽく笑って、ケンジをベッドに押し倒した。
陽子はベッドに仰向けになり、横になったケンジの手を取った。「責任とって、ケン坊」

ケンジは身体を起こし、陽子の身体に覆い被さると、いつもミカとのセックスの時にそうするように、片手でひとつの乳房を優しくさすりながら、唇をうなじから鎖骨を経由させてもう一つの乳首に到達させ、すでに隆起している蕾を咥え込んだ。「あ、あああ……」
ケンジは時間をかけてていねいに彼女の二つの乳房を舌と唇と指で刺激し続けた。「んんっ……」愛らしい呻き声を上げて陽子は喘いだ。「気持ちいい、ケン坊……」
陽子の手がケンジの黒い下着に伸ばされた。ケンジは陽子の身体を抱えて自分が下になった。
口を離した陽子が言った。「ケン坊って、口に出して果てるのが苦手なんだって?」
「絶っ対イヤですっ! 俺、陽子先輩の口に出すなんて、絶対しませんからねっ!」
「そんな力いっぱい拒絶しなくても……」
「ミカはそんなことまで言ったんですか?」
「うん。教えてくれた。でも大丈夫。そんなことさせないよ、ケン坊」陽子はそういいながら口をケンジの秘部に近づけ、ゆっくりと彼のビキニの下着を脱がせた。「んっ……」ケンジが小さく呻いた。
「思春期の少年じゃないんだし、ケン坊、あっという間に出したりしないでしょ?」陽子はふふっと笑った。
手でケンジのペニスを優しく握った陽子は、舌をそっと這わせ始めた。「あ、ああ、よ、陽子先輩……」
「ふふ、何だか大学時代に戻ったみたい。先輩って呼ばれるの、今でも悪くないね」陽子はゆっくりとケンジのペニスを口に咥え込みゆっくりと味わい始めた。
「んあ、あああああ……」少しざらついた舌の感触に、いつもとは違う熱さを感じ、ケンジは思わず身体を仰け反らせた。そして陽子の口の中でケンジのペニスはぐんぐん大きさを増していった。
ケンジは全裸になった陽子の秘部に顔を埋めた。そして唇と舌を使って谷間と小さな粒を刺激した。陽子は急に激しく身体を波打たせ始めた。「あ、ああっ! ケ、ケン坊、いい、いいっ!」
ケンジはその行為を長いこと続けた。やがて陽子の全身に汗が光り始めた。「来て、ケン坊、あたしに入れて」
陽子の秘部から口を離したケンジが言った。「あこがれの陽子先輩と繋がれるなんて、すごく光栄です」
「嘘でも嬉しい、ケン坊」陽子の秘部からはもう豊かに雫が溢れ始めていた。
ケンジはペニスの先端を谷間にあてがい、ゆっくりと挿入し始めた。「あ、ああああ!」
「痛くないですか? 陽子先輩」
「少しだけ……。長いこと使ってなかったからね。でも処女の頃を思い出して、かえって燃える。大丈夫、ケン坊、遠慮しないで入れて、奥まで」
「我慢できなかったら、言ってくださいね」
「入れて欲しくて我慢できない。早く入れて!」
ケンジはゆっくり、ゆっくり陽子の中に入っていった。そして二人の身体は深いところで繋がり合った。
「ああ、いいよ、ケン坊。もう大丈夫、痛くない、とっても気持ちいい、動いて、いっぱい動いて!」
「はい」ケンジは腰を大きく動かし始めた。「んっ、んっ、んっ!」
陽子は胸に、首筋に、額に汗を光らせ、目を固くつぶって、その細く白い体躯を捻らせ喘いだ。
ケンジは陽子の背中に腕を回して強く抱きしめながら左耳に熱い息を吹きかけた。
「ああああ……いい、カズ、いいよ、あたし、も、もうイくかも、あああああ……」
「陽子」ケンジは甘く囁いて、その耳たぶを柔らかく咬んだ。
「あああっ! カズ、カズっ!」
陽子もケンジの背中をきつく抱きしめながら大きく身体を波打たせた。
「カズ、先にイかないで、いっしょに、一緒にイって! お願い」
「陽子! 陽子っ!」ケンジが叫んだ。
「カズ! カズっ! あああああ!」
「う、うううっ……」ケンジの腰の動きがさらに激しくなってきた。
「も、もうイってる! あたし、イってるから、あなたも早く来て! カズ、カズーっ!」
「ぐううっ!」ケンジの身体の奥深くから一気に噴き上がったものが陽子の中に解放された。
「ああああああーっ!」陽子が叫んだ。
「んああああああっ! よ、陽子っ!」
「カズ、カズーっ!」がくがくがくがく! つながり合った陽子とケンジの身体が同じように大きく痙攣した。
「ケン坊、どうもありがとう。とってもよかった……」陽子は少し涙ぐんで言った。
「陽子先輩を満足させられたかな」ケンジは今さらながら照れたように頭を掻いた。
「うん。満足したよ、あたし。ミカって幸せだね。こんな素敵な人をダンナにできて」

「カズって、旦那さんの名前ですか?」
「ごめんね、ケン坊。あなたに抱かれながら、他の人の名前呼ぶなんて、無礼千万だよね」
「とんでもない。かえって俺も安心です。その方が」
「なんで?」
「だって、イく時、俺の名前呼ばれると、ホントに恋人か愛人のように錯覚しちゃいますもん。陽子先輩が違う人を想像しながらイってくれれば、俺も背徳感をあまり感じずにすみますからね」ケンジは笑った。
「ダンナの名前は一樹。あたしはカズって呼んでた。ケン坊の愛し方、カズに本当によく似てる。あたしの耳が感じやすいって、ケン坊、知ってたの?」
「え? いいえ」
「カズは、もうすぐって時に必ずあたしの耳に息を吹きかけて耳たぶを咬んでた」
「そうなんですか?」
「ケン坊にもそういうところがあったんだね」
ケンジは陽子と繋がったまま、静かに横になった。
「でも俺、そう言えば今までセックスの時、相手の耳を咬んだりしたこと、なかったな」
「そうなの?」
「はい。記憶にある限りでは」
「なんで今やってくれたの?」
「俺にもよくわかりません。何でかな……」
「それに、陽子って呼ぶ声もカズにすっごく似てた。ケン坊の今の声と違ってたよ。まるでカズが貴男に乗り移って、本当にあたしを愛してくれてるみたいだった。実際乗り移ってたのかもね」陽子はひどく嬉しそうに笑った。
「陽子先輩……。良かったですね」ケンジはしんみりと言った。「一樹さんに久しぶりに抱かれて、本当に、本当に良かったですね……」ケンジは涙ぐんだ。
「なんでケン坊が泣くんだよ」
「ご、ごめんなさい。変ですね、俺」
陽子はケンジの涙をその細い指で拭った。拭いながら陽子の目にも揺らめくものが宿り始めた。
「あの頃の胸の高鳴りが鮮やかに蘇ったよ」陽子の目に溜まっていたものがほろりとこぼれた。「ほんとにありがとう、ケン坊。あたしにまた甘い夢をみさせてくれて……」
今度はケンジが陽子の頬の涙を指でそっと拭った。「シャワー浴びます? 先輩」
「ううん。もうちょっと抱いててもらってもいい? ケン坊」
「もちろん、いいですよ」ケンジは微笑んだ。そして陽子の背中に腕を回した。
「あたしね、それでもカズとは、あんまりセックスしなかったんだよ」
「そうなんですか?」
「彼、あんまり積極的じゃなかったからね」
「そうなんだ」
「でも、あたしはあの頃セックスでしか二人は繋がり合えない、って思い込んでて、毎晩のようにカズを求めたんだよ」
「彼は応えてくれましたか?」
「うん。いつもってわけじゃなかったけど、彼なりにね。でも、すぐに妊娠しちゃって……。彼はとっても喜んでくれてたけど、内心どうだったのかな」
「え?」
「これであたしと離れることができなくなった、って残念な気持ちもあったかもしれないね」
「そ、そんなこと……」
「もっと遊びたかっただろうしさ」
「一樹さんは陽子先輩を愛してたんでしょ?」
「もちろん、あたしはそう思ってる。そう信じたいよ……」
「大丈夫ですって。だって、さっきから俺、なんか上の方から誰かに睨まれてるような気がずっとしてる」
「うそー」陽子は笑った。
「陽子先輩にはナーバスな雰囲気は似合いませんよ」
「それって、褒めてんの?」
「褒めてます。当然です」
「あたし、ずっと彼に負い目を感じてきた。亡くなった後もね。その罪滅ぼしに夏輝を育ててきたようなものかもしれない」
「夏輝ちゃん、立派に育ったじゃないですか。自慢の娘でしょ?」
「そうだね。素敵な彼もいるしね」
「修平君とは?」

「実はね、」陽子は嬉しそうにはにかみながら言った。「あの二人、間もなく結婚するような気がする」
「えっ?! そうなんですか?」
「よく続いたもんだよね。高校三年生からつき合い始めて、何度も危なくなったらしいけどさ。こないだ修平くん、あたしにこっそり会いに来てさ、『夏輝は金属アレルギーなんかありませんよね。』って聞くんだ」
「アレルギー?」
「指輪を考えてるってことでしょ?」
「なるほど、そりゃめでたい!」
「そのうちあの子たちが結婚を決めたら、正式にケン坊んちにあいさつに行かせるからさ、そん時はよろしくね」
「え? なんでうちに正式に……」
「聞いたよ、夏輝たち、あなたたちにエッチの仕方を習ったそうじゃない」
「そ、それは……。す、すみません、陽子先輩。軽々しくそんなこと教えちゃって……」
「まったく、子どもでもできてたらどうしてくれたんだ」
「ごっ、ごめんなさいっ!」
「でも、あたしは人のこと言える立場じゃないね。あ、抜いちゃだめ! 抜かないで、ケン坊」
ケンジのペニスが陽子から抜けそうになり、陽子はとっさに腰を押し付けた。「お願い、もう一回……。だめ?」
「一樹さん、いいですか?」ケンジが天井に目を向けて言った。
「許すってさ」陽子が言った。
「ほんとですか?」
「今度は乗り移ったりしないから、俺の代わりにおまえが陽子を癒してくれ、って言ってるよ」陽子はケンジの両頬を両手で挟み込んで言った。「ただ、ちゃんとイかせなきゃ、ただじゃ置かないってさ」
「わかりました。俺、がんばります」
「今度はケンジって呼ぶね。イく時」
「えー、そんなことしたら俺、先輩にのめり込んじゃいますよ」ケンジは笑った。
「だから、そんなことミカの親友のあたしとカズが許さないってば」
「お手柔らかに」
ケンジは再び陽子を仰向けにして覆い被さり、彼女の脚を開かせて、腰を動かし始めた。ケンジのペニスはまた次第にその大きさを増してきた。「んっ、んっ、んっ……」「ああああ、ケン坊……」





































