Twin's Story 11 "Sweet Chocolate Time"

《3 満を持す》
「で。どうだった? ケンジ」数日後、ミカが訊いた。
「え? 俺に訊くか?」
「だって、あなた当事者じゃん」
「そ、そうだけどさ」
「陽子の身体で満足できた?」
「う、うん。満足した」うつむいて少し赤くなっていたケンジはすぐに目を上げた。「で、でも、オトコだからな。イけばいつでも満足するもんだよ」
「言い訳じみてる」ミカがいたずらっぽく微笑んだ。「陽子、とっても良かった、心から癒されたって言ってたよ」
「な、なんだ、先輩からもう聞いてたんじゃないか。からかうなよ、まったく……」ケンジはコーヒーカップを手に取った。
「そうそう、」ケンジはカップをテーブルに戻しながら言った。「陽子先輩のだんなって、一樹さんって言うらしいけど、あの時、どうも彼、俺に乗り移ってたらしいんだ」
「はあ?!」ミカは大声を出した。「何なの? それ」
「おまえに訊くのもなんだけどさ、俺ってセックスの時、おまえの耳を咬んだりしたことないよな」
「たぶん……。そう言えばされたことないね、ケンジからは。ケネスにはあっちこっち思いっきり噛みつかれるけど」
「あいつはセックスの時は野獣だから、対象外だ」
ミカは笑った。「そうだね。でも何でそんなこと訊くの?」
「俺、陽子先輩の耳に息吹きかけて、耳たぶを咬んでイかせたらしいんだ」
「らしい、って何よ。他人事みたいに」
「いや、俺、その時そんな自覚がなかったし、とても自発的にやったとは思えないんだ」
「ふうん、何だか不思議な話だね」
「だろ? 一樹さんって、陽子先輩を抱く時は、いつもそういうことやってたらしいんだ」
「陽子、喜んでたでしょ」
「うん。涙ぐんでた」
「やっぱりね。あたしが言ったとおり、ケンジが抱いてやるべきだったんだよ、陽子をさ。一樹さんもそれを認めてくれたってことじゃない?」
「そうなのかな……」ケンジはカップを再び手に取った。
「あなたの陽子を思う純粋な気持ちが通じたんじゃないかな」ミカは穏やかに微笑んだ。
「俺もその時、一樹さんのことを話しながらはしゃぐ陽子先輩を見て、思わず涙ぐんでた」ケンジの目は少し潤んでいた。
照れたように目元を指先で拭うケンジを見て、ミカは優しい目を、前に座ったその夫に向けて言った。「あたし、ホントにいい人と結婚した。心からそう思うよ」
「な、何だよ、急に」
「あたし、ケンジと結婚できて、本当に良かった。あたしにはもったいないぐらいだよ」
「や、やめてくれよ。何だよ、今さら……」
「ケンジは、あたしと結婚して良かった?」
ケンジはその視線をミカの頭上に向けて穏やかに言った。「人生の中で、その選択に誤りは無かった、って自信を持って言える出来事があるとすれば、俺、ミカと結婚して龍を授かったことだと思う」
「そうか……」
「俺の大人の入り口に立ってたのはマユだけど、あいつが招き入れてくれた本当の大人の世界にはミカ、おまえがいた」
「何なの? その喩え」
「人の成長って、やっぱり人との出会いと温もりがガイドしてくれるような気がするよ。心から癒してくれる人、抱いてて心地よい人、」
「それに、抱かれて心地よい人」
「ミカ……」
「龍もいずれ、結婚するわけだけどさ」
「うん」
「手前味噌かもしんないけど、真雪はきっと幸せになれると思うよ」
「俺もそう思う。龍は中学の時虐待を受けたり、恋人が他人に寝取られそうになったりして、誰よりもつらい思いをしてたはずだけど、ちゃんと乗り越えてきたからな……」
「そうだね。身体ごと真雪に飛び込んでいくし、精一杯手を広げて真雪を受け止められる。そして自分の想いをストレートに伝えてる。何にも嘘をついてない。そういう子だね」
「うん。そんな子だ」
「あたし、彼が息子でいてくれることが、すっごく嬉しい」
「俺も。龍が息子だっていう実感が、今になって湧いてきた。本当にいい男に成長してくれたよ。ミカ、おまえのお陰」
ミカは目を細めて言った。「染色体は半分ずつ。ケンジとあたし」
◆
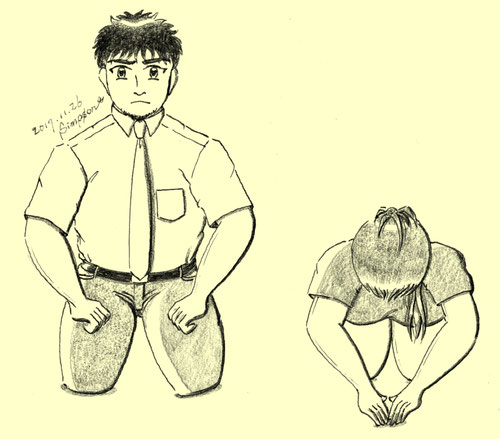
「ミカさんっ!」
「ケンジさんっ!」
修平と夏輝はいきなりアポなしで海棠家を訪ね、ソファの前の床に正座をして頭を床にこすりつけた。
「おまえら、全然成長してないな。あの時と同じじゃないか」ミカが呆れて言った。
「今度は何のお願いなんだ?」ケンジが二人をソファに座らせた。
「これっ、ミカさんの好きなビールですっ」修平がスーパーの袋に無造作に入れられた6缶入りのビールを差し出した。
「それから、これ、」夏輝は紙袋を差し出した。「コーヒーです。ケンジさんに買ってきました。どうぞ、お召し上がりください」
「あ、ありがとよ」ミカはそれを受け取った。
「なに気を遣ってるんだ、二人とも……」
修平がひとつ咳払いをして静かに口を開いた。「お、俺たちついに結婚します。7年に亘り交際を続けて行く中で、いろいろと紆余曲折もございましたが、最終的にこいつと一緒でなきゃ俺の人生は先に進まないことに気づきました次第です。つきましては公私共々大変、深くお世話になりましたあなたがたご夫婦に是非、俺たちの結婚式にあたってご媒酌の労を執っていただきたく、」
「断る」ミカがあっさりと言った。
「そ……」修平は顔を上げて絶句した。
「やだね。そんなの」
「や、やだね……って、ミカさん、そんな……」
「つまんないよ、今ドキ『ご媒酌人』だの、何だの」
「で、でも……」
「わかってる。わかってるんだ、あたしも」ミカが優しく修平に目を向けた。「夏輝の母親、陽子は満足に結婚式も挙げられなかった。だからせめて娘の結婚の時ぐらいはちゃんとした式や宴を出してやりたい、って考えてる。そうだろ? 夏輝」
「ミカさんは、何でもお見通しなんですね……」
「あの子、意外に古風なところ、あるからね」
「俺、夏輝を幸せにしてやることはもちろんだけど、こいつの母ちゃんも一緒に幸せにしてやりたい。そう思って……」修平がかしこまって言った。
「えらいぞ、修平君」ケンジは立ち上がり、修平の横に立って肩を叩きながら言った。「今の言葉、陽子先輩に聞かせてやりたいよ」
「その気持ちが伝えられればいいんだろ? 何もあたしたちに気を遣わなくてもさ」
「君たち自身が結婚を心から喜ぶことが、一番大事なこと。そう思うけどね」ケンジは微笑んだ。
「あたしたちは、あんたたちを祝福するために、式に出席するよ。それでいいだろ? 媒酌人なんて形ばかりのものに気を遣ったり、お金を使ったりすることないよ」
「あ、ありがとうございます」二人はそろって涙ぐんだ。
「陽子だってわかってくれる。違うことにお金を使いなよ。もっと大切なことにさ」ミカは微笑んだ。
「それから、」夏輝が指で涙を拭いながら顔を上げた。「ケンジさん、感謝してます。本当にありがとうございました」
「え? 何? 何のことだい?」
「あたしのお母ちゃんを抱いて下さって……」
「な、なんでそれを!」ケンジは慌てた。
「お母ちゃん、あれからとっても穏やかな表情に変わったんです」
「穏やかな表情?」ミカが言った。
「はい。それまでは、どんなに笑ってても、どこかに陰があった、っていうか、心の底から嬉しそうな顔をしない、っていうか……」
「さすが娘だね」ミカは感心してうなずいた。
「でも、ケンジさんに抱かれた日から、お母ちゃん、とっても無邪気に笑うんです。娘のあたしが言うのも変なんですけど」
「そ、そうなのか?」
「きっと、お母ちゃん、死んだお父ちゃんと二人で暮らしていた時って、そんな顔で笑ってたんだと思います」夏輝は一度目を伏せ、すぐに顔を上げてまた涙ぐみながら笑った。「本当にありがとうございました」
ケンジは頭を掻きながら言った。「陽子先輩を抱いたのは僕だけど、彼女の心を癒したのは一樹さんだよ。君のお父ちゃんだ」
「はい。きっとそうだと思います。あたしも。でも、」夏輝はケンジの目を見つめた。「ケンジさんがそれを実現して下さったのも事実。ケンジさんがお母ちゃんを抱いて、いい気持ちにさせて下さったから、お母ちゃんはかつてのお父ちゃんへの想いを甦らせることができたんです。ケンジさんが恩人であることに変わりはありません。あなたでなければできなかったこと……だと思います」
ケンジはまた頭を掻いた。
「お母ちゃんの中に、やっとお父ちゃんが帰ってきた……。そんな気がするんです」
「本当に母親思いの娘だね、夏輝は」ミカは微笑んだ。「大事にしてやりなよ、修平」
「はい」修平は力強い返事をした。
「おめでとう、夏輝ちゃん、修平君」ケンジも笑顔で言った。
◆

『シンチョコ』の駐車場に植えられたプラタナスの実が小さく育ち始めていた。
ケネスとマユミは、店の入り口の前に立っていた。
「健太郎も春菜さんも、きっと成長して帰ってくるよね」
「そうやな」
半年間のヨーロッパでの修行を終えて、健太郎が春菜とともに帰ってくる日だった。
ほどなくタクシーが駐車場に入ってきて停まった。後部座席から健太郎が外に出た。そして後から車を降りる春菜に手を貸した。
健太郎は背筋を伸ばし、両親の方を振り向いて言った。「ただいま、父さん、母さん」
「お帰りなさい」マユミが言った。ケネスは車に近づき、開けられたトランクから大きな二人の荷物を取り出した。
「お父さん、お母さん、ただいま戻りました」春菜が丁寧に頭を下げた。
別宅のリビング、暖炉の前で、四人はテーブルを囲んでいた。ヨーロッパ土産のたくさんの種類のお菓子が真ん中に並べられていた。
「どうやった? 本場の修行は」
「半年分以上の収穫があったよ」
「ずっとパリにいたんでしょ?」
「うん。まあ、そこで基本的には修行をしたんだけどさ、そこのだんながけっこうあちこち行って来い、って言って俺たちを追い出すんだ」
「追い出す?」
「そう。バウムクーヘンやザッハトルテはドイツに行って、ティラミスやパンナコッタはイタリアで、っていう感じさ」
「二人であちこち回ったの?」マユミが訊いた。
「うん。いつも一緒だよ、もちろん。っていうか、俺、英語だめだし、ルナがほとんど通訳だった。しかもパリでクイニーアマンの作り方を二人で習った時なんかさ、ルナは俺より生地の作り方が上手だって言われて、俺、かなり悔しかった」
「あははは、性格なんじゃない? 春菜さんの完璧主義の賜だよ」マユミが愉快そうに言った。
「春菜さんは英検二級の資格持っとるんやったな。そう言えば」
「は、はい、一応。でもヨーロッパでは英語が通じないところもいっぱいあって、苦労しました」
「腕のええ菓子職人にもなれそうやな。春菜さん」
春菜は照れてうつむいた。
「あちこち行ってみて、俺が一番気に入ったのは、やっぱりチョコレート。ベルギーのゴディバだね。これこれ」健太郎はテーブルの上の箱に手を伸ばした。
「あ、それ母さんも好きだよ。トリュフ ハニーロースト アーモンドがお気に入り」
「わいも、あそこのトリュフは好きやな。特にトリュフ カプチーノが絶品や」
「ですよね。もう口の中でとろけるあの甘さというか……」
「春菜さんもファンになったんやな」
「とにかく奥深いよ。お菓子ってさ」
「やっと気づきよったか。遅いわ! 25にもなって」
「そういう父さんはいつお菓子の奥深さに気づいたの?」
「わいは、もう小学校に上がる時には気づいとったで」
「ほんとかよ。単にチョコレート好きの坊主だったんじゃないの?」
「そうとも言う」
四人は笑い合った。
「でも、良かった」
「何が?」
「修平と夏輝の結婚式に間に合って」
「そうやな。式は12月、言うとったで」
「ウェルカム・スイーツとウェディングケーキと引き出物、全部任されたんだよ、うちに」
「そりゃそうだよ。町で一番名高いスイーツ屋だからね、うちは」
「それに、相変わらず春菜モデルのアソートの売れ行きは好調やで」
「ほんとですか? 嬉しい!」
「真雪モデルと張り合って、二つともよう売れとる。ありがたい話や」
「きっとまた春菜ファンが押しかけるね、春菜さんが帰ってきた、って知ったら」
「そうやな。頼んだで、春菜さん」
「任せてください、お父さん。いつでもピンクのメイド服着て接客します。私」
「そうやった、大事なこと言わなあかんかった」
「どうしたの? 父さん」
「おまえらの結婚式、2月14日に決めたよってにな」
「そうなんだ」健太郎がにっこりと笑って、春菜の顔を見た。春菜もますます顔を赤らめて嬉しそうにうつむいた。
「どこで?」
「秘密や。っちゅうか、この件に関してはおまえらには口出しさせへんからな、そのつもりでおるんやぞ」
「な、なんでだよ」
「問答無用や。わいら実行委員に任せとき」
「な、何だよ、その実行委員って」
「実行委員長のケンジの命令や。本人たちには直前まで極秘にしとけ、っちゅう」
「まったく……」
◆

「今さらだけど、ペットショップにいながら真雪って、」龍が店の中のトリミング・ルームの椅子に座って言った。
「何?」真雪はトイプードルのブラッシングを手際よくこなしながら応えた。
「今でもあっちこっちの牧場や畜産関係者から声がかかったりするんだろ?」龍はテーブルに真雪の好きなパック入りのカフェオレを置いた。「ここに置いとくよ」
「ありがとう。そうなんだ。週に二回ぐらいの割合で、あたしこの店を空けなきゃなんない」
「変わってるよね。真雪の職業って」龍は店の前でカフェオレと一緒に買ったパック入りの牛乳にストローを挿して咥えた。
「『家畜人工授精師』の免許持ってるしね」
「他にも君は『動物看護士』や『犬訓練士』の資格も持ってるじゃん」
「動物、好きだからね。あ、龍も大好きだよ、もちろん」
「俺と牛をいっしょにしないでくれよ」
「そう言えば、こないだ、龍、しゅうちゃんの学校に取材に行ったんだって?」
「うん。教育現場の今をうちの新聞で特集してるからね。修平さんにもいろいろ話を聞いたよ」
「そう。学校の先生って、ずっと学校にいるから、大変だろうね」
「いや、登校をしぶる生徒がいたり、町でなにかしでかす生徒がいたり、けっこう表に出て行くことも多い、って言ってた。そっちの方が大変そうだったよ」
「そうか。なかなかあたしたちには見えない部分だね、そういうの」
「それを伝えるのが僕らの役目だよ」
「龍、活躍してるね」
「まだまだ駆け出しさ。3年目だからね」
龍は高校卒業後、地元の新聞社に就職した。得意のカメラと軽いフットワークで、町のあちこちの出来事を幅広く伝えるジャーナリストの道を歩んでいた。
「龍、」真雪がブラッシングの手を休めて言った。
「何だい?」
「再来月、夏輝とそのしゅうちゃんの結婚式だね」
「そうそう。めでたいね」
「あの二人もつき合い長くて、途中いろいろあったらしいけど……」
「お似合いだよ。そう言えばあの二人、夏に俺んちに来て、父さんと母さんに仲人役を頼んだらしい」
「へえ、そうなの」
「でも断ったってさ。父さんたち」
「なんで?」
「そんなガラにもないこと、できるか、って母さん言ってた」
「ふふ、ミカさんらしいね」
「で、結局人前結婚式でこぢんまりやることにしたんだよね」
「それでも招待客は100人近くいるらしいから、大したもんだよ」
「二人の人徳だね」
「そうだね」真雪はまた犬のブラッシングを再開した。「あたしたちの式、どうなってるの?」
「父さんと母さんそれにケニー叔父さんとマユミ叔母さんが何か企んでるらしいけど……」
「どんな式を考えてるのかな」
「俺にも情報は掴めてないんだ。いろいろ探りを入れてはいるんだけど……」
「極秘で進めてるらしいね」

「今わかってるのは、来年の2月14日にやるってことだけ」
「2月14日?」
「そうさ。敢えてベタなバレンタインデー。同時にチョコレートの日」
「実行委員長は父さん。企画部長はケニー叔父さん」
「何それ。大げさだね」真雪は笑った。
◆
「つまり、」健太郎が『海棠スイミングスクール』の玄関前で呟いた。「ここで俺たちの結婚披露宴をやろう、っていうの? ケンジおじ」
スクールの看板の下に大きく『2月14日結婚披露宴! 健太郎-ハートマーク-春菜、龍-ハートマーク-真雪』と書かれた横断幕が下げられている。
「な、何だかとっても恥ずかしいんだけど」龍も同じようにそれを見上げて言った。「こんな往来に……」
「嬉しいだろ? 嬉しいよな。二組同時結婚披露宴だぞ。こんなにめでたいことはない。な、ミカ」
「そうだぞ、こんなこと滅多にない機会だ。もっと素直に喜んだらどうだ、二人とも」
「こんなこと、何度もあってたまるかよ」龍が言った。
「しかし、これ見たらルナ、どう思うかな……」健太郎はため息をついた。
「真雪にも、俺説明する勇気ないよ」龍も言った。





































