Twin's Story 5 "Liquor Chocolate Time"~Epilogue
《8 思い出と共に》
二度目のシャワーを浴びたケンジとマユミは、ソファに並んで座った。ケンジがテーブルに置かれたワインのボトルを持ち、手際よくコルクを抜いて二つのグラスに注ぎ、一つをマユミに手渡した。

「俺たちさ、」
「ん?」
「酒には手を出さなかったよな」
「そう言えばそうだね。まじめだったよね」
「ま、お前はチョコさえあれば満足なヤツだったし、」
「ケン兄もコーヒーで十分って感じだったしね」
ケンジはワインを一口飲んだ。
「でも、ケン兄、」マユミが少し睨んだようにケンジを見た。
「な、何だよ」
「あなた、ミカ姉さんと初めてエッチした時、泥酔状態だったんだって?」
「えっ? な、なんでそれを?」
「ミカ姉さんが教えてくれた。ひどいよ、ケン兄」
「反論していいか? マユ」
「言い訳? 一応聞いてあげる」
「あの時俺、酔っ払ってて、コトの最中ミカをお前だとずっと思い込んでたんだ」
「え? あたし?」
「そうだぞ! ほら、ミカってお前にちょっと似てるじゃん。だから酔っ払って感覚が鈍っていたあの時は、ずっとお前を抱いているつもりでいた」
「ミカ姉さん、かわいそう……」
「最後の瞬間に気づいて、慌てて抜いた」
「抜いた?」
「結局、彼女の腹や胸に出しちまった」ケンジはうつむいて赤くなった。「さっきみたいに、た、大量に……」
「最低!」
ケンジは最後の一口をぐいっと飲み干した後、グラスをテーブルに置いて大声で言った。「俺、謝ったぞ、死ぬ程恥ずかしくて、申し訳ない気になって、何度も土下座した。もう、酔いなんかいっぺんに吹っ飛んじまった」
「それって、あたしたちの19の誕生日の話でしょ?」
ケンジは静かな口調に戻った。「そう……俺、一人で誕生日を迎えるの、初めてだったから、お前がいない誕生日、初めてだったから、寂しくて、切なくて、お前が恋しくて……」
「実はね、あたしもその日、ケニーに抱かれたの、っていうか、抱いてもらったの」
「知ってる。ケニーに聞いた」
「あたしは酔ってはいなかったけど、ケニーがあたしのカラダを愛してくれる、その方法が、ケン兄とほとんど同じで、あたし、ケン兄、ケン兄ってずっと叫んでた」
「ケニーはどんな気持ちだったんだろうな……」
「あたしも後でケニーに対して、とっても申し訳なく思った。それでも彼は嫌がることもなくあたしを抱いて、最後までいってくれたんだよ」
「そうだったのか……」
「あの時は本当に……寂しかった」
「俺もだ、マユ……」

ケンジはマユミの持っていたグラスをそっと取り上げ、テーブルに戻した。そしてマユミの身体を抱き寄せ、キスをした。マユミの身体に巻かれていたバスタオルがはらりと落ちた。
二人はそこに立ったまま、全裸で抱き合った。胸を合わせ、唇を合わせ、ケンジはマユミの身体を強く抱きしめた。そしてそのままベッドに倒れ込むと、自ら仰向けになってマユミを促した。
唇へのキス、首筋へのキス、乳房へのキス……。下になったままケンジはマユミの身体を愛撫した。マユミはケンジの唇に合わせて身体を移動させた。「ケン兄って、本当にキスが好きだね」
「好きだ。お前を味わうのが、大好きなんだ」
「あたしもケン兄のキスは大好きだったよ」
「今も?」
「もちろん、今も」
ケンジはマユミの頭を手で引き寄せ、ゆっくりと味わいながら彼女の唇を舐め、吸った。
静かに口を離したケンジはマユミの頬を両手で包みこみながら言った。「マユ、俺の顔に跨ってくれないか」
「えー、ケン兄窒息しちゃうよ?」
「死なない程度に。俺、Mだし」ケンジもマユミも笑った。

「わかった」マユミは身体を起こし、ケンジの口に後ろ向きで自分の秘部をあてがった。「んんっ……」ケンジが少し苦しそうに呻いた。マユミは少し身体を浮かせて、ケンジの舌が自由に動かせるようにした。「あああ……」
ケンジの舌が谷間の入り口を舐め始めた。マユミは腰を動かしながら、ケンジの舌を自分の感じる部分に導いた。ケンジは一生懸命になってそのマユミの中心を愛撫した。まもなくマユミの谷間から雫が溢れ始めた。ケンジの口の周りはぬるぬるにされていった。それでもケンジはマユミの腰を両手で押さえ、自分の口に彼女の秘部を押しつけながら舌や唇を懸命に動かし続けた。
やがてマユミは身体を倒し、ケンジのペニスにそっと手を添えた。そしてひとしきり舐め上げた後、ゆっくりと口の中にそれを含んだ。「んんっ!」ケンジが身体をよじらせた。しかし彼はマユミの谷間から舌を離すことなく刺激し続けた。マユミの口の動きが激しくなった。
お互いがお互いを高め合い、二人の動きを激しくしていった。「んんんーっ!」「んんっ! んんん……」二人は言葉の代わりに大声で呻き続けた。
はあはあはあ……マユミがケンジから身体を離した。ケンジは起きあがり、マユミを仰向けにした。そして彼女の両脚を持ち上げ、荒い呼吸のまま言った。「マユ、お前に入りたい、入っていい?」
「うん。いいよ。入ってきて、あたしに」
ケンジはゆっくりとペニスをマユミの谷間に埋め込ませ始めた。「ああ、あああああ……、ケン兄……」
「マ、マユ……」
「あ、あたし、この瞬間がと、とても好き……」マユミが喘ぎながら言った。
「お、俺もだ、マユ」
「あ、あなたと一つになる瞬間が、とても好き」
「マユ」
ほどなくケンジはペニスを彼女の中に埋め込んだ。そして静かに腰を動かし始めた。「ああ、ああああ、感じる、いい気持ち、ケン兄……」
「んっ、んっ、んっ……」ケンジは次第に動きを速く、大きくしながら、ますます息を荒げてマユミを愛し続けた。
はあはあはあはあ……マユミの身体が熱くなり、ケンジ同様呼吸も速くなっていった。「も、もうすぐイきそう、ケン兄……」
「よし、マユ、イこう、いっしょに」
「うん」マユミは固く目を閉じて大きくうなずいた。
ケンジの腰の動きがさらに激しくなった。「ああああ! イく、ケン兄! イくよ、イっちゃうーっ!」「ああ! お、俺も、マユ、マユっ!」
ケンジの身体の中から熱いものが一気にわき上がってきた。「ぐ、ぐうっ!」
びゅるるっ! びゅくっ! 「ああああ! ケン兄! ケン兄! イってる! あたし、イってるっ!」マユミは身体を痙攣させ叫んだ。
びゅくっ! びゅくびゅくっ! びゅるるっ! 「ぐううううっ! マ、マユっ!」ケンジも身体を硬直させながら何度も何度も脈動し続けた。どくっ! ……どくどくっ! ……どくん、…………どくん…………どく…………。
毎年、夏が来ると、私たちは二人だけで会い、過去を懐かしみながら温もりを確かめ合います。兄妹の関係としては少し、いえ、かなり特異ですが、そのときだけは誰にも邪魔されずにあの頃の心のアルバムを開いて、さまざまな思い出といっしょに甘い時間を共有し、味わうのです。そう、兄が昔買ってくれたアソート・チョコレートのように。
-Twin's Story 「Chocolate Time」第1期 完-
2013,8,3 最終改訂脱稿
※本作品の著作権はS.Simpsonにあります。無断での転載、転用、複製を固く禁止します。
※Copyright © Secret Simpson 2012 all rights reserved
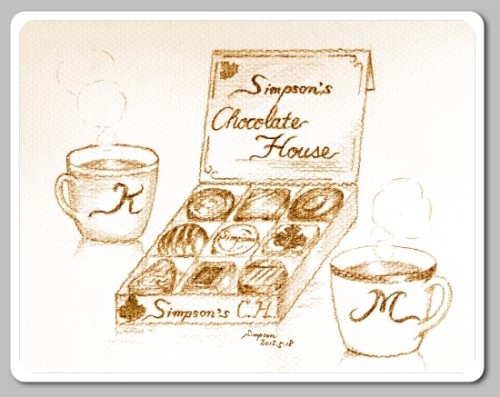
《Liquor Chocolate Time あとがき》
最後までお読みいただき感謝します。
意気地なし、と言われても仕方ないとは思いますが、僕はケンジとマユミを別れさせることができませんでした。
このシリーズを手がけた当初は、単に若い双子の兄妹がいちゃついて、くっつきあって……。という行為そのものを楽しむための物語を書いている、という意識が強かったような気がします。ところが、話を進めていく内に、ケンジとマユミが同じ時間を過ごすことで、彼ら同様、作者である僕自身にも二人が自分の家族のような、子どものような感覚に襲われ始めました。物語の登場人物に強く感情移入していったわけです。こういうのを『ピグマリオン効果』と言います。
衝動的に付き合い始めた二人は、しかしかなり「常識的な」人間だったので、成長とともに兄妹で愛し合うことに罪悪感を持ち始める。つき合い続けても結婚することはできない。理屈ではそうわかっていても、もう兄妹以上の感情でいっぱいだった二人にはそれが簡単にできないことは容易に想像できます。しかし、二人にとってはとても幸運なことに、親友のケネスの存在がありました。
ここまでずっと二人の間にいて、二人の想いを理解し、常に二人の気持ちを尊重していたケネスがいなければ、ケンジとマユミは遠い距離に隔てられ、再会までの長い時間を待たなければならなかったでしょう。ケネスは海棠兄妹にとっては間違いなく「恩人」です。
ケンジとマユミがそれぞれ人生の伴侶を持ち、分別もついてしっかり大人の世界に足を踏み入れた時、二人の関係は、言ってみれば「昇華」したように思います。恋人同士ではなく兄妹に戻った。しかし過去に愛し合った想いはずっと残っていて、お互いが癒し合える関係になった、というわけです。無論そうやって二人がその後も抱き合うことができるのはケネスとミカの心の広さがあってのこと。現実にはあまり起こりえないことかもしれませんが、こういう夫婦の在り方は一つの理想です。
年に一度、夏の二人の記念日にケンジとマユミが交わす会話は、作者である僕にとっても、遠い昔の甘い思い出を甦らせてくれます。彼らが部屋で、海で、街で過ごした一つ一つの場面が、ここまでくると思い出になってしまっているのです。変ですね。たかだか小説の中の世界なのに。
Simpson




































