真雪の独白~二日目の夜

1.
私の人生最大の罪をお話しします。
今から五年あまり前、二十歳になったばかりの私は、一回り以上も年上の男性と過ちを犯してしまいました。相思相愛の龍という恋人がいるにも関わらず、私はこの妻子ある男性に抱かれてしまったのです。
その板東 俊介という男性は当時35歳。実年齢よりもずっと若く見え、まだ20代でも通用するような容姿。足が長く、標準以上のイケメンで、彼に関わる女性の多くがこの人と親しくなりたいと思うような魅力を持つ男性でした。
私は高校を出て通っていた専門学校の必修カリキュラムの一つ、冬の宿泊実習のために、仲間の20人ほどと共に郊外の水族館に一週間滞在していました。
そこで私たちは研修主任という立場の板東と出会いました。彼は私たちの研修全般の世話を担当し、自らも講師として実習に携わり、実習生にもいつも優しく親切に接していて、仲間内、特に女子学生から高い好感度を得ていました。
実習が始まって四日目の夜、私はいきなり板東に夕食に誘われました。
丁度その時、いつも何不自由なく好きな時に会うことができていた恋人の龍と離ればなれになっていて、前の晩には彼に電話も繋がらなかったことから、私はその寂しさを紛らそうと彼の誘いを受けてしまいました。そしてディナーで慣れないアルコールを勧められ、調子に乗って飲んでしまったこともあって、その後私は板東に連れられてラブホテルに入ることを拒みませんでした。
その時の私は、会ったばかりの言わば行きずりのこの板東という男性に抱かれることに抵抗がなかったかというと、残念ながらそこまで拒絶感を持ってはいなかったような気がします。恋人に会えない寂しさと身体の火照りが並大抵でなく、その息苦しさをどうしても解消したくて、私はこの人に自分の心と身体を慰めてもらいたいと思っていたのです。今思えば、自分でもどうしてそれほどまで怪しい熱さになっていたのか、全く不可解で理解に苦しみます。
龍の優しさやその身体に包まれて伝わってくる彼の温かさ、龍と一緒に高まって感じるエクスタシーの弾けるような喜び、龍の胸に顔を埋めて過ごす最高に幸せな癒やしの時間。それをこの板東に求めていたのです。龍とは似ても似つかないこの男性に。
その全ての感覚、感情が唯一龍でなければ手に入れることができないということは最初から解っていたはずなのに、私はふらふらとこの男にその幻覚を求め、満たされようとしていたのです。その結果私は、弱冠16歳の多感な時期の恋人龍の心を、深く傷つけてしまいました。
私の手は、いつの間にか龍の手を自ら離してしまっていたのです。
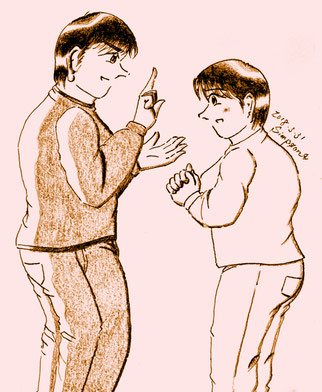
そして、次の日も……。
板東はその夜、水族館の宿舎で食事とシャワーを済ませた私をわざわざ部屋に訪ね、自分の部屋においで、と優しく声を掛けてきました。私は彼の呪文のようなその言葉にふらふらと従い、彼がこの職場でプライベートな空間として使っているさして広いとは言えない個室に招かれました。
その6畳ほどの部屋には、幅1㍍程の作り付けのキャビネット、パソコンの載せられたデスク、そして一人用にしては少し広めのベッドが備えられていました。ベッドの横には引き出しのついたサイドテーブル。その上に電気スタンドと空になったマグカップがなぜか二つ置いてありました。
私は自ら着ていたスウェットを脱ぎ、下着姿になりました。前日、ホテルでの情事では期待していたように心も身体も癒やされることはなく、私の中で蠢いていた熱い疼きが残ったままでした。きっとそれはお酒のせいだったのだ、と思い込んでいた私は、この日はもしかしたらこの男性にちゃんと心と身体を慰めてらえるかもしれないと思い、自分の意思で裸になったのです。
板東にしてみれば、前日落とした女が、次の日もこうして自分の目の前で自ら服を脱いだのですから、もうすっかり思い通りにコトが運んでいると確信したに違いありません。

その前日、ホテルでは板東はベッドの枕元に置いてあった避妊具に手をつけることもなく、クライマックスの時、そのまま私の中に躊躇いなく射精しました。ある意味納得の上でこの男性を受け入れたにも関わらず、自分の身体の中に出されたことは私にとってかなりの衝撃で、激しい拒絶感を覚えました。無慈悲に放出され、残された板東の精液が、自分の身体だけでなく心までもどんどん蝕んでいくような気がしたのです。
しかしそんな私の気持ちを知るはずもなく、また解ろうともせず、その夜板東はその後私に甘い言葉を掛けるでもなく、さっさと背を向けて眠ってしまいました。私はその男の姿を見て、今更ながら自分がどうしてこんなことをしたのかと激しく後悔し、一人バスルームのシャワーで中に出されたものを必死で洗い流しました。全身も何度も何度も洗って、あの男の残り香を消そうと躍起になっていました。
そんなことをしておきながら私は次の夜も板東に誘われ、その部屋に足を踏み入れてしまったのです。すでに私の中にあった理性というスイッチが切れてしまっていたのです。
それでも今夜はたとえセックスまでいくにしても、この人にはちゃんと避妊具を使ってもらおう、などと自分の都合のいいように考えていました。
でも、それは甘い考えでしかありませんでした。板東は私のことを実習で知り合い、軽い気持ちで声を掛け、その結果思い通りにのこのこついてきた尻の軽い女としか思っていなかったことでしょう。熱い身体を持てあましながらも、ひどくナーバスになっている私の気持ちなど、この男に解るはずはなかったのです。
――その全てにおいて。




































